
こんにちは。
空き家活用コンサルタントの藤本と申します。
普段は大阪を拠点としております。
ご縁をいただき、全国各地の空き家問題のご相談に対応させていただいております。
さて、この記事をお読みのあなた。
おそらく北海道網走市にある空き家のことで、何かしらの悩みや課題を抱えていらっしゃるのではないでしょうか。
網走市といえば、流氷観光で有名ですね。
オホーツク海に面し、網走湖や能取湖といった美しい湖沼群。
広大な農地、そして豊かな海の幸。
厳しい冬のイメージもありますが、夏は冷涼で過ごしやすい。
大自然の恵みを存分に感じられる、素晴らしい土地だと思います。
網走監獄やオホーツク流氷館などの観光スポットも人気です。
美味しいものがたくさんある「食の宝庫」でもありますね。
しかし、その一方で、網走市もまた、日本の多くの地方都市が直面している「空き家問題」と無縁ではありません。
人口の減少。
高齢化の進行。
そして都市部への若者の流出…。
様々な要因が絡み合い、かつて家族の暮らしを支えた家々が、主を失い、静かにその数を増やしている。
それが現状ではないでしょうか。
「親が住んでいた網走の実家、相続したけれど、自分は道外に住んでいて…」
「もう何年も空き家状態で、たまに様子を見に行くだけ。
管理も大変だし、固定資産税の負担も馬鹿にならない」
「売りに出そうにも、家が古すぎて買い手がつくか分からない。
リフォームするお金もないし…」
「解体するしかないかと思うけど、費用がいくらかかるか心配。
そもそも解体して更地にしても、その後どうすれば…」
「近所の人に迷惑をかけていないか、いつも気がかりだ」
もし、これらの言葉に少しでも心当たりがあるなら。
この記事は、きっとあなたのためのものです。
このページでは、網走市の空き家を所有するあなたが直面するであろうあらゆる問題点を徹底的に掘り下げます。
- なぜ空き家を放置してはいけないのか? その深刻なリスクとは?
- 空き家対策で陥りがちな失敗パターンとその回避策は?
- 売却、賃貸、解体といった一般的な解決策のメリット・デメリットを網走市の状況に合わせて徹底比較
- そして、私、藤本が提案する「費用負担を限りなくゼロに近づける」3つの具体的な活用戦略とは?
- さらには、相続や税金、補助金といった関連情報まで
…網走市の空き家問題について、包括的に、そして深く掘り下げて解説していきます。
空き家問題は、あなたが思っている以上に根が深いものです。
様々な要素が複雑に絡み合っています。
表面的な情報だけでは、本質的な解決には繋がりません。
この記事を最後までお読みいただければ。
あなたの網走の空き家に対する漠然とした不安が解消されるはずです。
「何をすべきか」「どう動けばよいか」が明確に見えてくるでしょう。
そして、その先には、負担から解放され、心穏やかな未来が待っているかもしれません。
少し長い内容になりますが、どうぞ、最後までお付き合いください。
あなたの空き家問題を解決する「最適解」を、一緒に見つけ出すお手伝いができれば幸いです。
なお、この記事の執筆にあたっては。
全国で100軒以上の空き家再生実績を持つ「日本の空き家研究所」代表の竹田さんの監修と、豊富な事例提供も受けています。
机上の空論ではない、実践に基づいた情報をお届けします。
【第一章】見て見ぬふりはもう限界!網走市の空き家放置がもたらす深刻な危機

「まあ、誰も住んでいないだけだし、特に誰にも迷惑はかけていないだろう」
「そのうち、時間ができたら考えよう」
網走市にある空き家に対して、もしあなたがこのように考えているとしたら。
それは非常に危険なサインかもしれません。
その「放置」という選択が、気づかないうちに、あなた自身、そして地域社会全体にとって、取り返しのつかない問題を引き起こす可能性があるのです。
なぜ、空き家を放置してはいけないのでしょうか?
その理由を、多角的に、そして深く掘り下げていきましょう。
1-1. 経済的リスク:あなたの財布を蝕む「見えないコスト」と「突然の負担増」
空き家を所有し続けることによる経済的な負担。
これは、放置期間が長引くほど重くのしかかってきます。
単に「もったいない」というレベルではありません。
家計を圧迫し、将来設計にも影響を与えかねない深刻な問題なのです。
毎年課税される固定資産税・都市計画税という「確実な支出」

まず、避けて通れないのが固定資産税です。
これは、毎年1月1日時点で土地や家屋を所有している人に課される市町村税です。
(網走市の場合は網走市が課税します)
その土地や家屋を実際に利用しているかどうかは関係ありません。
所有しているというだけで納税義務が発生します。
さらに、もしあなたの空き家が網走市の「市街化区域」にある場合。
固定資産税に加えて都市計画税も課税される可能性があります。
都市計画税は、道路や公園、下水道などの都市計画事業の費用に充てるための目的税です。
これらの税額は、固定資産税評価額に基づいて計算されます。
固定資産税評価額は、3年ごとに評価替えが行われます。
土地の時価や建物の経年劣化なども考慮されますが、空き家だからといって極端に安くなるわけではありません。
網走市内の具体的な税額は、物件の状況によって大きく異なります。
例えば、所在地(市内中心部か、郊外かなど)。
土地の広さ。
建物の構造(木造、鉄骨造など)、床面積、築年数などです。
一般的には、年間で数万円から十数万円、場合によってはそれ以上の税金を支払い続けることになります。
考えてみてください。
仮に年間10万円の税金を払っているとします。
- 5年間放置すれば 50万円
- 10年間放置すれば 100万円
- 20年間放置すれば 200万円
これは、決して小さくない金額です。
何の収益も生まないどころか、様々なリスクを抱える対象に対して、これだけの金額を払い続ける。
まさに「負の資産」に、お金を注ぎ込み続けている状態と言えるでしょう。
特定空家指定による「税金6倍」のリスク – 突然の負担急増
さらに深刻なのは、この固定資産税が、ある日突然、大幅に増額されるリスクがあることです。
その引き金となるのが、「特定空家」への指定です。
「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)」という法律があります。
これに基づき、市町村は、管理不全で危険な状態や、周辺環境に悪影響を及ぼしている空き家を「特定空家」として指定できます。
そして、所有者に対して改善を求めることができるのです。
どのような状態が「特定空家」に該当する可能性があるか。
もう少し具体的に見てみましょう。
- 構造の危険性:建物が傾いている、屋根や壁が崩れ落ちそう、基礎が沈下しているなど、倒壊・崩壊の危険性が高い状態。
- 衛生面の悪化:ゴミが散乱・放置されている、悪臭が発生している、害虫(ハチ、ネズミ、ゴキブリなど)が大量発生しているなど。
- 景観上の問題:外壁の落書きがひどい、窓ガラスが全て割れている、庭の雑草が異常に繁茂しているなど、周辺の景観を著しく損なっている状態。
- その他不適切:立木が隣地に越境して危険、動物が住み着いて騒音や糞尿被害があるなど、周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼしている状態。
(※網走市がどのような基準で判断するかは、市のガイドライン等をご確認ください)
もし、あなたの空き家がこれらの状態に該当すると判断され、網走市から「特定空家」として指定されてしまうと。
さらに状態改善の「勧告」を受けてしまうと…
住宅用地の特例措置が適用されなくなります。
これはどういうことか?
通常、住宅が建っている土地は、税負担が軽減されています。
(200㎡以下の部分は、固定資産税の課税標準額が1/6に、都市計画税が1/3に減額)
この特例が解除されるため、土地にかかる税金が、単純計算で固定資産税は最大6倍、都市計画税は最大3倍に跳ね上がる可能性があるのです。
例えば、これまで土地の固定資産税が年間3万円だったものが、一気に18万円になる。
そんな事態が起こり得るわけです。
これは、所有者にとって壊滅的な負担増と言えるでしょう。
特定空家への指定は、決して他人事ではありません。
全国的に空き家対策が強化される中、網走市でも、危険な空き家に対する監視の目は厳しくなっていると考えられます。
維持管理に伴う継続的な支出 – チリも積もれば山となる
税金以外にも、空き家を維持するためには、様々な費用が発生します。
目に見えにくいコストですが、積み重なると無視できません。
- 交通費・滞在費:
遠方(道外や札幌など)から網走市の空き家を管理するために、定期的に訪れる場合の費用。
(飛行機代、JR代、高速料金、ガソリン代、宿泊費など)
年間数回でも、かなりの負担になります。
- 管理委託費:
地元の方や業者に管理(見回り、草むしり、換気など)を依頼している場合の費用。
月額数千円~1万円程度でも、年間では大きな額に。
- メンテナンス費用:
庭木の剪定、簡単な修繕、雪下ろし(必要な場合)などを業者に依頼すれば、その都度費用が発生します。
- 火災保険料など:
空き家でも火災リスクに備える保険料は必要です。
(空き家は保険加入が難しかったり、割高になったりすることも)
- 水道光熱費(基本料金):
電気や水道を完全に止めていない場合、基本料金がかかります。
特に冬場の凍結防止ヒーターは電気代がかさみます。
- 町内会費など:
地域によっては、空き家でも支払いを求められる場合があります。
これらの「見えないコスト」も合わせると。
空き家を「ただ持っているだけ」で、毎年多額の支出を強いられていることになるのです。
1-2. 物理的リスク:急速な劣化、倒壊・損壊、災害時の脆弱性
お金の問題以上に深刻かもしれないのが、空き家の物理的な劣化です。
そして、それに伴う様々な危険性です。
特に、自然環境の厳しい網走市では、そのリスクはより高まります。
「空き家は傷みやすい」は本当か?そのメカニズム
「人が住まないと家は傷む」とよく言われます。
これには明確な理由があります。
換気不足:湿気の滞留と結露
締め切られた室内では空気が循環しません。
湿気がこもりやすくなります。
これが木材の腐朽、壁紙の剥がれ、カビの発生、金属部分の錆などを引き起こします。
特に梅雨時期や、冬場の結露には注意が必要です。
日常的なメンテナンスの欠如
雨漏り、壁のひび割れ、建具の不具合。
そんな小さな問題が放置され、時間とともに大きな損傷へと発展します。
排水溝の詰まりなども、建物の基礎に悪影響を与えることがあります。
害虫・害獣の侵入と営巣
人の気配がない家は、ネズミ、イタチ、アライグマなどの小動物や、ゴキブリ、ハチ、シロアリなどの害虫にとって安全な隠れ家となります。
これらが柱や壁、断熱材を傷つけたり、糞尿で汚したりすることで、建物の劣化はさらに進みます。
シロアリ被害は特に深刻です。
これらの要因が複合的に作用します。
空き家は、人が住んでいる家よりも格段に速いスピードで劣化していくのです。
網走の厳しい自然が追い打ちをかける
そして、網走市の厳しい気候条件。
これが、空き家にとってさらなる試練となります。
水道管凍結・破裂:冬場の最大の敵
マイナス10℃以下も珍しくない網走の冬。
適切な水抜き措置がされていない空き家の水道管は、ほぼ確実に凍結・破裂します。
春に水が噴き出し、家全体が水浸しになる大惨事も。
修復には高額な費用がかかります。
積雪の重圧:
屋根に積もった雪の重みは相当なもの。
老朽化した屋根構造に大きな負担をかけます。
雨漏り、歪み、最悪の場合は倒壊の危険も。
屋根からの落雪が、隣家や通行人に被害を与える可能性もあります。
凍上・凍害による基礎・外壁へのダメージ
地面の凍結・融解(凍上)は、建物の基礎を傾かせることがあります。
外壁材が凍結・融解を繰り返す(凍害)と、ひび割れや剥離を引き起こします。
風雪・塩害による建材の劣化
オホーツク海からの強い風や吹雪は、屋根材や外壁を傷つけます。
飛散した建材が被害を与えることも。
海岸に近いエリアでは、潮風による塩害で金属部分が錆びやすくなります。
倒壊・破損による第三者への加害リスク
老朽化が進んだ空き家は、それ自体が存在するだけで「危険物」です。
もし、台風や地震、あるいは単なる老朽化によって、建物の一部が崩れたり、飛散したりして。
第三者に損害を与えてしまった場合。
その損害賠償責任は、原則として空き家の所有者が負うことになります。
(民法第717条 工作物責任)
「自然災害だから仕方ない」という言い訳は、通常通用しません。
所有者には、建物を安全な状態に維持管理する義務があるからです。
賠償額が高額になるケースもあり、所有者の人生を左右しかねない重大なリスクです。
1-3. 社会的リスク:地域コミュニティへの負の影響
放置された空き家は、所有者だけの問題ではありません。
その存在自体が、地域社会全体にとってもマイナスの影響を及ぼすのです。
これは「社会問題」としての側面です。
景観の悪化と地域イメージの低下
手入れされず荒れ果てた空き家。
これは、単純に見た目が良くありません。
- 雑草が生い茂り、ゴミが散乱した庭。
- 壁が剥がれ、窓が割れたままの建物。
- 放置された古い車や不用品。
このような空き家が地域に点在するとどうなるでしょう?
街全体の景観が損なわれ、活気のない寂れた印象を与えてしまいます。
これは、地域のイメージダウンに繋がります。
観光客の誘致や、移住者の呼び込みにも悪影響を与えかねません。
網走の美しい自然や街並み。
その中に、そのような「負のスポット」が存在するのは、非常に残念なことです。
また、周辺の不動産価値にも影響します。
近隣住民の資産価値を下げる要因にもなり得るのです。
治安の悪化と犯罪の誘発
「割れ窓理論」という言葉を聞いたことがありますか?
建物の窓が割れているのを放置すると。
「誰も地域に関心を持っていない」というサインになります。
やがて他の窓も割られ、さらなる軽犯罪や凶悪犯罪が起こりやすくなる。
そういう考え方です。
管理されていない空き家は、まさにこの「割れた窓」と同じ状況を生み出します。
- 不法投棄のターゲット:
「どうせ誰も見ていないだろう」
そう思われ、粗大ゴミや産業廃棄物などを不法に捨てられやすくなります。
- 不審者の侵入・住み着き:
鍵が壊れていたり、入りやすい状態だと簡単に侵入されます。
ホームレスの寝床になったり、若者のたまり場になったり。
犯罪の拠点として利用される危険性もあります。
- 放火のリスク:
誰もいない建物は、放火のターゲットにされやすい傾向があります。
枯草やゴミが散乱していると、燃え広がりやすくなります。
隣接する建物への延焼リスクも非常に高く、大惨事につながりかねません。
たった一軒の放置空き家が。
地域全体の安全・安心を脅かす存在となり得るのです。
近隣住民とのトラブル発生
空き家の存在は、様々な形で近隣住民とのトラブルを引き起こす可能性があります。
- 越境問題:
庭木や雑草が隣の敷地にまで伸びて迷惑をかける。
屋根からの落雪が隣地に落ちる。
- 衛生問題:
敷地内のゴミから悪臭が発生する。
ネズミや害虫が大量発生し、近隣にまで被害が及ぶ。
- 安全問題:
「建物がいつ崩れるか分からない」
「ブロック塀が倒れてきそうで怖い」
といった不安感を与える。
- 景観問題:
「家の見栄えが悪くて気分が悪い」
といった感情的な対立。
あなたが「迷惑はかけていないはず」と思っていても。
知らず知らずのうちに、ご近所の方々に不安や不快感を与えているかもしれません。
地域全体の価値を下げてしまっているかもしれないのです。
最初は小さな苦情でも、放置され続けることで、住民間の関係が悪化します。
深刻なトラブルに発展することも少なくありません。
特に、昔からお世話になったご近所さんとの関係が悪化するのは、避けたいですよね。
1-4. 将来的リスク:「負動産」化と相続時の問題
現在だけでなく、将来にわたっても。
放置された空き家は様々な問題を引き起こします。
特に、次世代への相続が発生した際に、問題が一気に噴出するケースが後を絶ちません。
資産価値の消失と「負動産」への転落
前述の通り、放置期間が長引くほど、建物の老朽化は進みます。
その資産価値は限りなくゼロに近づいていきます。
いざ売却しようとしても。
- 建物自体には値段がつかず、土地代のみの評価となる。
- 土地代から、建物の解体費用を差し引いた金額での売却となる(マイナス査定)。
- そもそも買い手が見つからない。
という状況になりがちです。
賃貸に出すにしても、多額のリフォーム費用が必要となります。
投資回収の見込みが立たないケースが多いでしょう。
結果として、売ることも貸すこともできない。
解体する費用も捻出できないまま。
税金と管理の負担だけが残り続ける…。
これが「負動産」と呼ばれる状態です。
持っているだけで、お金と手間を奪われ続ける、まさに「負の資産」。
かつては大切な「資産」であったはずの家が。
将来世代にとって「負の遺産」となってしまうのです。
放置は、この負動産化を決定的なものにしてしまいます。
相続時のトラブル拡大:「空き家問題」が「争続問題」へ
もしあなたが、将来、その空き家を誰かに相続させる(あるいは、あなたが相続する)立場にある場合。
問題はさらに複雑化します。
誰が相続するのか?:
誰も住む予定のない、管理も大変な「負動産」。
これを、誰も相続したがらない、というケースは非常に多いです。
相続人間で押し付け合いになり、関係が悪化することも。
管理・費用の負担はどうする?:
複数の相続人で共有名義になった場合。
誰が管理を担当し、固定資産税や修繕費をどのように分担するのか。
これで、必ずと言っていいほど揉めます。
処分方法で意見が対立:
「売りたい」「貸したい」「解体したい」
「いや、思い出があるから残したい」
など、相続人間の意見がまとまらない。
結局何も決められないまま、放置状態が継続してしまうケースも後を絶ちません。
相続登記の義務化:
2024年4月から相続登記が義務化されました。
正当な理由なく登記を怠ると、過料の対象となる可能性もあります。
手続きの手間と費用もかかります。
空き家を相続する際には、この点も考慮が必要です。
空き家問題は、放置すればするほど解決が困難になります。
相続が発生したタイミングで、家族・親族間の深刻なトラブル。
いわゆる「争続」の火種となる可能性が非常に高いのです。
あなたが良かれと思って残した(あるいは、放置してしまった)空き家。
それが将来、大切な家族の間で深刻な争いを引き起こす原因になるかもしれない。
これは、何としても避けたい事態ではないでしょうか。
以上、空き家を放置することのリスクを4つの側面から詳しく見てきました。
経済的負担。
物理的危険。
地域社会への悪影響。
そして将来世代への負の遺産…。
これらのリスクは、時間が経てば経つほど、雪だるま式に膨らんでいきます。
「まだ大丈夫」と思っているうちに、手遅れになってしまうかもしれません。
だからこそ、今すぐ行動を起こすことが何よりも重要なのです。
しかし、焦りは禁物です。
良かれと思って取った行動が、かえって問題をこじらせてしまう。
そんな「失敗パターン」も存在します。
次の章では、その点について詳しく解説していきます。
放置リスク、具体的に診断します
あなたの網走の空き家は、どのリスクが高い状態でしょうか? 税金? 老朽化? それとも近隣への影響? 不安な点をLINEで教えてください。専門家の視点から、現状のリスクレベルと、今すぐ取るべき対策をアドバイスします(相談無料)。
【第二章】時間とお金の無駄遣い? 網走市の空き家対策で避けるべき3つの落とし穴
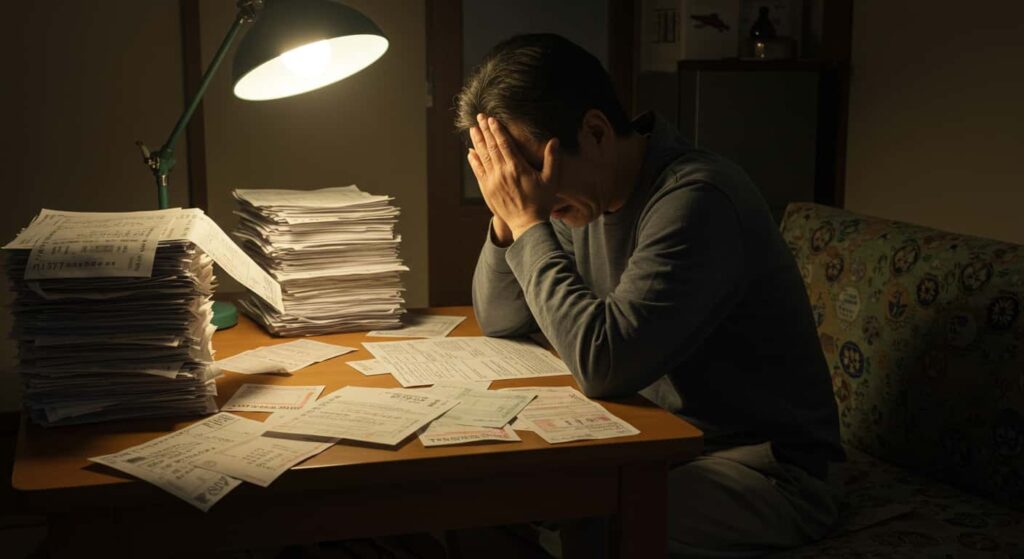
第一章では、網走市の空き家を放置すること。
その深刻なリスクについて、詳しく解説しました。
「これは大変だ、早く何とかしなければ!」
そう決意された方もいらっしゃることでしょう。
しかし、焦って行動を起こした結果。
かえって時間やお金を無駄にしてしまったり。
問題をさらに複雑にしてしまったりするケースも少なくありません。
空き家対策には、知らずに足を踏み入れると抜け出せなくなるような。
そんな「落とし穴」が存在するのです。
この章では、網走市の空き家所有者が特に陥りやすい。
代表的な3つの失敗パターンとその原因。
そして回避策について、深く掘り下げて解説していきます。
あなたの貴重な時間とお金を無駄にしないために。
ぜひ参考にしてください。
落とし穴①:「いつかやる」という名の永久放置 – 決断できないことの代償

これが、空き家問題で最も多く見られる。
そして最も根深い「落とし穴」かもしれません。
頭では「何とかしなければ」と分かっている。
放置のリスクも理解している。
しかし、様々な理由から具体的な行動に移せない。
時間だけが過ぎていく…。
結果的に、第一章で述べたリスクが現実のものとなり。
より深刻な状況に陥ってしまうのです。
なぜ行動できないのか? その心理的・物理的障壁
人が決断し、行動に移せない背景。
そこには、様々な要因が複雑に絡み合っています。
情報不足と選択肢の複雑さ:
「そもそも、空き家をどうすればいいのか、選択肢が分からない」
「売る、貸す、壊す、それぞれのメリット・デメリットがよく理解できない」
「網走市の不動産市場や、地域特有の事情が分からない(特に遠方在住の場合)」
「誰に相談すれば、信頼できる情報が得られるのか分からない」
情報が多すぎたり、逆に少なすぎたりすると混乱します。
思考停止に陥ってしまうことがあります。
手続きへの抵抗感・面倒くささ:
不動産会社とのやり取り、役所での手続き、書類の準備。
これらを考えると、「面倒だ」「難しそう」と感じてしまう。
特に、相続が絡む場合は、さらに煩雑な手続きが必要です。
日々の仕事や生活に追われ、「空き家のことまで手が回らない」という方も多いでしょう。
費用に対する不安と躊躇:
「売却するにしても、仲介手数料や税金がかかるのでは?」
「賃貸に出すには、リフォーム費用がいくらかかるか見当もつかない」
「解体費用が高額だと聞いて、とても払えそうにない」
具体的な費用が分からない、あるいは高額になると思い込んでいる。
そのため、最初の一歩を踏み出せないケースです。
感情的な要因・思い出への執着:
「生まれ育った家だから、手放すのは忍びない」
「親が大切にしていた家を、壊すなんてできない」
家に対する愛着や、家族との思い出が強い場合。
合理的な判断が難しくなることがあります。
「もう少し、このままにしておきたい」
そんな気持ちが、決断を鈍らせます。
相続人間の意見の不一致・調整の困難さ:
複数の相続人で空き家を共有している場合。
それぞれの立場や考え方の違いから、方針がまとまらないケースが非常に多いです。
「長男は売りたいが、次男は残したい」
「兄弟間で連絡を取り合うのも億劫」
「誰も主導権を握らないと話が進まない」
といった状況です。
意見調整の難しさから、結局「現状維持=放置」という選択(あるいは不作為)に陥りがちです。
「先延ばし」がもたらす致命的な結末
これらの障壁によって行動を先延ばしにしている間にも。
事態は刻一刻と悪化していきます。
- 建物の劣化は加速度的に進行:
放置期間が1年延びるごとに、修繕費用は確実に増大します。
- 市場価値は下落の一途:
築年数が古くなるほど、売却価格も賃料も下がっていきます。
- 特定空家指定のリスク増大:
管理不全が続けば、行政からの指導・勧告、そして税金増額のリスクが高まります。
- 解決の選択肢が狭まる:
最初は「賃貸」も可能だったかもしれない家が。
劣化が進みすぎて「解体」しか選択肢がなくなる、といった事態も。
- 相続時のトラブル深刻化:
問題を先送りしたまま相続が発生すると。
次世代にさらに重い負担と対立の火種を残すことになります。
「いつかやろう」は、多くの場合「永遠にやらない」と同義です。
そして、その代償は、想像以上に大きいものになる可能性があります。
【回避策】まずは「現状把握」と「相談」から
この「永久放置」の落とし穴を避けるためには。
まず現状を正確に把握し、一人で抱え込まずに相談することが重要です。
情報収集:
ネットや書籍だけでなく、網走市の公式ウェブサイト(空き家バンク、補助金など)。
地元の不動産会社のウェブサイトなど、信頼できる情報源から情報を集めましょう。
現状確認:
可能であれば実際に現地を訪れ、建物の状態を確認します。
(雨漏り、傾き、設備の状況など)
周辺環境も確認しましょう。
難しければ、写真や動画で記録したり、信頼できる人に依頼したり。
固定資産税の納税通知書なども確認し、情報を整理します。
専門家への相談:
不動産会社、建築士、司法書士、税理士。
そして私のような空き家専門のコンサルタントなど。
相談内容に応じて適切な専門家を選びましょう。
初回相談は無料で行っている専門家も多いです。
まずは気軽に連絡してみることが大切です。
相続人間の話し合い:
共有名義の場合は、まず相続人全員で話し合う場を設けることが不可欠です。
「現状」と「今後の意向」について話し合いましょう。
感情的にならず、客観的な情報(リスク、費用など)を共有します。
現実的な解決策を探る姿勢が求められます。
小さな一歩を踏み出す:
「全てを一度に解決しよう」とせず。
「まずは査定だけ依頼してみる」
「無料相談を利用してみる」
など、実行可能な小さなステップから始めてみましょう。
行動を起こすことで、次の道筋が見えてくることがあります。
重要なのは、「完璧な解決策」を最初から見つけようとしないこと。
「問題をこれ以上悪化させないために、今できることから始める」
そういう意識を持つことです。
落とし穴②:根拠なき期待が生む大赤字 – 高額リフォーム投資の罠
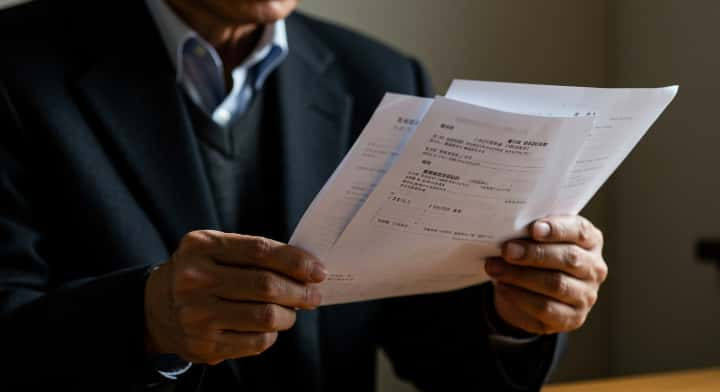
「古い家でも、お金をかけて綺麗にリフォームすれば、高く売れるはずだ!」
「おしゃれな内装にすれば、すぐに借り手が見つかって、家賃収入で儲かるだろう!」
このような期待から、高額なリフォーム費用を投じてしまうケースがあります。
数百万円、場合によっては1000万円を超えるような投資です。
しかし、その投資が、必ずしも期待通りのリターンを生むとは限りません。
むしろ、かけた費用を全く回収できず。
大きな借金だけが残ってしまうという悲劇も起こり得るのです。
なぜ高額リフォームは失敗しやすいのか?
高額なリフォーム投資が失敗に終わる主な原因。
それは、「市場ニーズとのミスマッチ」と「費用対効果の読み違い」にあります。
市場調査の不足:
リフォーム前に、網走市の賃貸・売買市場の現状を十分に調査していない。
「自分が住みたいと思う綺麗な家なら、他の人も借りたいはず」
そういう主観的な思い込みで進めてしまうケースが多いです。
実際の家賃相場や、需要のある間取り・設備などの客観的な分析が不足しています。
費用対効果の甘い見通し:
リフォーム費用と、それによる家賃収入や売却価格の上昇分。
これを冷静に比較検討できていません。
「リフォームに〇〇万円かけたから、家賃は△万円上乗せできるはず」
といった、希望的観測に基づいた計算をしてしまう。
特に地方では、リフォーム費用をそのまま価格に転嫁できるケースは稀です。
業者選定の失敗・過剰な工事:
リフォーム業者の言いなりになってしまう。
必要以上に高額な工事や、地域のニーズに合わないデザイン・設備を導入してしまう。
複数の業者から見積もりを取らず、比較検討を怠る。
悪質な業者に騙されるケースも。
想定外の追加費用:
古い家の場合、工事を始めてから隠れた問題が見つかることがよくあります。
(構造材の腐食、シロアリ被害、配管の老朽化など)
当初の見積もりを大幅に超える追加費用が発生することも。
ローン返済のプレッシャー:
リフォーム費用をローンで賄った場合。
たとえ借り手や買い手が見つからなくても、毎月の返済は待ってくれません。
収入がないまま返済だけが続き、家計を圧迫する二重苦に。
【網走市特有の注意点】寒冷地仕様とコスト
網走市で空き家をリフォームする場合。
特に注意が必要なのが「寒冷地仕様」です。
冬の厳しい寒さに対応するためには、追加の費用がかかる項目が多くなります。
- 断熱性能の向上:壁、床、天井への断熱材追加、高性能な断熱窓への交換など。
- 暖房設備の更新:効率の良い暖房器具の設置。
- 凍結防止対策:水道管へのヒーター設置や配管経路の見直し。
- 屋根・外壁の耐久性:積雪や風雪、凍害に強い素材の選定。
これらの寒冷地対策を十分に行わないと、快適に住めません。
光熱費が高額になったり、結露や凍結のリスクが高まったりします。
しかし、十分な対策を行えば、それだけリフォーム費用は嵩みます。
このコスト増を、家賃収入や売却価格で回収できるのか。
より慎重な判断が求められます。
【回避策】「最低限」と「市場目線」を徹底する
高額リフォームの罠を避けるためには。
以下の点を徹底することが重要です。
徹底的な市場調査:
リフォーム前に、網走市の賃貸・売買市場の動向を把握します。
家賃相場、売却相場、需要のある物件タイプなどを客観的に調べます。
「いくらなら借り手・買い手が見つかりそうか」という現実的なラインを見極めます。
費用対効果のシビアな計算:
想定されるリフォーム費用と、見込めるリターンを比較します。
「本当に投資に見合うか」を厳しく判断します。
回収期間、空室リスク、金利なども考慮しましょう。
「貸せる・売れる最低限」のリフォームに留める:
「自分が住みたい家」ではなく、「市場で受け入れられる最低限のレベル」を目指します。
特に賃貸の場合は、高額な設備投資は避けます。
清潔感と基本的な機能の確保を優先します。
DIY可能な状態で貸し出す、という選択肢も有効です。
信頼できる業者選びと相見積もり:
複数の業者から詳細な見積もりを取り、比較検討します。
実績や評判、担当者の対応なども考慮し、信頼できる業者を選びましょう。
契約内容は細部まで確認します。
自己資金の範囲内で行う:
可能な限り、リフォーム費用は自己資金で賄える範囲に留めます。
安易にローンに頼らないようにします。
僕、藤本の提案する「管理代行」は。
まさにこの「最低限の整備で貸し出す」という考え方に基づいています。
オーナー様の費用負担をなくし、リスクを最小限に抑えながら活用する道を探る。
それが、最も現実的で賢明な選択肢の一つだと考えています。
落とし穴③:「取らぬ狸の皮算用」に終わる補助金への過度な期待
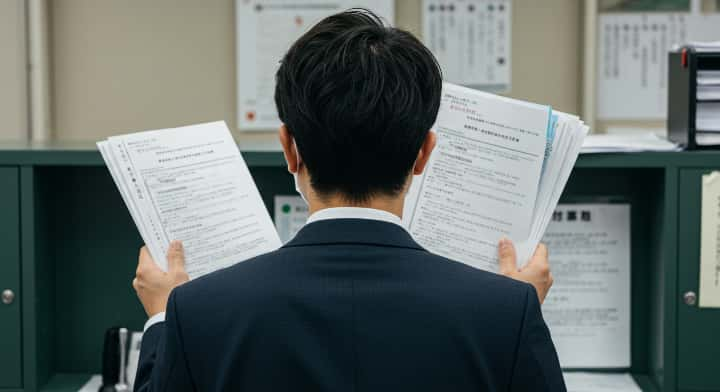
「空き家の解体やリフォームには、市から補助金が出るらしいぞ!」
「補助金を使えば、費用の大部分を賄えるんじゃないか?」
空き家対策に関する補助金制度は、確かに存在します。
国や、都道府県、そして網走市のような市町村が。
空き家問題の解決を後押しするために、様々な支援策を用意している場合があります。
しかし、この補助金を「あてにしすぎる」と。
思わぬ落とし穴にはまることがあります。
計画そのものが頓挫したり、期待外れの結果に終わったりする可能性があるのです。
補助金制度の「甘くない現実」
補助金に対して、以下のような「甘い期待」を抱いていませんか?
- 「申請すれば、誰でも簡単にもらえるものだ」
- 「費用の大部分、あるいは全額を補助してもらえる」
- 「手続きも、それほど難しくないだろう」
残念ながら、現実はそれほど甘くありません。
補助金制度には、利用する上で知っておくべき、いくつかの重要な注意点があります。
厳しい受給要件:
補助金には、非常に細かい条件が付いているのが普通です。
(対象空き家の状態、場所、築年数、耐震性、工事内容、申請者の所得、居住要件など)
これらの条件を一つでも満たさない場合は、申請すらできません。
予算と期間の壁:
補助金には予算の上限があります。
予算がなくなり次第、年度途中でも受付終了となります。
申請期間も限られています。
タイミングを逃さないようにする必要があります。
手続きの煩雑さと時間:
申請には多くの書類が必要となり、作成・収集に時間と手間がかかります。
申請から交付決定までにも、数週間から数ヶ月かかるのが一般的です。
補助額の上限と自己負担:
補助されるのは費用の一部であり、上限額も設定されています。
必ず自己負担が発生します。全額補助はまずありません。
原則「後払い」!立て替え資金が必要
多くの場合、工事完了・支払い後に補助金が振り込まれます。
つまり、工事費用は一旦全額、自己資金で立て替える必要があるのです。
制度の変更・廃止リスク:
補助金制度は、毎年度見直されるのが一般的です。
今年度あった制度が、来年度は変更・廃止される可能性もあります。
【回避策】補助金は「おまけ」と考え、依存しない計画を
補助金頼みの計画がいかに危ういか、お分かりいただけたでしょうか。
この落とし穴を避けるためには、以下の考え方が重要です。
- 補助金ありきで考えない:
まずは、補助金がなくても実現可能な計画を検討します。
- 情報収集は正確かつ最新のものを:
網走市の公式ウェブサイトや担当窓口で、最新情報を確認します。
- 利用できそうなら、早めに相談・準備:
条件に合いそうなら、早めに市の担当窓口に相談し、準備を進めます。
- 補助金は「もらえたらラッキー」程度に:
補助金は「おまけ」と捉え、受給できなくても計画が頓挫しないようにします。
補助金を過信せず、地に足の着いた計画を立てることが。
空き家対策を成功させるための鍵となります。
以上、網走市の空き家対策で陥りやすい3つの落とし穴について解説しました。
①決断できないことによる永久放置
②市場を見誤った高額リフォーム投資
③補助金への過度な期待
これらの失敗パターンを回避するためには。
正確な情報収集、現状の客観的な把握、そして現実的な計画立案が不可欠です。
そして、一人で悩まず、信頼できる専門家に相談することも、解決への近道となります。
では、これらのリスクや失敗パターンを踏まえた上で。
具体的にどのような解決策が考えられるのでしょうか?
次の章では、一般的な空き家問題の解決策である「売却」「賃貸」「解体」について。
それぞれのメリット・デメリット、そして網走市における注意点を、さらに詳しく比較検討していきます。
失敗しない空き家対策、専門家と一緒に考えませんか?
「落とし穴」を避け、着実に問題を解決したいですよね。あなたの網走の空き家の状況に合わせて、最適な解決策を一緒に考えます。失敗談から学び、成功への道を歩みましょう。LINE相談は無料です。
【第二章】時間とお金の無駄遣い? 網走市の空き家対策で避けるべき3つの落とし穴
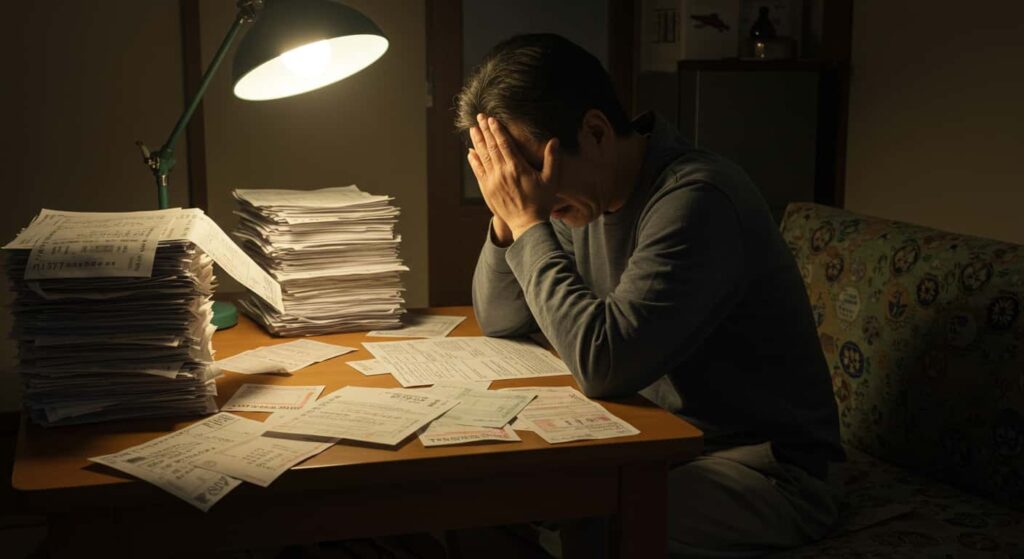
第一章では、網走市の空き家を放置すること。
その深刻なリスクについて、詳しく解説しました。
「これは大変だ、早く何とかしなければ!」
そう決意された方もいらっしゃることでしょう。
しかし、焦って行動を起こした結果。
かえって時間やお金を無駄にしてしまったり。
問題をさらに複雑にしてしまったりするケースも少なくありません。
空き家対策には、知らずに足を踏み入れると抜け出せなくなるような。
そんな「落とし穴」が存在するのです。
この章では、網走市の空き家所有者が特に陥りやすい。
代表的な3つの失敗パターンとその原因。
そして回避策について、深く掘り下げて解説していきます。
あなたの貴重な時間とお金を無駄にしないために。
ぜひ参考にしてください。
落とし穴①:「いつかやる」という名の永久放置 – 決断できないことの代償

これが、空き家問題で最も多く見られる。
そして最も根深い「落とし穴」かもしれません。
頭では「何とかしなければ」と分かっている。
放置のリスクも理解している。
しかし、様々な理由から具体的な行動に移せない。
時間だけが過ぎていく…。
結果的に、第一章で述べたリスクが現実のものとなり。
より深刻な状況に陥ってしまうのです。
なぜ行動できないのか? その心理的・物理的障壁
人が決断し、行動に移せない背景。
そこには、様々な要因が複雑に絡み合っています。
情報不足と選択肢の複雑さ:
「そもそも、空き家をどうすればいいのか、選択肢が分からない」
「売る、貸す、壊す、それぞれのメリット・デメリットがよく理解できない」
「網走市の不動産市場や、地域特有の事情が分からない(特に遠方在住の場合)」
「誰に相談すれば、信頼できる情報が得られるのか分からない」
情報が多すぎたり、逆に少なすぎたりすると混乱します。
思考停止に陥ってしまうことがあります。
手続きへの抵抗感・面倒くささ:
不動産会社とのやり取り、役所での手続き、書類の準備。
これらを考えると、「面倒だ」「難しそう」と感じてしまう。
特に、相続が絡む場合は、さらに煩雑な手続きが必要です。
日々の仕事や生活に追われ、「空き家のことまで手が回らない」という方も多いでしょう。
費用に対する不安と躊躇:
「売却するにしても、仲介手数料や税金がかかるのでは?」
「賃貸に出すには、リフォーム費用がいくらかかるか見当もつかない」
「解体費用が高額だと聞いて、とても払えそうにない」
具体的な費用が分からない、あるいは高額になると思い込んでいる。
そのため、最初の一歩を踏み出せないケースです。
感情的な要因・思い出への執着:
「生まれ育った家だから、手放すのは忍びない」
「親が大切にしていた家を、壊すなんてできない」
家に対する愛着や、家族との思い出が強い場合。
合理的な判断が難しくなることがあります。
「もう少し、このままにしておきたい」
そんな気持ちが、決断を鈍らせます。
相続人間の意見の不一致・調整の困難さ:
複数の相続人で空き家を共有している場合。
それぞれの立場や考え方の違いから、方針がまとまらないケースが非常に多いです。
「長男は売りたいが、次男は残したい」
「兄弟間で連絡を取り合うのも億劫」
「誰も主導権を握らないと話が進まない」
といった状況です。
意見調整の難しさから、結局「現状維持=放置」という選択(あるいは不作為)に陥りがちです。
「先延ばし」がもたらす致命的な結末
これらの障壁によって行動を先延ばしにしている間にも。
事態は刻一刻と悪化していきます。
- 建物の劣化は加速度的に進行:
放置期間が1年延びるごとに、修繕費用は確実に増大します。
- 市場価値は下落の一途:
築年数が古くなるほど、売却価格も賃料も下がっていきます。
- 特定空家指定のリスク増大:
管理不全が続けば、行政からの指導・勧告、そして税金増額のリスクが高まります。
- 解決の選択肢が狭まる:
最初は「賃貸」も可能だったかもしれない家が。
劣化が進みすぎて「解体」しか選択肢がなくなる、といった事態も。
- 相続時のトラブル深刻化:
問題を先送りしたまま相続が発生すると。
次世代にさらに重い負担と対立の火種を残すことになります。
「いつかやろう」は、多くの場合「永遠にやらない」と同義です。
そして、その代償は、想像以上に大きいものになる可能性があります。
【回避策】まずは「現状把握」と「相談」から
この「永久放置」の落とし穴を避けるためには。
まず現状を正確に把握し、一人で抱え込まずに相談することが重要です。
情報収集:
ネットや書籍だけでなく、網走市の公式ウェブサイト(空き家バンク、補助金など)。
地元の不動産会社のウェブサイトなど、信頼できる情報源から情報を集めましょう。
現状確認:
可能であれば実際に現地を訪れ、建物の状態を確認します。
(雨漏り、傾き、設備の状況など)
周辺環境も確認しましょう。
難しければ、写真や動画で記録したり、信頼できる人に依頼したり。
固定資産税の納税通知書なども確認し、情報を整理します。
専門家への相談:
不動産会社、建築士、司法書士、税理士。
そして私のような空き家専門のコンサルタントなど。
相談内容に応じて適切な専門家を選びましょう。
初回相談は無料で行っている専門家も多いです。
まずは気軽に連絡してみることが大切です。
相続人間の話し合い:
共有名義の場合は、まず相続人全員で話し合う場を設けることが不可欠です。
「現状」と「今後の意向」について話し合いましょう。
感情的にならず、客観的な情報(リスク、費用など)を共有します。
現実的な解決策を探る姿勢が求められます。
小さな一歩を踏み出す:
「全てを一度に解決しよう」とせず。
「まずは査定だけ依頼してみる」
「無料相談を利用してみる」
など、実行可能な小さなステップから始めてみましょう。
行動を起こすことで、次の道筋が見えてくることがあります。
重要なのは、「完璧な解決策」を最初から見つけようとしないこと。
「問題をこれ以上悪化させないために、今できることから始める」
そういう意識を持つことです。
落とし穴②:根拠なき期待が生む大赤字 – 高額リフォーム投資の罠
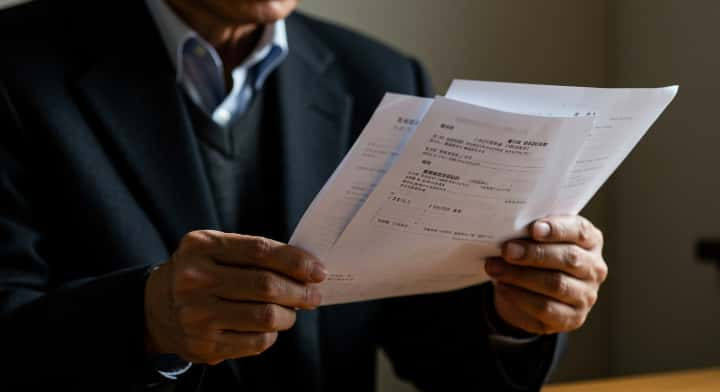
「古い家でも、お金をかけて綺麗にリフォームすれば、高く売れるはずだ!」
「おしゃれな内装にすれば、すぐに借り手が見つかって、家賃収入で儲かるだろう!」
このような期待から、高額なリフォーム費用を投じてしまうケースがあります。
数百万円、場合によっては1000万円を超えるような投資です。
しかし、その投資が、必ずしも期待通りのリターンを生むとは限りません。
むしろ、かけた費用を全く回収できず。
大きな借金だけが残ってしまうという悲劇も起こり得るのです。
なぜ高額リフォームは失敗しやすいのか?
高額なリフォーム投資が失敗に終わる主な原因。
それは、「市場ニーズとのミスマッチ」と「費用対効果の読み違い」にあります。
市場調査の不足:
リフォーム前に、網走市の賃貸・売買市場の現状を十分に調査していない。
「自分が住みたいと思う綺麗な家なら、他の人も借りたいはず」
そういう主観的な思い込みで進めてしまうケースが多いです。
実際の家賃相場や、需要のある間取り・設備などの客観的な分析が不足しています。
費用対効果の甘い見通し:
リフォーム費用と、それによる家賃収入や売却価格の上昇分。
これを冷静に比較検討できていません。
「リフォームに〇〇万円かけたから、家賃は△万円上乗せできるはず」
といった、希望的観測に基づいた計算をしてしまう。
特に地方では、リフォーム費用をそのまま価格に転嫁できるケースは稀です。
業者選定の失敗・過剰な工事:
リフォーム業者の言いなりになってしまう。
必要以上に高額な工事や、地域のニーズに合わないデザイン・設備を導入してしまう。
複数の業者から見積もりを取らず、比較検討を怠る。
悪質な業者に騙されるケースも。
想定外の追加費用:
古い家の場合、工事を始めてから隠れた問題が見つかることがよくあります。
(構造材の腐食、シロアリ被害、配管の老朽化など)
当初の見積もりを大幅に超える追加費用が発生することも。
ローン返済のプレッシャー:
リフォーム費用をローンで賄った場合。
たとえ借り手や買い手が見つからなくても、毎月の返済は待ってくれません。
収入がないまま返済だけが続き、家計を圧迫する二重苦に。
【網走市特有の注意点】寒冷地仕様とコスト
網走市で空き家をリフォームする場合。
特に注意が必要なのが「寒冷地仕様」です。
冬の厳しい寒さに対応するためには、追加の費用がかかる項目が多くなります。
- 断熱性能の向上:壁、床、天井への断熱材追加、高性能な断熱窓への交換など。
- 暖房設備の更新:効率の良い暖房器具の設置。
- 凍結防止対策:水道管へのヒーター設置や配管経路の見直し。
- 屋根・外壁の耐久性:積雪や風雪、凍害に強い素材の選定。
これらの寒冷地対策を十分に行わないと、快適に住めません。
光熱費が高額になったり、結露や凍結のリスクが高まったりします。
しかし、十分な対策を行えば、それだけリフォーム費用は嵩みます。
このコスト増を、家賃収入や売却価格で回収できるのか。
より慎重な判断が求められます。
【回避策】「最低限」と「市場目線」を徹底する
高額リフォームの罠を避けるためには。
以下の点を徹底することが重要です。
徹底的な市場調査:
リフォーム前に、網走市の賃貸・売買市場の動向を把握します。
家賃相場、売却相場、需要のある物件タイプなどを客観的に調べます。
「いくらなら借り手・買い手が見つかりそうか」という現実的なラインを見極めます。
費用対効果のシビアな計算:
想定されるリフォーム費用と、見込めるリターンを比較します。
「本当に投資に見合うか」を厳しく判断します。
回収期間、空室リスク、金利なども考慮しましょう。
「貸せる・売れる最低限」のリフォームに留める:
「自分が住みたい家」ではなく、「市場で受け入れられる最低限のレベル」を目指します。
特に賃貸の場合は、高額な設備投資は避けます。
清潔感と基本的な機能の確保を優先します。
DIY可能な状態で貸し出す、という選択肢も有効です。
信頼できる業者選びと相見積もり:
複数の業者から詳細な見積もりを取り、比較検討します。
実績や評判、担当者の対応なども考慮し、信頼できる業者を選びましょう。
契約内容は細部まで確認します。
自己資金の範囲内で行う:
可能な限り、リフォーム費用は自己資金で賄える範囲に留めます。
安易にローンに頼らないようにします。
僕、藤本の提案する「管理代行」は。
まさにこの「最低限の整備で貸し出す」という考え方に基づいています。
オーナー様の費用負担をなくし、リスクを最小限に抑えながら活用する道を探る。
それが、最も現実的で賢明な選択肢の一つだと考えています。
落とし穴③:「取らぬ狸の皮算用」に終わる補助金への過度な期待
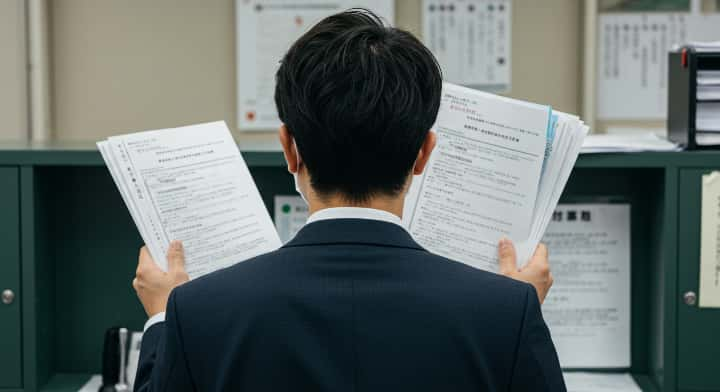
「空き家の解体やリフォームには、市から補助金が出るらしいぞ!」
「補助金を使えば、費用の大部分を賄えるんじゃないか?」
空き家対策に関する補助金制度は、確かに存在します。
国や、都道府県、そして網走市のような市町村が。
空き家問題の解決を後押しするために、様々な支援策を用意している場合があります。
しかし、この補助金を「あてにしすぎる」と。
思わぬ落とし穴にはまることがあります。
計画そのものが頓挫したり、期待外れの結果に終わったりする可能性があるのです。
補助金制度の「甘くない現実」
補助金に対して、以下のような「甘い期待」を抱いていませんか?
- 「申請すれば、誰でも簡単にもらえるものだ」
- 「費用の大部分、あるいは全額を補助してもらえる」
- 「手続きも、それほど難しくないだろう」
残念ながら、現実はそれほど甘くありません。
補助金制度には、利用する上で知っておくべき、いくつかの重要な注意点があります。
厳しい受給要件:
補助金には、非常に細かい条件が付いているのが普通です。
(対象空き家の状態、場所、築年数、耐震性、工事内容、申請者の所得、居住要件など)
これらの条件を一つでも満たさない場合は、申請すらできません。
予算と期間の壁:
補助金には予算の上限があります。
予算がなくなり次第、年度途中でも受付終了となります。
申請期間も限られています。
タイミングを逃さないようにする必要があります。
手続きの煩雑さと時間:
申請には多くの書類が必要となり、作成・収集に時間と手間がかかります。
申請から交付決定までにも、数週間から数ヶ月かかるのが一般的です。
補助額の上限と自己負担:
補助されるのは費用の一部であり、上限額も設定されています。
必ず自己負担が発生します。全額補助はまずありません。
原則「後払い」!立て替え資金が必要
多くの場合、工事完了・支払い後に補助金が振り込まれます。
つまり、工事費用は一旦全額、自己資金で立て替える必要があるのです。
制度の変更・廃止リスク:
補助金制度は、毎年度見直されるのが一般的です。
今年度あった制度が、来年度は変更・廃止される可能性もあります。
【回避策】補助金は「おまけ」と考え、依存しない計画を
補助金頼みの計画がいかに危ういか、お分かりいただけたでしょうか。
この落とし穴を避けるためには、以下の考え方が重要です。
- 補助金ありきで考えない:
まずは、補助金がなくても実現可能な計画を検討します。
- 情報収集は正確かつ最新のものを:
網走市の公式ウェブサイトや担当窓口で、最新情報を確認します。
- 利用できそうなら、早めに相談・準備:
条件に合いそうなら、早めに市の担当窓口に相談し、準備を進めます。
- 補助金は「もらえたらラッキー」程度に:
補助金は「おまけ」と捉え、受給できなくても計画が頓挫しないようにします。
補助金を過信せず、地に足の着いた計画を立てることが。
空き家対策を成功させるための鍵となります。
以上、網走市の空き家対策で陥りやすい3つの落とし穴について解説しました。
①決断できないことによる永久放置
②市場を見誤った高額リフォーム投資
③補助金への過度な期待
これらの失敗パターンを回避するためには。
正確な情報収集、現状の客観的な把握、そして現実的な計画立案が不可欠です。
そして、一人で悩まず、信頼できる専門家に相談することも、解決への近道となります。
では、これらのリスクや失敗パターンを踏まえた上で。
具体的にどのような解決策が考えられるのでしょうか?
次の章では、一般的な空き家問題の解決策である「売却」「賃貸」「解体」について。
それぞれのメリット・デメリット、そして網走市における注意点を、さらに詳しく比較検討していきます。
失敗しない空き家対策、専門家と一緒に考えませんか?
「落とし穴」を避け、着実に問題を解決したいですよね。あなたの網走の空き家の状況に合わせて、最適な解決策を一緒に考えます。失敗談から学び、成功への道を歩みましょう。LINE相談は無料です。
【第三章】あなたの網走の空き家、どうする? 売却・賃貸・解体 完全比較ガイド
第一章で空き家放置のリスクを。
第二章で対策における失敗パターンを学びました。
いよいよ、あなたの網走市にある空き家を。
具体的にどのように扱っていくべきか。
その選択肢を深く検討していく段階です。
空き家問題の解決策として一般的に考えられるのは。
大きく分けて以下の3つです。
- 【売却】:不動産として手放し、現金化する。
- 【賃貸】:誰かに貸し出し、家賃収入を得る。
- 【解体】:建物を取り壊し、更地にする。
この章では、これら3つの選択肢について。
それぞれの具体的なプロセス、メリット・デメリット、費用。
そして網走市という地域特性を踏まえた上での注意点などを。
徹底的に比較・解説していきます。
ご自身の状況や希望と照らし合わせながら。
どの選択肢が最も適しているか、じっくりと考えてみてください。
3-1. 選択肢①:【売却】 – 負担からの解放と現金化

空き家問題から最も早く、そして根本的に解放される方法。
として、まず思い浮かぶのが「売却」でしょう。
所有権を手放すことで。
固定資産税の支払い義務、管理の手間。
将来的なリスクなど、あらゆる負担から解放されます。
さらに、売却代金としてまとまった現金が手に入る可能性もあります。
売却の具体的なプロセス(仲介の場合)
一般的な不動産仲介による売却プロセス。
その流れを見ていきましょう。
不動産会社選びと査定依頼:
網走市内や近隣地域に詳しい不動産会社を複数ピックアップします。
(できれば3社程度)
各社に連絡を取り、空き家の査定(いくらで売れそうか)を依頼します。
査定は無料の場合がほとんどです。
査定価格だけでなく、根拠、販売戦略、担当者の対応なども比較し、信頼できる会社を選びます。
媒介契約の締結:
売却を依頼する会社を決めたら、「媒介契約」を結びます。
契約には3種類(専属専任、専任、一般)あります。
特徴が異なるので、担当者とよく相談して選びましょう。
販売価格の決定:
査定価格や市場相場、自分の希望額などを考慮して、売り出し価格を決めます。
高すぎても安すぎても良くないので、慎重な判断が必要です。
販売活動の開始:
不動産会社が広告などを利用して、買い手を探します。
(ウェブサイト、ポータルサイト、チラシなど)
購入希望者からの内覧(物件見学)に対応します。
購入申し込みと条件交渉:
購入希望者が見つかると、「購入申込書」が提出されます。
価格や引き渡し日などの条件を交渉します。
売買契約の締結:
条件が合意に至れば、正式な「売買契約」を結びます。
買主から手付金を受け取ります。
契約書の内容を十分に確認し、署名・捺印します。
決済と引き渡し:
決済日に、買主から残代金を受け取ります。
同時に、司法書士が所有権移転登記の手続きを行います。
鍵を買主に渡し、物件を引き渡して完了です。
(※不動産買取の場合は、よりシンプルな流れで、期間も短くなります。)
売却にかかる費用と税金
売却によって現金が手に入る一方で。
様々な費用や税金も発生します。
仲介手数料(仲介の場合):
不動産会社に支払う成功報酬です。
売買契約が成立した場合にのみ発生します。
法律で上限額が決まっています。
(売買価格400万円超の場合:(売買価格 × 3% + 6万円) + 消費税)
印紙税:
売買契約書に貼付する収入印紙代です。
契約金額に応じて税額が決まります。
登記費用(司法書士報酬含む):
抵当権抹消登記や住所変更登記などが必要な場合、費用がかかります。
司法書士への報酬も必要です。
譲渡所得税・住民税:
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合に課税されます。
譲渡所得 = 売却価格 – (取得費 + 譲渡費用)
税率は所有期間によって異なります(5年超は約20%、5年以下は約39%)。
ただし、様々な控除や特例制度があります。
特に「相続空き家の3000万円特別控除」が使えるかどうかが重要です。
(適用には細かい要件あり)
税金については、税務署や税理士に相談するのが確実です。
その他の費用:
必要に応じて、測量費用、建物解体費用(更地渡しの場合)、ハウスクリーニング費用、残置物撤去費用などがかかることがあります。
売却のメリット
経済的・精神的負担からの完全解放:
固定資産税、管理の手間、老朽化リスク、近隣トラブルの心配など。
あらゆる負担から解放されます。これが最大のメリットです。
現金化による資金確保:
売却代金を得て、他の目的に資金を活用できます。
相続問題の簡略化:
将来の相続で「負動産」を遺す心配がなくなります。
現金なら分割も容易です。
問題の早期解決(買取の場合):
買取業者なら、短期間で確実に問題を解決できます。
売却のデメリットと注意点
希望価格で売れるとは限らない:
特に地方の古い空き家は、市場価値が低い可能性があります。
期待した価格で売れない、買い手が見つからないことも。
網走市の需要動向によっては、長期間売れ残るリスクも覚悟が必要です。
売却までに時間がかかる(仲介の場合):
買い手が見つかるまで、数ヶ月から1年以上かかることも。
その間も維持費はかかり続けます。
諸費用・税金がかかる:
仲介手数料や税金など、様々な費用が発生します。
手取り額は売却価格より少なくなります。
家を手放す寂しさ:
思い出の詰まった家を手放すことに、感情的な抵抗を感じる方もいるでしょう。
契約不適合責任のリスク(仲介の場合):
売却後、隠れた欠陥が見つかった場合、責任を問われる可能性があります。
(雨漏り、シロアリ被害、給排水管の故障など)
修繕費請求や契約解除、損害賠償に繋がることも。
事前に建物状況調査(インスペクション)を行うことも有効です。
買取価格は安くなる(買取の場合):
早期現金化や手間削減のメリットはありますが。
買取価格は市場価格より低くなるのが一般的です。
【網走市での売却】考慮すべき地域特性
網走市で空き家を売却する場合。
以下の点を考慮する必要があるでしょう。
人口動態と需要:
網走市も人口減少・高齢化の傾向にあります。
住宅需要全体が活発とは言えない可能性があります。
どのような層が買い手となり得るかを見極める必要があります。
(地元住民、移住者、セカンドハウス需要など)
立地条件の重要性:
市内中心部、駅周辺、商業施設や学校に近いエリア。
これらは比較的需要が見込めるかもしれません。
しかし、郊外や交通の便が悪い場所などは、売却が困難になる可能性があります。
建物の状態と築年数:
築年数が古い木造家屋が多いでしょう。
耐震性や断熱性に問題を抱えているケースも少なくないはずです。
大幅なリフォームが必要な物件は、敬遠されがちです。
冬場の状況:
冬期間は積雪のため内覧が難しくなったり。
買い手の動きが鈍くなったりする可能性があります。
売却活動のタイミングも考慮が必要です。
地元の不動産会社の情報力:
地域に根ざした不動産会社は、地元の需要動向や買い手候補の情報を持っている可能性があります。
複数の会社に相談し、信頼できるパートナーを見つけることが重要です。
売却は、うまくいけば問題を一掃できる有効な手段です。
しかし、特に網走市のような地方都市の古い空き家の場合。
期待通りに進まない可能性も十分にあります。
「売れるはず」と安易に考えず。
まずは現実的な市場価値を把握しましょう。
売却にかかる費用やリスクを理解した上で。
慎重に判断することが求められます。
3-2. 選択肢②:【賃貸】 – 収益化と資産維持の両立

「家を手放すのはもったいない」
「愛着があるから、できれば残したい」
「将来、自分や家族が使う可能性もゼロではない」
このように考えている場合。
「賃貸」に出して誰かに活用してもらう、という選択肢があります。
家賃収入を得ることで。
固定資産税などの維持費を賄えるだけでなく。
プラスの収益(インカムゲイン)を生み出す可能性があります。
また、人が住むことで家の換気や管理が行われます。
老朽化の進行を遅らせる効果も期待できます。
賃貸の具体的なプロセス
空き家を賃貸に出す場合。
一般的には以下のようなステップを踏みます。
賃貸可能かどうかの判断と準備:
まず、その空き家が賃貸物件として貸し出せる状態かを確認します。
建物の安全性、設備の状況、法的な問題などをチェックします。
必要に応じて、リフォームや修繕、ハウスクリーニング、残置物の撤去を行います。
どの程度手を入れるかは、ターゲット層や家賃設定によります。
網走市での賃貸需要や家賃相場を調査し、現実的な家賃を設定します。
入居者募集(不動産会社への依頼):
地元の不動産会社に依頼し、入居者を募集してもらうのが一般的です。
(賃貸仲介)
募集広告の作成、内覧対応、入居審査などを行います。
入居者が決まれば、仲介手数料を支払います。
(家賃の1ヶ月分+消費税が上限)
賃貸借契約の締結:
入居希望者が見つかり、審査をクリアすれば、「賃貸借契約」を結びます。
契約書には、家賃、敷金、礼金、契約期間、修繕義務などを明記します。
借地借家法に基づいた、法的に有効な契約書を作成することが重要です。
物件の引き渡しと管理業務:
契約開始日までに、物件を入居可能な状態にして鍵を引き渡します。
入居後は、家賃の集金、滞納時の督促、クレーム対応、退去時の立ち会い、原状回復費用の精算など、様々な管理業務が発生します。
管理委託(オプション):
これらの管理業務を自分で行うのが難しい場合。
(特に遠方在住の場合)
不動産管理会社に委託することができます。
管理委託手数料(家賃の5%程度が相場)がかかりますが、煩雑な業務から解放されます。
賃貸にかかる費用と税金
賃貸経営には、家賃収入というリターンがある一方で。
様々なコストもかかります。
初期費用:
リフォーム・修繕費用。
(網走の寒冷地仕様を考えると高額になる可能性も)
ハウスクリーニング費用。
残置物撤去費用。
設備交換費用(給湯器、暖房器具など)。
火災保険料。
仲介手数料(最初の入居者決定時)。
運営費用(ランニングコスト):
固定資産税・都市計画税。
管理委託手数料(委託する場合)。
修繕費(経年劣化による設備の故障など)。
共有部分の維持費(アパート等)。
空室時のローン返済(ローン利用の場合)。
税金(不動産所得):
家賃収入から必要経費を差し引いた「不動産所得」に対して、所得税・住民税が課税されます。
確定申告が必要です。
賃貸のメリット
継続的な収入(インカムゲイン):
空室期間がなければ、毎月安定した家賃収入を得られます。
維持費を賄い、プラスの収益となる可能性があります。
資産の維持・活用:
家を手放すことなく、資産として維持し続けられます。
将来的に自分や家族が利用する可能性を残せます。
老朽化の抑制:
人が住むことで、家の換気や清掃が行われ、劣化のスピードを遅らせる効果が期待できます。
節税効果(場合による):
不動産所得が赤字になった場合、他の所得と損益通算できる可能性があります。
減価償却費を経費計上できるメリットもあります。
賃貸のデメリットと注意点
初期投資(リフォーム費用)が高額になる可能性:
貸し出せる状態にするために、まとまった費用が必要になることが多いです。
空室リスク:
常に入居者がいるとは限りません。
空室期間中は収入ゼロですが、支出は続きます。
網走市の賃貸需要が低い場合、長期空室のリスクも。
家賃滞納リスク:
入居者が家賃を支払ってくれないリスクがあります。
督促や法的手続きが必要になることも。
入居者トラブルのリスク:
騒音、ゴミ出し、近隣トラブルなど、入居者が問題を起こす可能性があります。
修繕費用の発生:
経年劣化による設備の故障や建物の修繕は、基本的に大家負担です。
突然の出費に備える必要があります。
管理の手間:
自主管理する場合、多くの手間と時間がかかります。
遠方在住の場合は現実的に困難でしょう。
管理委託費用:
管理会社に委託すれば手間は省けますが、手数料がかかります。
貸したら自由に使えない:
契約期間中は、自分や家族が使いたくても、自由には使えません。
借地借家法による借主保護:
正当な理由がない限り、大家側から一方的に契約解除や更新拒絶はできません。
【網走市での賃貸】考慮すべき地域特性
網走市で空き家を賃貸に出す場合。
売却と同様に地域特性を考慮する必要があります。
賃貸需要のターゲット:
どのような層からの需要が見込めるか。
(単身者、ファミリー、学生、高齢者、季節労働者、移住者など)
東京農大関連の学生需要、医療・福祉関係者、公務員などの転勤者需要はある程度見込めるかもしれません。
家賃相場:
網走市の家賃相場は、都市部に比べて低いと考えられます。
リフォーム費用に見合う家賃設定が難しい可能性があります。
競合物件:
市内のアパートや他の戸建て賃貸との競争になります。
築年数、立地、設備、家賃などで差別化が必要です。
季節変動:
観光シーズンや漁業・農業の繁忙期など。
季節によって短期的な賃貸需要がある可能性も。
(安定性は低いかもしれません)
寒冷地対策の必須性:
冬場の暖かさ、断熱性能、除雪のしやすさ。
これらは網走で物件を選ぶ上で非常に重要です。
対策が不十分な物件は敬遠される可能性が高いです。
信頼できる管理会社の存在:
遠方から賃貸経営を行う場合。
地元の事情に詳しく、信頼できる管理会社を見つけられるかが成功の鍵です。
賃貸は、うまくいけば継続的な収入源となり、資産を維持できる魅力的な選択肢です。
しかし、初期投資、空室リスク、管理の手間など。
乗り越えるべきハードルも少なくありません。
特に、網走市で賃貸経営を行うには。
地域の需要を正確に読み、費用対効果を慎重に見極め、適切な管理体制を築くことが不可欠です。
安易な期待だけで始めると、「負動産」を抱えたまま、さらなる負担を背負い込むことになりかねません。
3-3. 選択肢③:【解体】 – リスク除去と土地活用への道

「もう家が古すぎて、売ることも貸すこともできそうにない」
「倒壊の危険があって、近所にも迷惑をかけているから、とにかく早く建物をなくしたい」
「相続したけど、誰も使う予定がないし、土地だけにしてスッキリさせたい」
様々な理由から、最終的な選択肢として考えられるのが。
建物を「解体」して更地(さらち:建物がない状態の土地)にすることです。
物理的に建物をなくすことで。
第一章で述べたような建物のリスクを根本的に解消できます。
(老朽化、倒壊、特定空家指定、損害賠償責任、景観・治安悪化など)
また、更地にすることで。
土地としての活用(売却、駐車場など)の選択肢が広がる可能性もあります。
解体の具体的なプロセス
建物の解体工事は、専門的な知識と技術、そして法的な手続きが必要です。
信頼できる解体業者に依頼するのが一般的です。
大まかな流れは以下のようになります。
解体業者選びと見積もり依頼:
網走市内や周辺地域で実績のある解体業者を複数探します。
(できれば3社以上)
各社に現地調査を依頼し、詳細な見積もりを取ります。
見積内容(解体範囲、アスベスト調査、廃棄物処分費、整地費用など)をしっかり確認しましょう。
金額だけでなく、工事内容、工期、実績、保険加入状況なども比較し、信頼できる業者を選びます。
安さだけで選ぶと、後でトラブルになる可能性があるので注意が必要です。
契約の締結:
依頼する業者が決まったら、工事請負契約を結びます。
契約書の内容(工事内容、金額、工期、支払い条件など)を十分に確認します。
各種届出:
一定規模以上の解体では、建設リサイクル法に基づく届出が必要です。
アスベスト除去作業がある場合は、関連法規に基づく届出も必要です。
(通常は業者が代行してくれます)
近隣への挨拶:
工事前には、解体業者と一緒に近隣住民へ挨拶回りを行います。
工事期間や内容、騒音・振動・粉塵などへの配慮について説明し、理解と協力を求めます。
これはトラブル防止に繋がります。
ライフラインの停止・撤去:
電気、ガス、水道などを停止し、必要に応じてメーターや引き込み線を撤去依頼します。
(業者がサポートしてくれることが多いです)
(必要な場合)アスベスト調査・除去:
事前にアスベスト含有調査が必要な場合があります。
含まれている場合は、法令に基づいた適切な除去作業が必要となり、別途費用がかかります。
古い建物ほど注意が必要です。
解体工事の実施:
足場・養生シートを設置し、騒音や粉塵の飛散を防ぎます。
内装材・建具を撤去し、重機で建物本体を解体します。
水を撒きながら作業し、粉塵を抑えます。
地中の基礎部分も掘り起こし、撤去します。
最後に地面を平らにならします(整地)。
廃棄物の分別・搬出・処分:
発生した廃棄物を法律に従って分別し、適正に搬出・処分します。
不法投棄は絶対に許されません。
マニフェスト(産業廃棄物管理票)で適正処理を確認します。
工事完了確認と支払い:
工事が完了したら、契約通りか確認し、問題なければ代金を支払います。
建物滅失登記の申請:
建物を取り壊したら、1ヶ月以内に法務局へ「建物滅失登記」を申請する義務があります。
怠ると過料に処せられる可能性があります。
通常は土地家屋調査士に依頼します。
解体にかかる費用
解体費用は、様々な要因によって大きく変動します。
一般的な目安としては、木造住宅の場合、坪単価で3万円~5万円程度と言われることがあります。
(あくまで目安であり、保証するものではありません)
例えば、延床面積30坪の木造家屋なら、90万円~150万円程度が目安です。
ただし、以下の要因によって費用は大きく変わります。
- 建物の構造:木造 < 鉄骨造 < RC造 の順に高くなります。
- 建物の大きさ:大きいほど高くなります。
- 立地条件:重機が入りにくい、隣家が近いなどは費用増の要因に。
- 付帯工事の有無:塀、門、物置、庭木などの撤去は追加費用。
- アスベスト含有の有無:調査・除去費用が別途必要。
- 地中埋設物の有無:予期せぬ埋設物が見つかると追加費用。
- 廃棄物の種類と量:処分費用が変わります。残置物処分も別途。
- 解体業者の違い:業者によって見積金額に差が出ます。
- 時期:繁忙期や、網走の場合は冬期(積雪時)は割高になる可能性。
正確な費用を知るためには。
必ず複数の信頼できる業者に現地調査をしてもらい、詳細な見積もりを取ることが不可欠です。
解体のメリット
建物に関するリスクの完全除去:
老朽化、倒壊、特定空家指定、損害賠償責任など。
建物が存在することによるあらゆるリスクを根本的に解消できます。
これが最大のメリットです。
管理の手間からの解放:
建物の維持管理、見回り、修繕、火災保険などが一切不要になります。
土地活用の選択肢が広がる(可能性):
更地になることで、土地としての売却がしやすくなったり。
駐車場など、新たな活用を検討できるようになったりします。
(ただし、活用できるかは土地の条件や地域の需要次第です)
精神的な解放:
長年の悩みの種だった空き家問題が物理的になくなることで。
精神的な負担から解放され、スッキリすることができます。
解体のデメリットと注意点
高額な解体費用:
最も大きなデメリットは、やはり費用負担です。
木造でも100万円以上かかることが多く、条件によっては数百万円に。
この費用を捻出できるかが最大のハードルです。
固定資産税の増額:
建物がなくなると、「住宅用地の特例措置」が適用されなくなります。
土地にかかる固定資産税が最大6倍、都市計画税が最大3倍になる可能性が高いです。
更地のままにしておくと、税負担が以前より重くなるケースがほとんどです。
更地活用の難しさ:
解体して更地にしても、その土地がすぐに活用できるとは限りません。
特に地方では土地需要が低く、買い手が見つからないことも。
駐車場にしても利用者がいないかもしれません。
網走市でも、立地によっては更地のまま長期間放置されるリスクがあります。
資産価値の消滅(建物部分):
当然ながら、建物としての資産価値は完全に失われます。
「まだ活用できたかもしれない」という可能性も消滅します。
工事に伴う近隣への影響:
解体工事中は騒音、振動、粉塵などが発生します。
近隣住民に一時的な迷惑をかけることになります。
十分な説明と配慮が必要です。
思い出の喪失:
家に対する愛着や思い出がある場合。
それらが物理的に消滅してしまうことに、大きな喪失感を伴うことがあります。
【網走市での解体】考慮すべき地域特性
網走市で空き家の解体を検討する場合。
以下の点も考慮に入れると良いでしょう。
冬期間の工事:
積雪が多い冬期間(例:12月~3月頃)は。
工事が困難になるか、費用が割高になる可能性があります。
工事のタイミングは業者とよく相談が必要です。
解体業者・廃棄物処理業者の状況:
網走市内や近隣地域に、信頼できる業者がどれくらい存在するか。
選択肢が限られる場合、費用が高止まりする可能性も。
解体後の更地の需要:
網走市内で、更地に対する需要がどれくらいあるか。
中心市街地ならまだしも、郊外では活用が難しいかもしれません。
隣接地への売却、家庭菜園なども考えられますが、収益性は低いでしょう。
補助金の活用:
網走市に、危険な空き家の解体費用に対する補助金制度があるか確認しましょう。
(第二章参照)
もし利用できれば、費用負担を軽減できます。
ただし、条件や予算、期間などをよく確認する必要があります。
解体は、建物のリスクを一掃できる最終手段です。
しかし、高額な費用と、その後の固定資産税増額。
そして更地活用の難しさという大きな課題が伴います。
「壊してしまえば終わり」と安易に考えるのではなく。
解体後の土地をどうするのかまで見据えた上で。
慎重に判断する必要があります。
特に、まだ活用できる可能性が少しでもある建物であれば。
解体以外の選択肢(例えば、藤本が提案するような負担の少ない活用法)を。
先に検討してみる価値は十分にあると、僕は考えています。
3-4. 【まとめ】売却・賃貸・解体 徹底比較表
ここまで解説してきた「売却」「賃貸」「解体」の3つの選択肢。
それぞれの特徴を比較表にまとめました。
ご自身の空き家の状況や、何を最も重視するか。
(スピード、収益性、負担軽減、リスク回避など)
によって、最適な選択肢は異なります。
この表を参考に、じっくりと比較検討してみてください。
(※SWELLユーザーの方は、後でリッチなテーブルブロックに変換してくださいね)
| 比較項目 | ① 売却 (仲介) | ② 売却 (買取) | ③ 賃貸 | ④ 解体 |
|---|---|---|---|---|
| 主な目的 | 現金化 / 負担解放 | 早期現金化 / 早期負担解放 | 収益化 / 資産維持 | リスク除去 / 土地活用準備 |
| メリット | 市場価格に近い売却 / 負担完全解放 | 早期確実な現金化 / 手間少ない / 現状渡し可 | 継続収入 / 資産維持 / 老朽化抑制 | 建物リスク消滅 / 管理不要 / 精神的解放 |
| デメリット | 売れるか不明 / 時間かかる / 仲介手数料 / 契約不適合責任 | 売却価格が安い | 初期費用高 / 空室リスク / 管理手間 / 滞納・トラブルリスク | 解体費用高 / 固定資産税増 / 更地活用困難リスク |
| 期間 (目安) | 数ヶ月~1年以上 | 数週間~1ヶ月程度 | 募集開始まで準備期間 / 運営は長期 | 準備~完了まで1~3ヶ月程度 |
| 費用 (目安) | 仲介手数料 / 税金 / 諸費用 | (売却価格が低い) / 税金 / 諸費用 | リフォーム費 / 仲介・管理費 / 税金 / 修繕費 | 解体費用(100万~) / 滅失登記費 / 固定資産税増 |
| 手間 | 不動産会社選定 / 内覧対応 / 契約手続き | 比較的少ない | リフォーム手配 / 入居者対応 / 管理業務 (委託可) | 業者選定 / 契約 / 近隣挨拶 / 滅失登記 |
| 確実性 | 不確実 (売れるか不明) | 確実 (業者が買取る) | 不確実 (入居者が見つかるか不明) | 確実 (建物は無くなる) |
| 将来性 | 資産はなくなる | 資産はなくなる | 資産維持 / 収益可能性 | 土地のみ残る / 活用次第 |
| 向いている人 | 高く売りたい / 時間余裕あり / 物件状態が良い | 早く手放したい / 手間かけたくない / 現金化急ぐ / 状態悪い | 家を残したい / 収益得たい / 初期投資可能 / 管理できる(委託含む) | 建物リスクなくしたい / 解体費用用意できる / 更地活用策あり |
| 網走市での注意点 | 需要低い可能性 / 冬季の活動停滞 | 買取価格が更に低くなる可能性 | 需要低い可能性 / 家賃相場低い / 寒冷地仕様コスト | 冬期工事困難 / 更地需要低い可能性 / 税金増 |
この比較表はあくまで一般的な目安です。
個々の物件の状況や、あなたの希望によって。
最適な選択肢は変わってきます。
「うーん、こうして見ると、どれも一長一短だな…」
「結局、私の網走の家の場合、どうするのが一番いいんだろう?」
そう感じられたのではないでしょうか。
一般的な解決策には、それぞれメリットもありますが。
同時に無視できないデメリットやリスクも存在します。
特に、費用負担や手間といった点で。
なかなか実行に踏み切れないケースが多いのが実情です。
そこで、次章では。
これらの一般的な方法とは異なるアプローチ。
すなわち、私、藤本が提案する「費用負担を限りなくゼロに近づける」空き家活用戦略について。
詳しくご紹介したいと思います。
もしかしたら、あなたの悩みを解決する。
全く新しい道が見つかるかもしれません。
どの選択肢がベスト? 一緒に考えましょう
売却、賃貸、解体… それぞれにメリット・デメリットがありますね。あなたの網走の空き家とあなたの状況に合わせて、どの道が最適か、専門家の視点からアドバイスします。比較検討のお手伝いも可能です。まずはLINEでご相談ください。
【第四章】藤本流・負担ゼロ戦略!網走の空き家を『お荷物』から『可能性』へ変える3つの秘策
さて、ここまでの章で。
網走市の空き家を放置するリスク。
対策における失敗パターン。
そして一般的な解決策(売却・賃貸・解体)とそのメリット・デメリットを詳しく見てきました。
おそらく多くの方が、こう感じられたのではないでしょうか。
「どの選択肢も、結局は費用や手間、リスクが伴うんだな…」
「もっと負担なく、何とかならないものか…」
そのお気持ち、痛いほどよく分かります。
私、藤本が全国の空き家所有者様からご相談を受ける中で。
最も多く耳にするのが、まさにその「負担」に関する悩みだからです。
そこで、この第四章では。
従来の常識にとらわれない、私、藤本が提案する独自の空き家活用戦略について。
詳しくご紹介したいと思います。
そのコンセプトは。
「オーナー様の費用負担を限りなくゼロに近づけながら、空き家という『お荷物』を、新たな『可能性』へと変える」
ことです。
「そんな虫の良い話、本当にあるの?」
疑念を持たれるのも無理はありません。
しかし、発想を転換し、工夫を凝らせば、道は拓けるのです。
私が目指しているのは、単なる不動産取引ではありません。
空き家を介して、
オーナー様の悩みを解消し、
新たな利用者(入居者・テナント)に価値を提供し、
そして地域にも貢献する。
そんな「三方よし」の関係性を築くことです。
そして、その活動を支えているのが。
全国で100軒以上の空き家を実際に管理・再生されている。
「日本の空き家研究所」代表の竹田さんとの強固なパートナーシップです。
竹田さんの圧倒的な経験値と全国ネットワーク。
そして多様な成功事例から得られる知見は。
私の提案に大きな裏付けと深みを与えてくれています。
これからご紹介する3つの秘策は、すべてこの理念に基づいています。
あなたの網走の空き家の状況や、あなたの希望に合わせて。
最適な方法を一緒に見つけていきましょう。
秘策①:【管理代行】 – 費用ほぼゼロで、手間なく、固定資産税以上の収益を目指す!

これが、私の提案の中核であり。
最も多くのオーナー様に喜んでいただいている方法です。
一言で言えば。
「あなたの網走の空き家を、現状に近い状態で私(藤本)がお預かりし、責任を持って管理・活用(賃貸)します」
というものです。
「え、でも古い家を貸すには、まず大掛かりなリフォームが必要なんじゃないの?」
通常はそう考えますよね。
しかし、私のやり方は少し違います。
高額な初期投資(リフォーム費用)をオーナー様に求めません。
現状のポテンシャルを最大限に活かし、最低限の手入れで貸し出すことを目指します。
藤本流「管理代行」の5つの特徴
オーナー様の費用負担、原則ゼロ!
プロのハウスクリーニング、壁紙・床の全面張替え。
水回り設備の総入れ替えといった、費用のかかるリフォームは行いません。
ただし、貸し出す上で最低限必要となる整備。
これは、原則として私(藤本)の負担で行います。
例えば…
- 残置物の片付け相談・一部撤去:オーナー様と相談の上、不要な家財道具などを撤去・処分します。(使えるものは次に活かすことも)
- 基本的な清掃:最低限、人が入れる程度の清掃を行います。
- 軽微な修繕・応急処置:雨漏り補修、割れたガラス交換、床の一部補強など、安全確保や機能維持に必要な最低限の修繕。
- 給湯器の設置・交換:生活に必須な給湯器がない場合や故障時は、私(藤本)負担で対応します。
- その他、最低限の整備:個々の状況に応じて、必要最低限の手入れを行います。
これにより、オーナー様は初期費用をほとんどかけることなく、賃貸への第一歩を踏み出せます。
「現状好み」の借り手を見つけるマッチング力
ピカピカの物件だけが求められているわけではありません。
「家賃が安ければ、古くても気にしない」
「自分の好きなようにDIYできるなら、むしろ古い方がいい」
「短期間だけ、寝泊まりできれば十分」
「広いスペースを、趣味や仕事の作業場として使いたい」
…など、「現状のまま」あるいは「多少の手直し」で満足してくれる借り手は、実は潜在的に存在します。
私の役割は、そのような借り手を見つけ出し、空き家とマッチングさせることです。
ターゲットとなり得るのは、例えば…
- 費用を抑えたい若者、学生
- DIY好き、クリエイター層
- 短期滞在者(季節労働者、出張者、お試し移住者など)
- 二拠点生活者、セカンドハウス需要
- 地域活動団体
- 起業家・個人事業主
物件の特性と、地域のニーズ(網走ならではの需要)を考慮し、最適な借り手像を設定し、アプローチします。
オーナー様の手間は一切不要!丸投げOK
賃貸経営で最も大変なのは、管理業務です。
(入居者募集、契約、家賃管理、トラブル対応、退去手続きなど)
私の「管理代行」では、これらの業務をすべて私(藤本)が責任を持って行います。
契約形態は、オーナー様と私(藤本)の間、そして私(藤本)と入居者様の間で、それぞれ契約を結びます。
(いわゆる転貸借(てんたいしゃく)に近い形式です)
これにより、
- オーナー様は、入居者と直接やり取りする必要が一切ありません。
- 家賃集金、クレーム対応なども、すべて私が窓口となります。
- あなたは、基本的に「何もしなくて良い」のです。まさに「丸投げ」が可能です。
遠方にお住まいで、網走の物件管理が難しい方には、特に大きなメリットです。
目指すは「固定資産税プラスα」の収益
入居者が見つかり、家賃収入が発生した場合。
その中から必要経費(私の管理手数料など)を差し引いた金額を。
オーナー様へ毎月お支払いします。
目標は、まず年間の維持費(固定資産税など)を、この収益で相殺すること。
そして、可能であれば、さらにプラスの収益をオーナー様にもたらすことを目指します。
空き家が「お金を食う存在」から、「わずかでもお金を生む存在」に変わる可能性があります。
【重要】これは「空室保証」ではありません
一点、非常に重要な注意点があります。
この「管理代行」は、いわゆるサブリース契約(家賃保証・空室保証)ではありません。
私(藤本)が入居者を見つけ、その方から家賃をいただけて。
初めてオーナー様への支払いが発生する仕組みです。
したがって、入居者が見つかるまでの期間や、一時的に空室になった期間については、オーナー様への家賃支払いは発生しません。
この点は、誤解のないよう、あらかじめご了承ください。
あくまで、オーナー様と私(藤本)がリスクを分かち合いながら、協力して空き家活用を目指すパートナーシップである、とお考えください。
【網走市での可能性】どんな活用が考えられる?
網走市の空き家をこの「管理代行」で活用する場合。
どのような可能性が考えられるでしょうか?
- 釣り・アウトドア愛好家の拠点:
網走湖やオホーツク海に近い物件なら、道具置き場付き格安拠点として。
- 農業体験・漁業体験の滞在場所:
網走の第一次産業に関心のある方向けの短期~中期賃貸。
- リモートワーカーの「お試し移住」先:
自然豊かな環境で働きたい方向けの短期賃貸。
- アーティスト・クリエイターのアトリエ兼住居:
広いスペースや静かな環境を求める方向けに、DIY可能な物件として。
- 大学・専門学校生向け下宿:
東京農大生など向けに、相場より安い家賃で。
- 地域活動の拠点:
NPO法人の事務所、地域の集会所、イベント時の荷物置き場として。
- 外国人観光客・労働者向けシェアハウス:
(法規制・近隣配慮が必要)複数人で安く滞在したい層向けに。
これらはほんの一例です。
物件の個性や立地、そして地域の潜在的なニーズを探り当てることで。
思いがけない活用法が見つかるかもしれません。
この「管理代行」モデルなら。
あなたは初期費用ゼロ、手間ゼロで。
空き家が収益を生む資産に変わるかもしれないのです。
魅力的だと思いませんか?
「うちの網走の家でも、可能性があるかも?」
そう少しでも感じていただけたら、ぜひ一度ご相談ください。
秘策②:【倉庫・資材置き場活用】 – 住めない家でも価値を見出す逆転の発想

「藤本さん、うちの家は古すぎて、雨漏りもするし、傾いている気もする。
とてもじゃないけど、人に貸せるような状態じゃないんだよ…」
ご相談を受けていると、このように。
建物の状態がかなり悪く、「人に住んでもらう」という選択肢が現実的ではないケースも少なくありません。
通常なら、「もう解体するしかないか…」と考えてしまうような状況です。
しかし、ここでも諦めるのはまだ早いかもしれません。
人が住むのは難しくても。
「モノを置く場所」としてなら活用できる可能性があるのです。
それが、「倉庫」や「資材置き場」としての活用です。
なぜ「倉庫」なら活用できるのか?
求められる条件が低い:
人が居住するわけではないので。
内装の綺麗さ、水回り設備の状態、断熱性などは、ほとんど問われません。
最低限、雨風がある程度しのげて、荷物を置くスペースが確保できればOK、というケースが多いです。
借り手の対象が異なる:
地域の事業者(建設業、農家、漁師、個人事業主など)。
地域活動団体、趣味のサークルなどが。
資材、道具、機材、収穫物、イベント用品などを保管する場所を探していることがあります。
管理の手間が比較的少ない:
住居として貸す場合に比べて。
入居者トラブルや、頻繁な設備修繕の必要性は低い傾向にあります。
(ただし、契約内容や利用状況によります)
倉庫活用のメリット・デメリット
メリット:
状態の悪い空き家でも活用できる可能性。(解体を回避できるかも)
わずかでも賃料収入を得て、固定資産税の負担を軽減できる可能性。
建物が利用されることで、完全な放置よりは劣化を抑えられる可能性。
デメリット:
得られる賃料は住居用より安くなるのが一般的。
倉庫としての需要が地域にあるかどうかが不確実。
荷物の搬入・搬出のため、ある程度のアクセスが必要。
建物の安全確保(倒壊リスクなど)は最低限必要。
利用方法によっては、近隣への配慮が必要。(騒音、トラックの出入りなど)
火災リスク(保管物による)や保険加入も検討が必要。
【網走市での可能性】どんな需要が見込める?
網走市で倉庫・資材置き場としての需要を考えると。
以下のような可能性が考えられます。
- 農業・漁業関連:農機具、漁具、資材、収穫物(一時保管)など。
- 建設・土木関連:工事用の資材、道具、機材など。
- 運送・物流関連:配送用の一時的な荷物置き場。
- 地域イベント関連:お祭り用品、備品などの保管。
- 個人の趣味・レジャー関連:キャンピングカー、ボート、アウトドア用品などの保管。(セキュリティ配慮要)
- 企業の書類保管など:(セキュリティ等が不要なレベルなら)
港湾地区、工業団地周辺、農村部など。
立地によって求められるニーズも変わってくるでしょう。
藤本の役割
私(藤本)は、オーナー様からお預かりした空き家について。
倉庫・資材置き場としての活用の可能性を探ります。
地域の事業者ネットワークや、直接訪問なども行いながら。
ニーズを持つ借り手を探し出し、マッチングを行います。
契約条件の交渉や契約書の作成。
トラブル発生時の対応なども、もちろん私が行います。
オーナー様には、基本的に手間はかかりません。
「もう壊すしかない」と思っていた家が。
意外な形で誰かの役に立ち、固定資産税の負担だけでも軽減できるかもしれない。
それが、この「倉庫・資材置き場活用」の可能性です。
建物の状態が悪くても、すぐに諦めずに。
この選択肢も検討してみる価値はあります。
秘策③:【解体費用半額引取り】 – 最終手段としての『手放し』サポート
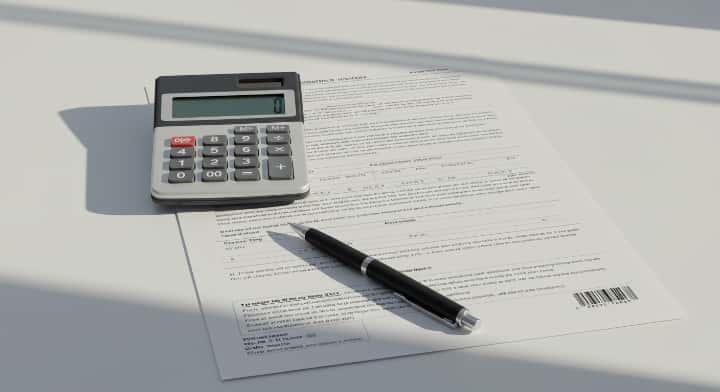
ここまで、空き家を「活用」するための2つの秘策。
(管理代行、倉庫活用)をご紹介してきました。
私(藤本)としては、できる限り、これらの方法で空き家を活かしたい。
オーナー様の負担を減らしつつ、新たな価値を生み出すことを目指しています。
しかし、残念ながら、すべての空き家が活用できるわけではありません。
建物の老朽化が著しく、物理的に活用が困難な場合。
立地条件が悪く、借り手を見つけることが絶望的な場合。
相続問題が複雑にこじれてしまい、共有者全員の合意形成が極めて難しい場合。
あるいは、オーナー様ご自身が。
「もう活用とか維持とかは考えられない」
「とにかく早く、この空き家との縁を切りたい」
と強く望まれる場合。
このような、活用が極めて難しく、かつオーナー様が早期の解決を強く望まれるケース。
その最後の選択肢として私が提案しているのが。
「解体費用の半額程度をご負担いただければ、私(藤本)がその空き家を責任もって引き取る」
という方法です。
なぜ「引取り」なのか? その目的とメリット
通常、不要になった不動産を手放すには、「売却」するか、「自分で解体する」かです。
しかし、売却は買い手が見つからないリスクがあります。
自分で解体するには高額な費用がかかります。
この「半額引取り」は、これらの問題を解決するための、いわば「第三の道」です。
オーナー様のメリット:
- 負担の軽減:自分で解体業者に依頼する場合に比べて、少ない費用負担で空き家を手放すことができます。
- 早期解決・完全な手離れ:私が引き取った時点で、あなたは空き家に関する一切の責任、義務、リスクから解放されます。固定資産税の支払いも、管理の手間も、将来的なトラブルの心配も、もうありません。
- 精神的な解放:長年抱えてきた空き家問題という重荷から、完全に解放され、精神的な安寧を得ることができます。相続トラブルなどで疲弊している場合には、特に大きなメリットとなります。
藤本の役割:
- 私が物件の所有権(またはそれに準ずる権利)を引き継ぎます。
- その後の物件の扱いについては、私が責任を持って対応します。
- オーナー様は、引き渡し後のことについて、一切関与する必要はありません。
なぜ「解体費用の半額負担」をお願いするのか?
「お金を払ってまで、引き取ってもらうなんて…」
そう思われるかもしれません。当然の疑問だと思います。
私がオーナー様に費用の一部負担をお願いするのには、理由があります。
- 藤本側にもリスクとコストがある:
私が物件を引き取った後、その管理や最終的な処分(解体などが必要な場合)には、費用と手間、そしてリスクが伴います。
その一部を、オーナー様にも少しだけご負担いただく、という考え方です。
- 負担の分かち合い:
空き家問題の解決には、どうしてもコストがかかります。
そのコストを、オーナー様と私とで「痛みを分かち合う」ということです。
- 安易な「ゼロ円引取り」との違い:
「無料で引き取ります」と謳う業者には注意が必要です。
不法投棄のリスクや、後で高額請求される可能性がないか、慎重な見極めが必要です。
私は、透明性のある形で、ご納得いただいた上で、責任を持って引き取らせていただきます。
「半額」というのはあくまで目安です。
物件の状態や状況によっては、負担額についてご相談に応じることも可能です。
まずは状況をお聞かせください。
どのようなケースで有効か?
この「半額引取り」が特に有効と考えられるのは、以下のようなケースです。
- 建物の老朽化が激しく、倒壊の危険性が高い。
- アスベスト除去に高額な費用がかかることが判明している。
- 再建築不可の土地である、立地が悪すぎるなど、売却も賃貸も絶望的。
- 共有名義の相続人で、意見が全くまとまらず、誰も管理・費用負担をしようとしない。
- 既に「特定空家」に指定され、行政から改善命令や解体指導を受けている。
- 所有者自身が高齢であったり、健康上の問題を抱えていたりして、今後の管理が困難。
- とにかく一日でも早く、空き家に関する全てのことから解放されたいと強く願っている。
手続きの流れ
- ご相談:まずはLINEやお電話で、状況をお聞かせください。
- 現地調査・ヒアリング:私(または提携スタッフ)が現地を確認し、状況を詳しく伺います。
- 条件のご提示:調査結果に基づき、引取りの可否と、ご負担いただく費用を提示します。
- ご検討・合意:提示内容をご検討いただき、ご納得いただければ合意となります。(相続物件の場合は、原則として共有者全員の同意が必要です)
- 契約締結:引取りに関する契約書を作成し、締結します。
- 決済・権利関係の整理:ご負担いただく費用をお支払いいただき、物件に関する権利関係を整理します。(所有権移転登記等)
- 引取り完了:これで、空き家は完全にあなたの手から離れます。
「お金を払って引き取ってもらう」という選択。
これに抵抗を感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、考えてみてください。
自分で解体すれば、倍以上の費用がかかるかもしれません。
放置し続ければ、リスクは増大し、税金はかかり続け、いつまでも悩みから解放されません。
他の選択肢と比較した場合。
この「半額引取り」は、確実に、そして比較的少ない負担で、問題を「終わらせる」ことができる。
非常に合理的な選択肢となり得るのです。
特に、どうしようもなく手詰まりになってしまっている方。
精神的に追い詰められている方にとっては。
「救いの手」となる可能性もあります。
私としても、リスクが伴うことは承知の上で。
オーナー様の長年の苦しみが解消されるのであれば、そのお手伝いをさせていただきたい。
そう考えています。
『一件でも多くの空き家を、負担なく未来へ繋ぐ』
この活動理念に基づき、最後のセーフティネットとして、この選択肢をご用意しています。
もし、あなたが網走の空き家で深刻にお悩みで。
この「半額引取り」に関心を持たれたなら。
まずは一度、お話だけでも聞かせていただけませんか。
もう限界…? 最後の手段もご相談ください
活用も売却も難しい、相続で揉めている、とにかく早く手放したい… そんな八方塞がりな状況でも、諦めないでください。藤本の「半額引取り」が、解決の糸口になるかもしれません。秘密厳守でご相談に応じます。
【第五章】網走市で活用できる? 空き家関連の支援制度・補助金情報(注意点あり)

空き家の解体やリフォーム、活用を検討する上で。
少しでも費用負担を軽減したいと考えるのは当然のことです。
そこで気になるのが、国や自治体が提供している「支援制度」や「補助金」の存在でしょう。
この章では、網走市で利用できる可能性がある空き家関連の支援制度について。
一般的な情報と、利用する上での重要な注意点を解説します。
どのような支援制度・補助金がある可能性があるか?
全国の自治体では、空き家対策として様々な支援メニューが用意されています。
網走市でも、以下のような制度が実施されている可能性があります。
(※あくまで可能性であり、最新情報は必ず市にご確認ください)
老朽危険空き家解体補助金:
倒壊の危険性が高いなど、一定の基準を満たす空き家を解体する際の費用の一部を補助するもの。
補助対象基準(例:市の事前調査で危険判定)や、補助率・上限額が定められています。
空き家リフォーム補助金:
空き家を改修して、居住用や地域交流拠点などとして活用する場合の費用の一部を補助するもの。
補助対象となる改修内容(例:耐震、バリアフリー、断熱など)や、補助率・上限額、改修後の用途などが細かく定められていることが多いです。
単なる美装化は対象外となる可能性も。
移住・定住促進のための空き家改修補助金:
市外から網走市へ移住する人が、市内の空き家を改修する場合の費用の一部を補助するもの。
移住者の年齢要件や定住期間の要件などが付随することがあります。
多世代同居・近居支援のための改修補助金:
子育て世帯や親世帯などが、同居・近居のために空き家を改修する場合の費用の一部を補助するもの。
空き家バンク制度:
空き家を「売りたい・貸したい」所有者と、「買いたい・借りたい」利用希望者をマッチングするための情報提供制度。
網走市が運営または連携している可能性があります。
登録物件に対して、補助金が優先適用されるなどの連携がある場合も。
専門家相談・派遣制度:
空き家の活用や管理について、専門家に無料で相談できる窓口や、専門家を現地に派遣する制度。
これらはあくまで一般例です。
網走市で現在、どのような制度が、どのような条件で実施されているか。
それは、必ず網走市の公式ウェブサイトや担当部署で最新情報を確認してください。
【最重要】補助金利用における注意点 – 甘い期待は禁物!
第二章の「失敗パターン③」でも触れましたが。
補助金の利用を検討する際には、以下の点を十分に理解しておく必要があります。
安易な期待は、計画の頓挫や思わぬトラブルを招きかねません。
情報は必ず「最新」かつ「公式」を確認!
補助金制度は、毎年度変更・終了することが頻繁にあります。
ネットの古い情報や噂は鵜呑みにしないこと。
必ず、網走市の公式ウェブサイトや担当窓口で、[該当年度]の最新情報を確認してください。
「誰でももらえる」わけではない!厳しい条件を確認
補助対象となる空き家の状態、場所、工事内容、申請者の所得など、非常に細かい条件があります。
ご自身の空き家や計画が、条件をすべて満たしているか、募集要項などを熟読しましょう。
不明な点は市の担当者に確認が必要です。
予算と期間には限りがある!
補助金には予算枠があり、先着順で受付、予算がなくなり次第終了となるのが一般的です。
申請期間も厳密に定められています。
利用を検討する場合は、早めに情報収集・準備し、募集開始後すぐに申請できる体制を整えましょう。
手続きは煩雑!時間と手間がかかる
申請には多くの書類が必要となり、作成・収集に時間と手間がかかります。
申請から交付決定までも数週間~数ヶ月かかることがあります。
自己負担は必ず発生!全額補助は稀
補助されるのは費用の一部であり、上限額も設定されています。
必ず自己負担が発生します。全額補助はまずありません。
自己資金がどれくらい必要か、事前に計算しましょう。
原則「後払い」!立て替え資金が必要
多くの場合、工事完了・支払い後に補助金が振り込まれます。
つまり、工事費用は一旦全額、自己資金で立て替える必要があるのです。
網走市公式情報の確認先(推奨)
最新かつ正確な情報を得るためには、以下の方法で確認することをお勧めします。
- 網走市公式ウェブサイト:
「網走市 空き家 補助金 [該当年度]」などで検索。
関連ページ(都市整備課、建築住宅課など)を探します。
- 網走市役所の担当窓口への電話・訪問:
直接窓口で相談すれば、より詳しい情報を得られる可能性があります。
(参考)網走市役所ウェブサイト: https://www.city.abashiri.hokkaido.jp/
(※リンク先や担当部署はご自身で最新情報をご確認ください)
補助金は、条件に合致し、タイミングよく利用できれば、大きな助けとなります。
しかし、その不確実性や制約を十分に理解しましょう。
「補助金がなくても計画が実行できるか」を常に考えておくことが重要です。
補助金を「主役」にするのではなく。
あくまで「脇役」あるいは「ボーナス」と捉え。
地に足の着いた計画を立てることを強くお勧めします。
なお、私、藤本が提案する3つの秘策は。
基本的に補助金の利用を前提としていません。
もちろん、もしオーナー様が利用可能な補助金があれば。
申請手続きについて、可能な範囲での情報提供やアドバイスはさせていただきます。
補助金、本当に使える? 詳しく確認します
網走市の補助金制度、複雑で分かりにくいですよね。あなたの空き家で使える可能性があるか、最新情報を元に一緒に確認しましょう。補助金申請の注意点や、補助金に頼らない解決策についてもアドバイスできます。LINEでご相談ください。
【第六章】実例に学ぶ!網走市の空き家が再生する成功モデルケース3選
「理屈は分かったけど、実際にうまくいくものなの?」
「藤本さんの言うような方法で、本当に網走の空き家が再生した例があるの?」
ここまで様々なリスクや解決策についてお読みいただき。
そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。
そこでこの章では。
私、藤本がこれまで携わってきた事例や。
パートナーである「日本の空き家研究所」竹田さんの豊富な経験に基づき。
網走市を舞台とした架空の成功モデルケースを3つ、ご紹介したいと思います。
もちろん、これらは架空のストーリーですが。
実際に起こりうる状況や、解決に至るプロセスをリアルに描いています。
あなたの網走の空き家にも、きっと重なる部分があるはずです。
これらのケースを通じて。
あなたの空き家が持つ「可能性」を感じ取っていただければ幸いです。

モデルケース1:【管理代行】相続で放置されていた鱒浦地区の家が、移住希望者の「お試し住居」に

- 物件所在地(想定):北海道網走市 鱒浦地区(JR鱒浦駅近く、オホーツク海が見える高台)
- 建物:築48年 木造2階建て(4LDK)
- 所有者:埼玉県在住 50代 姉妹(共有名義)
- 経緯と悩み:
- 10年前に両親が亡くなり、姉妹で相続。
- 当初はたまに帰省したが、次第に足が遠のき、ここ5年ほどは完全な空き家状態。
- 姉妹ともに遠方在住で、管理は全くできていない。庭は荒れ放題。
- 家の中もホコリっぽく、カビ臭さも感じる。
- 固定資産税(年間約7万円)の支払いが負担。
- 姉妹間で、管理や費用の押し付け合いになり、関係がギクシャク。
- 売却も考えたが、「この状態では難しい。解体しないと売れないかも」と言われた。
- 解体費用(約160万円)も捻出できず、途方に暮れていた。
- 海が見える景色は気に入っており、できれば家を残したい気持ちもあった。
藤本の対応と解決プロセス
オンライン相談と現地調査:
まず、姉妹のお二人とオンラインで面談。
状況と希望(負担なくしたい、できれば残したい)をヒアリング。
その後、私が現地(網走市鱒浦)を訪問し、建物の状態をチェック。
構造的な問題は少ないが、内装の汚れ、水回りの古さ、給湯器の故障などを確認。
庭の荒れ具合も相当だった。
「管理代行」プランの提案:
高額リフォームはせず、現状に近い状態で貸し出す「管理代行」を提案。
最低限の整備(清掃、給湯器交換、草刈りなど)は藤本負担で行うこと。
家賃収入から維持費を相殺し、残りを姉妹に分配すること。
空室保証はないことなどを丁寧に説明。
姉妹は「費用負担がないなら」と合意。
ターゲット設定と整備:
網走への移住希望者や、二拠点生活希望者をターゲットに設定。
「本格移住前のお試し住居」として、月5万円程度の家賃で貸し出す方針を決定。
藤本の負担で、ハウスクリーニング、給湯器交換、庭の草刈りと簡単な整地を実施。
(費用合計 約25万円)
借り手探しとマッチング:
移住関連サイトやSNS、地域の協力者を通じて情報発信。
東京から網走への移住を検討している30代夫婦(リモートワーカー)とマッチング。
「移住前に数ヶ月~1年ほど、網走の暮らしを体験したい」
「初期費用を抑えたい」という希望と合致。
契約と入居開始:
藤本が間に入り、姉妹⇔藤本、藤本⇔入居者夫婦でそれぞれ契約を締結。
家賃(月5万円)の入金を確認し、入居開始。
成果とその後
所有者(姉妹):
費用負担ゼロで、管理の手間と精神的ストレスから解放。
毎月、家賃収入の一部(約3万円)を受け取れ、固定資産税の負担が消え、わずかにプラスに。
姉妹間の関係も改善し、「家を残せてよかった」と安堵。
入居者(移주希望夫婦):
敷金・礼金なし、安い家賃で網走での「お試し移住」が実現。
鱒浦の自然豊かな環境と景色を気に入り、DIYで少しずつアレンジ。
地域住民とも交流し、本格移住に向けて準備中。
藤本:
管理料収入を得つつ、空き家再生、移住希望者の後押しにやりがいを感じる。
姉妹、入居者双方から感謝され、良好な関係を築いている。
このケースのように。
一見価値がないと思われる古い家でも。
視点を変えれば「宝物」になることがあるんです。
費用をかけずに、オーナー様、入居者様、そして僕の三者がハッピーになれました。
モデルケース2:【倉庫活用】市内中心部に近い元商店が、地元のイベント団体の備品庫に

- 物件所在地(想定):北海道網走市 南○条東(市内中心部に比較的近い、かつての小規模商店エリア)
- 建物:築60年 木造平屋建て(元々は食料品店)
- 所有者:網走市在住 70代 男性
- 経緯と悩み:
- 30年前に親から店を継いだが、15年前に閉店。以来、物置代わりに使っていたが、ここ数年は完全に放置。
- 建物はかなり老朽化。雨漏り箇所が複数あり、床も一部抜けそう。人が住める状態ではない。
- 固定資産税(年間約4万円)が、年金暮らしには地味に負担。
- 解体も考えたが、思い出のある店を壊すのに抵抗があり、費用(約120万円)も捻出が難しい。
- 近所からは「見栄えが悪い」という声も聞こえ始めていた。
藤本の対応と解決プロセス
相談と現地調査:
所有者の男性から直接相談を受ける。
現地を確認すると、確かに老朽化は激しい。
しかし、元店舗スペースは広く、天井も比較的高い。
雨漏りはしているが、即時倒壊リスクは低いと判断。
「倉庫活用」プランの提案:
居住用としての再生は困難と判断。
「倉庫・作業スペース」としての活用を提案。
最低限の雨漏り対策(藤本負担)のみ行い、現状のまま格安で貸し出す方針を説明。
所有者は「そんな使い方が」と驚きつつも、「少しでも負担が減るなら」と同意。
ターゲット設定と整備:
地域の活動団体や、資材置き場を必要とする小規模事業者などをターゲットに設定。
家賃は月1.5万円程度で募集することに。
藤本の負担で、ひどい雨漏り箇所の応急的な防水処置を実施。
(費用合計 約5万円)
借り手探しとマッチング:
地域のイベントを主催・協力している地元のNPO団体にアプローチ。
ちょうど、お祭りで使う山車やテントなどの保管場所に困っていたことが判明。
「広さも十分だし、家賃も安い。多少雨漏りしても大丈夫」とのことで、利用が決まる。
契約と利用開始:
藤本が間に入り、所有者⇔藤本、藤本⇔NPO団体でそれぞれ契約を締結。
利用開始。
成果とその後
所有者(70代男性):
解体費用をかけずに済んだ。思い出の店が形を変えて残ったことに安堵。
毎月、家賃収入(約1万円)が入り、固定資産税の負担が大幅に軽減。
地域活動に貢献できている満足感も。近隣からの目も気にならなくなった。
利用者(NPO団体):
安価で広い保管スペースを確保でき、イベント運営の効率が向上。
市内中心部に近い立地も便利。
藤本:
解体寸前だった建物を救い、地域貢献にも繋がった。
管理の手間も少なく、安定した管理料収入を得ている。
このケースのように。
人が住むには厳しい状態の建物でも。
視点を変えれば「倉庫」としての価値が見出されることがあります。
地域の事業者や団体のニーズとマッチングさせることで。
解体を回避し、所有者の負担を軽減することが可能になるのです。
モデルケース3:【解体費用半額引取り】相続放棄寸前だった、 北浜地区の危険な空き家

- 物件所在地(想定):北海道網走市 北浜地区(JR北浜駅近くの線路沿い)
- 建物:築70年以上 木造平屋建て(元々は漁師の家)
- 所有者:相続人不存在(最終的に相続放棄手続き中の甥(道外在住)から相談)
- 経緯と悩み:
- 所有者(叔父)が亡くなり、法定相続人は全員既に他界。
- 次の順位の相続人である甥・姪たちも、誰も相続を希望せず、相続放棄の手続きを進めていた。
- 建物は長年空き家で、老朽化が極めて深刻。屋根は一部崩落、壁も剥がれ落ち、建物全体が傾いている危険な状態。
- JRの線路に近く、万が一倒壊すれば大事故につながる恐れも。
- 市役所からも、危険な状態であるとして、早期の対応を求める連絡が来ていた。
- 相続放棄しても、次の管理人が決まるまで管理義務が残る可能性があり、甥は途方に暮れていた。「放棄しても責任が残るなら…」と藤本に相談。
- 解体費用は約200万円と見積もられたが、誰も負担する意思がなかった。
藤本の対応と解決プロセス
状況確認と法的整理:
相談者の甥の方から詳細な状況をヒアリング。
相続関係、相続放棄の状況、建物の危険度、行政からの指導などを確認。
提携司法書士と連携し、相続放棄後の管理責任リスクなどを整理。
活用不可と判断、引取り提案:
現地調査の結果、建物の危険度は極めて高く、活用は不可能と判断。
放置すれば、倒壊リスクや行政代執行のリスクが非常に高いことを説明。
その上で、「解体費用の半額(約100万円)を、相続人候補者で分担する」ことを条件に、藤本が物件を責任もって引き取ることを提案。
これにより、相続放棄後の管理責任問題や、行政代執行のリスクから解放されるメリットを強調。
相続人候補者間の合意形成:
甥の方を通じて、他の相続人候補者にも状況と提案内容を説明。
「一人あたり数十万円の負担で、全ての責任とリスクから解放されるなら…」
と、最終的に全員の同意を取り付ける。
契約と引取り実行:
相続人候補者全員の同意のもと、負担金の支払いと引き換えに、藤本が物件の管理を引き継ぐ形で契約。
(※所有権移転が困難な場合の特殊な契約形態)
物件の管理・対応:
藤本が物件を引き継ぎ、以降の管理責任を負う。
近隣住民や行政との対応も藤本が行う。
成果とその後
相談者(甥)と他の相続人候補者:
相続放棄後も残りかねなかった管理責任と、倒壊・行政代執行のリスクから完全に解放された。
通常の解体費用の半額以下の負担で、長年の懸案事項を解決できた。
精神的な重圧から解放され、「本当に助かった」と感謝される。
地域社会:
危険な空き家に関するリスクが軽減され、地域の安全性が向上した。
線路への影響懸念も解消された。
藤本:
引き受けにはリスクも伴うが、差し迫った危険を回避し、相続人の方々の窮状を救うことができた。
「日本の空き家研究所」のネットワークも活用し、同様の困難案件への対応ノウハウを蓄積。
このケースのように。
活用が絶望的で、法的な問題も絡み、誰も手が付けられないような「最悪」の状況でも。
解決の道筋は存在します。
放置が最も危険であり。
ある程度の費用負担を受け入れてでも、問題を確実に「終わらせる」ことが。
最終的に関係者全員にとって最善の選択となる場合があるのです。
以上、3つのモデルケースをご紹介しました。
これらはあくまで一例ですが。
あなたの網走の空き家にも、必ず何らかの解決策。
そして「可能性」が眠っているはずです。
諦めずに、まずはその可能性を探ることから始めてみませんか?
あなたの空き家、再生ストーリーを描きませんか?
モデルケースのように、あなたの網走の空き家もきっと変われます。管理代行、倉庫活用、あるいは最後の手段としての引取り。最適な解決策を一緒に見つけ、負担なく未来へ繋ぐお手伝いをします。まずはLINEであなたのストーリーを聞かせてください。
【第七章】よくある質問(FAQ) – 網走市の空き家に関する疑問を解消!

ここまで、網走市の空き家問題について。
リスク、対策、そして私からの提案について詳しくお話ししてきました。
それでも、個別の疑問や不安な点が、まだ残っているかもしれません。
この章では、これまで空き家の所有者様から実際に寄せられた質問の中から。
特に多かったものとその回答をFAQ形式でまとめました。
あなたの疑問解消の一助となれば幸いです。
- 本当に相談は無料なんですか?
-
はい、ご相談は完全に無料です。公式LINEにて受付をしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
- 藤本さんは大阪在住とのことですが、大阪から遠方の物件でも本当に対応可能なんですか?
-
はい、全く問題ありません! 僕は全国の空き家に対応しています。パートナーである「廃墟不動産投資家の村上氏」「日本の空き家研究所代表の竹田氏」のネットワークもありますので、地域に関わらず、まずはご相談ください。距離は問題になりませんよ。
- 築年数がかなり古い家、ボロボロで雨漏りもするような家でも相談できますか?
-
はい、どんな状態の家でも、まずはご相談ください。 「こんな状態じゃ誰も見向きもしないだろう…」とご自身で判断せずに、まずは現状をお聞かせください。LINEで写真(外観・内観)を送っていただけると、より具体的なお話ができます。諦める前に一度、可能性を探らせてください。
- 一軒家だけですか? アパートの空き部屋でも相談可能ですか?
-
はい、一軒家だけでなく、アパートでもご相談可能です。まずは物件の種類と状況をお知らせください。
- 家の中に荷物(家具や生活用品など)がたくさん残っている状態でも大丈夫ですか?
-
はい、残置物がある状態でも全く問題ありません。 ご自身で片付けるのが大変な場合も、ご相談ください。空き家の中に残置物がそのままの場合でも対応することも可能です。そのまま活用できる家具などは、次の入居者に使ってもらうこともあります。
- 相続した物件で、兄弟(姉妹)と共有名義になっているのですが、相談できますか?
-
はい、共有名義の物件でも、ご相談は可能です。ただし、最終的に管理代行契約や引取り契約を結ぶ際には、原則として共有者全員の同意が必要になります。もし、相続人間で意見がまとまらずお困りの場合も、どうすれば合意形成ができるか、解決に向けてのアドバイスやサポートをさせていただきます。
- 管理代行をお願いした場合、固定資産税はどうなりますか? 他に費用はかかりますか?
-
管理代行の場合でも、固定資産税・都市計画税の支払い義務は、引き続き所有者様にあります。僕の目標は、家賃収入でこれらの税金をカバーし、さらにプラスの収益をお返しすることです。その他の費用については、前述の通り、貸し出すための最低限の簡易修繕(雨漏り補修、給湯器交換など)は原則僕が負担しますが、それ以上の大規模な修繕が必要になった場合などは、別途ご相談となります。契約前に費用負担については明確にご説明しますのでご安心ください。
- 管理代行の家賃収入は保証されるのですか? いわゆるサブリース契約とは違うのですか?
-
僕の管理代行は、不動産会社がよく行う、空室期間も一定の家賃を保証する「サブリース契約(家賃保証付き借り上げ)」とは全く異なります。借り手が見つかってから、オーナー様への家賃収入からお支払いさせていただきます。できるだけ早く、そして安定的に借り手が見つかるよう、僕も最大限の努力をすることはお約束します。
- 相談した内容や、個人情報が外部に漏れることはありませんか?
-
はい、ご相談内容は秘密厳守をお約束します。お預かりした個人情報や物件情報は、空き家問題の解決という目的以外で利用することは一切ありません。また、外部に漏洩することがないよう、厳重に管理いたしますので、どうぞご安心ください。
上記以外にも、個別の状況によって様々な疑問や不安があるかと思います。
「こんな基本的なことを聞いてもいいのかな?」
「私のケースは特殊だから、対応してもらえないかも…」
などと心配なさらず、どんな些細なことでも結構ですので、お気軽にLINEでお問い合わせください。
ご相談内容は秘密厳守いたします。安心して、あなたの悩みをお聞かせください。
まだ疑問がありますか? 直接お答えします!
FAQだけでは解決しない、あなた固有の疑問や不安があるはずです。どんな小さなことでも構いません。LINEで直接ご質問ください。藤本が一つひとつ丁寧にお答えし、あなたの不安を解消します。
【最終章】網走の空き家、重荷から希望へ – 未来への一歩を踏み出すために

長い時間、この記事にお付き合いいただき、本当にありがとうございました。
北海道網走市にある空き家を巡る様々な問題点、リスク、そして解決策について。
できる限り詳しく、そして分かりやすくお伝えしようと努めてきました。
厳しい冬の寒さ、流氷がもたらす神秘的な風景、豊かな自然の恵み…。
網走市は、厳しいながらも、他にはない独自の魅力を持つ素晴らしい街です。
そんな街の中で、ポツンと取り残されたように存在する空き家。
それが「問題児」として扱われ、所有者の方々の「重荷」になっている。
この現状は、本当にもったいない、そして悲しいことだと感じています。
私自身、全国の様々な空き家とその所有者様と向き合う中で。
痛感していることがあります。
それは、空き家は単なる「モノ」や「不動産」ではない、ということです。
そこには、かつて住んでいた人々の生活の記憶が刻まれています。
家族の笑顔、涙、成長の記録…。
そして、所有者の方にとっては。
先祖代々受け継いできた大切な財産であり。
故郷との繋がりを象徴する存在でもあるかもしれません。
だからこそ、「ただ壊せばいい」「安く売れればいい」という単純な話ではないのです。
私が目指しているのは。
そうした空き家に込められた想いや価値をできる限り尊重しながら。
所有者の方の経済的・精神的な負担を取り除き、
新たな活用方法を見出すことで、その家に再び息吹を与え、
そして、地域社会にとってもプラスとなるような解決策
を見つけ出すことです。
もちろん、簡単なことではありません。
一つとして同じ状況の空き家はなく、解決策もオーダーメイドで考えていく必要があります。
時には、私の力だけではどうにもならない壁にぶつかることもあります。
それでも、諦めません。
『一件でも多くの空き家を、負担なく未来へ繋ぐことを目指して日々奮闘中です』
この想いを胸に。
過去の無数の空き家と向き合ってきた経験。
そしてパートナーである「日本の空き家研究所」の竹田さんの全国レベルでの知見とネットワークを総動員して。
あらゆる可能性を探ります。
高額な費用がかかる専門家(弁護士など)に頼る前に。
私自身が汗をかき、知恵を絞り、柔軟な発想でできる限りの対応をさせていただきます。
もし、あなたが今、網走市の空き家のことで。
「どうしたらいいか、本当に分からない」
「誰に相談しても、解決策が見つからない」
「費用をかけずに、この問題を何とかしたい」
「もう、一人で悩むのに疲れてしまった…」
そう感じているのであれば。
どうか、その重荷を一人で背負い続けないでください。
まずは、私、藤本に、あなたの声を聞かせていただけませんか?
公式LINEを通じて。
あなたの空き家の状況(場所、築年数、状態など)や。
あなたが抱えている悩み。
そして「本当はどうしたいのか」という想いを、ぜひお聞かせください。
可能であれば、空き家の写真(外観、内観、特に気になる箇所など)を送っていただけると。
より具体的なアドバイスがしやすくなります。
相談は無料です。
相談したからといって、無理に私の提案を受け入れる必要は全くありません。
しつこい営業なども一切いたしません。
まずは、あなたの問題解決の「第一歩」として。
情報収集のつもりで、あるいは単に悩みを打ち明ける相手として。
私を気軽に利用していただければ、それだけで嬉しいです。
行動を起こさなければ、何も変わりません。
しかし、小さな一歩を踏み出すことで、必ず道は開けます。
あなたの網走の空き家が、「重荷」から「希望」へと変わる未来を。
一緒に創り上げていきませんか?
あなたからのご連絡を、心よりお待ちしております。
一緒に、最善の解決策を見つけ出しましょう。
【今すぐ行動を!】未来を変える第一歩はLINE相談から
長い記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました。網走の空き家問題、もう放置はできませんね。解決への道筋は見えましたか? 不安や疑問がまだ残っていても大丈夫。今すぐ下のボタンからLINEで無料相談を! 藤本があなたの状況に合わせた最適なプランを提案し、全力でサポートします。未来を変える決断を、今ここで!
※本記事の情報は2025年5月時点のものです。
※本記事で紹介している支援制度や補助金の情報は2025年5月時点のものです。最新の正確な情報は必ず北海道網走市公式ウェブサイトでご確認ください
※本記事は空き家に関する一般的な情報提供を目的としており、特定の物件に対する法的、税務的、あるいは投資上のアドバイスを提供するものではありません。具体的な対策については、必ず専門家にご相談ください。









