こんにちは、藤本と申します。
僕は大阪に住んでいますが、ご縁があって全国各地へ足を運んでいます。
何をしているかというと、「空き家問題」の解決に取り組んでいるんです。
これは単なる仕事というより、僕自身のライフワーク。
社会的な課題への挑戦、そんな風にも感じています。
なぜなら、空き家って、ただの古い家じゃないんですよね。
一つひとつに、持ち主の方の歴史や想いが詰まっている。
そして、「どうしようもできない」複雑な事情が絡んでいることも多いんです。
それを、これまでたくさん見てきました。
さて、この記事では「北海道 苫小牧市」。
この街の空き家について、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
苫小牧市。
道央圏の南にあって、太平洋に面した大きな港「苫小牧港」がある。
北海道を代表する工業都市ですよね。
製紙業や自動車関連、たくさんの工場が集まっていて、活気があります。
でも、それだけじゃない。
渡り鳥がたくさん来る「ウトナイ湖」。ラムサール条約にも登録されています。
そして、今も活動を続ける雄大な「樽前山」。
豊かな自然にも恵まれた、本当に魅力的な街だと思います。
僕も以前、苫小牧を訪れたことがあります。
広い工業地帯のすぐ隣に、手つかずの自然が広がっている。
あのコントラスト、北海道ならではのスケールの大きさを感じましたね。

でも、そんな発展と自然が共存する苫小牧市でも。
他の多くの日本の街と同じように、「空き家」という問題が静かに広がっているんです。
しかも、その数は少しずつ、確実に増えている。
もしかしたら、この記事を読んでくれているあなたも…
苫小牧市内に、空き家を持っている、あるいは実家が空き家になってしまっている、
そんな状況ではありませんか?
- 相続で引き継いだけど、遠くに住んでいてどうしようもない。
- 親が施設に入って、家がそのままになっている。
- 昔住んでいた家が、今は誰も使っていない。
- どうしたら良いか分からなくて、困っている。
- 固定資産税だけ、毎年払い続けているのが負担だ。
- 家が古くなってきて、ご近所の目が気になる…。
こんな悩みを抱えている方、実は少なくないんです。
「何とかしなきゃ」とは思っていても…
「解体するにはお金がかかるし…」
「売ろうにも、こんな古い家、売れないだろう…」
「貸す? いやいや、リフォームなんて無理だ…」
そんな風に考えて、一歩を踏み出せないでいる。
気持ちは、すごくよく分かります。
今日の記事は、まさにそんなあなたのためのものです。
空き家をそのままにしておくことのリスク。
一般的な解決策にはどんなメリット・デメリットがあるのか。
そして、僕、藤本が提案する、
「お金や手間をできるだけかけずに、空き家を負担から解放し、次に繋げる」
その具体的な方法について。
苫小牧市の空き家問題について、色々な角度から深く掘り下げていきます。
少し詳しくお話しすることになります。
でも、読み終わるころには、きっと。
あなたの空き家問題に対する見方が変わり、
「こうすれば良いのかも」
そんな風に、次の一歩を踏み出すヒントが見つかるはずです。
どうか、少しだけお付き合いください。
一緒に、解決への道を探っていきましょう。
【深層分析】なぜあなたの街、北海道 苫小牧市で「空き家」が増えているのか? その複合的な要因を探る
「空き家問題」とよく聞くけれど。
どうして、あなたの街、北海道 苫小牧市で、使われない家が増えているんでしょうか?
その背景には、色々な理由が複雑に絡み合っています。
表面的なことだけでなく、その根本にある原因を知ることが大切です。
それが、本当に意味のある解決策を見つけるための第一歩になりますからね。

苫小牧市で空き家が増えている背景。
主に、次の5つの要因が考えられます。
要因1:日本全体の縮図「少子高齢化」の進行と世帯構造の変化
これは、苫小牧市だけの話ではありません。
日本全体が抱える、大きな構造的な問題です。
そして、空き家が生まれる一番根本的な原因とも言えます。
- 高齢化率の上昇:
日本全体で、65歳以上の人の割合が増えています。
苫小牧市も、例外ではありません。
昔、家を建てたり買ったりした世代の方々が高齢になっています。
そして、施設に入ったり、亡くなったりすることで、家が空き家になるケースが増えているんです。
特に、昔からある住宅地や、少し前に開発された郊外の団地などでは、この傾向が強いかもしれませんね。
- 単身・夫婦のみ高齢者世帯の増加:
昔のように、大家族で一緒に住むことが減りました。
核家族化が進み、高齢者だけ、あるいは一人暮らしの高齢者世帯が増えています。
こうした世帯では、住んでいる方が病気になったり、亡くなったりすると、家がそのまま誰も住まない状態になりやすいんです。
- 少子化による住宅継承者の不在・負担増:
生まれてくる子どもの数が減っています。
そのため、親の家を相続する子どもがいなかったり、
いても一人っ子で、遠くに住んでいたり、自分の生活で手一杯だったり。
実家の管理まで手が回らない、というケースが増えています。
兄弟姉妹で相続しても、話がまとまらずに放置、ということもよくあります(これは後で詳しく話しますね)。
こういう人口構造の変化が、親世代が建てた家を、子世代がスムーズに引き継ぐことを難しくしています。
これが、空き家が増える大きな土壌になっているんですね。
苫小牧市の将来の人口予測を見ても、この流れは今後も続くと考えられます。
要因2:若年・中年層の「市外・道外への流出」とUターン・二地域居住の障壁
苫小牧市は、北海道の中でも大きな工業都市です。
仕事の機会も、ある程度はあるでしょう。
でも、もっと色々な仕事を探したい、もっと高い給料が欲しい。
あるいは、大学や専門学校で学びたい。
そんな理由で、札幌や、東京・大阪などの大都市へ移り住む若い人たちや、働き盛りの世代も少なくありません。
そうして、一度苫小牧を離れた人たちが、親から実家を相続した場合。
多くの場合、次のような壁にぶつかります。
- 生活の拠点がもう他にある:
移り住んだ先で仕事に就き、家庭を持ち、子どもが学校に通っている。
生活の基盤が完全にできあがっている場合、
たとえ実家が残っていても、苫小牧に戻って住む、というのは現実的に難しいですよね。
- 遠くからの管理は大変すぎる:
たまに帰省するだけでも、時間もお金もかかります。
家の状態をチェックしたり、庭の手入れをしたり、郵便物を確認したり。
特に大変なのが、冬の雪対策。
雪下ろしや、水道が凍らないようにする「水抜き」。
年に数回帰るだけでは、とても十分な管理はできません。
- Uターンや二地域居住のハードル:
「いつかは故郷に…」と思っていても、
苫小牧で希望通りの仕事が見つかるか?
パートナーは賛成してくれるか?
子どもの学校はどうする?
あるいは、二つの地域で生活する「二地域居住」をするにも、経済的・時間的な余裕がない。
色々な理由で、なかなか実現できないのが現実です。
その結果、相続した実家は、「使う予定はないけど、捨てる(売る・壊す)こともできない」
そんな宙ぶらりんな状態になってしまう。
そして、時間が経つうちに、空き家として固定化してしまうんです。
要因3:北海道特有の「厳しい気候条件」と高額な維持管理コスト
これは、北海道に不動産を持つ上で、絶対に無視できないポイントです。
本土とは違う、厳しい自然環境。
これが、空き家の維持管理を格段に難しくし、費用も高くする大きな原因になっています。
特に注意が必要なのは、やはり「冬」ですよね。
- 重い雪との戦い:
苫小牧市も、冬には雪が積もります。
屋根に積もった雪は、かなりの重さになります。
そのままにしておくと、家が歪んだり、潰れたりする危険も。
だから、定期的な「雪下ろし」が必要になります。
でも、これが重労働だし、屋根からの転落事故も多くて危険です。
遠くに住んでいたら、自分でやるのはほぼ不可能ですよね。
業者に頼むと、もちろん費用がかかります。
- 水道管凍結・破裂の恐怖:
冬の厳しい冷え込みで、水道管の中の水が凍る。
水は凍ると体積が増えるので、管が破裂してしまうことがあります。
そして、気温が上がって氷が溶けると、そこから水が噴き出す…。
床下が水浸しになったり、壁の中に水が染み込んだり。
気づくのが遅れると、被害は甚大です。
これを防ぐには、冬になる前に水道管の水を抜く「水抜き」という作業が必須。
あるいは、凍結防止ヒーターを付けたり、微量の水を出しっぱなしにしたり、暖房をつけっぱなしにしたり… いずれも手間や費用がかかります。
- 「すがもり」という厄介な現象:
北海道の家でよく聞くトラブルです。
屋根の雪が、部屋の暖かさや太陽の熱で溶けます。
その溶けた水が、軒先で冷たい外気に触れて凍る。
そうすると、氷のダムみたいなものができて、水の流れをせき止めてしまうんです。
行き場を失った水が、屋根材の隙間などから、じわじわと家の中に染み込んでくる。
これが「すがもり」です。
雨漏りと違って、気づきにくいことも多く、知らないうちに天井裏や壁の中が腐ってしまうこともあります。
冬だけではありません。
- 夏場の湿気とカビ:
夏は過ごしやすいイメージの北海道ですが、意外と湿度は高くなります。
人が住んでいない家は、窓を閉め切っていて換気が悪い。
だから、湿気がこもりやすいんです。
壁や畳、押し入れの中などがカビだらけ…なんてことも珍しくありません。
冬場も、暖房と外気の温度差で「結露」が発生しやすく、カビの原因になります。
- 古い家の断熱性能の問題:
昔の家は、今ほど断熱材がしっかり入っていなかったり、窓が断熱性の低いものだったりします。
だから、冬は寒くて暖房費がかさむ。
夏は日差しで暑くなりすぎることも。
もし、その家を誰かに貸したり、自分で使ったりしようと思ったら。
断熱性能を上げるためのリフォームが必要になるかもしれません。
でも、それには結構な費用がかかります。
こうした北海道ならではの気候に対応して、空き家を維持管理するには。
専門的な知識や、こまめな手入れが必要です。
そして、光熱費(凍結防止のための暖房など)、修繕費、管理を業者に頼む費用など、お金もかかります。
この負担の重さが、「もう管理できない…」と所有者の方に思わせてしまう。
そして、放置につながってしまう大きな理由の一つになっているんです。
北海道にお住まいの方なら、この大変さはよくお分かりになるのではないでしょうか。
要因4:経済・産業構造の変化と「住宅需要のミスマッチ・偏在」
苫小牧市は、港を中心とした工業都市として発展してきました。
でも、時代とともに、経済や産業の形も変わっていきます。
それが、地域の住宅のニーズにも影響を与え、空き家問題の原因になっている面もあります。
- 産業構造の変化と雇用の影響:
例えば、昔は盛んだった産業が縮小したり、企業の工場が移転したりすると、
そこで働く人が減って、地域の人口が減るかもしれません。
そうなると、当然、住宅の需要も減ってしまいます。
苫小牧市の基幹産業の動向によっては、そういう影響が出る可能性もあります。
- 社宅などの減少:
昔は、会社が従業員のためにたくさんの社宅や寮を持っていました。
でも、最近はそういうのが減ってきています。
会社が持っていた古い社宅が、使われなくなって空き家になっている、というケースもあるかもしれません。
- 昔の家と今のニーズのズレ:
昔、たくさんの人が住んでいた時代に建てられた家。
例えば、郊外の大きな団地とか。
そういう家が、今の時代の暮らし方や家族の形(一人暮らしや夫婦だけ、など)に合わなくなってきている。
間取りが広すぎたり、設備が古かったり。
バリアフリーじゃなかったり。
そういう点が、今の若い世代などから敬遠される理由になることもあります。
これが「住宅のミスマッチ」です。
- 地域による需要の差:
苫小牧市内でも、場所によって住宅の人気には差がありますよね。
駅に近いとか、スーパーや学校が近いとか、比較的新しい住宅地とか。
そういう便利な場所は需要が高いかもしれません。
でも、中心部から離れていたり、坂道が多かったり、古い家が密集していたりするエリアは、
なかなか住みたいという人が現れず、空き家がそのまま残りやすい傾向があるかもしれません。
これを「需要の偏在」と言ったりします。
このように、経済や社会の変化が、住宅の「欲しい人(需要)」と「ある家(供給)」のバランスを崩してしまう。
そして、使われなくなった家が「空き家」として取り残されていく。
そういう構造的な問題も、背景にはあるんです。
要因5:「相続」をめぐる手続き・権利関係の複雑さと意識の問題
空き家が生まれる、一番多いきっかけ。それは「相続」です。
親が亡くなって、子どもが家を引き継ぐ。
でも、その相続が、空き家問題をさらにややこしく、深刻にしてしまうことがあるんです。
- 相続登記がされていない問題:
不動産の持ち主が亡くなったら、相続人が自分の名前に変える「相続登記」が必要です。
でも、以前はこの登記が義務じゃなかった。
だから、亡くなったおじいちゃん、あるいはもっと前の人の名義のまま、
放置されている不動産が、実はたくさんあるんです。
そうなると、いざ売ろうとか、貸そうとか思っても、
「今の本当の持ち主は誰?」がはっきりせず、手続きが進められない。
管理の責任も曖昧になってしまいます。
(※注意:2024年4月から相続登記は義務になりました! 過去の相続も対象です。怠ると罰金も…)
- 共有名義で話がまとまらない問題:
兄弟姉妹など、複数人で家を相続すると、「共有名義」になります。
この共有の不動産をどうするか、例えば、売る、貸す、壊すといった大事なことを決めるには、
原則として、共有している人、全員の同意が必要です。
でも、これがなかなか大変なんです。
「誰が管理するの?」
「固定資産税や修理代は、誰がどう払うの?」
「売りたい人」と「残したい人」。
意見がバラバラで、話し合いが進まない。
特に、相続人同士が遠くに住んでいたり、仲が悪かったりすると、もう大変。
結局、誰も責任を取らないまま、時間だけが過ぎて放置…というケースが本当に多いんです。
- 「実家」への特別な感情と現実逃避:
生まれ育った家、家族との思い出が詰まった家。
そういう特別な場所に対して、「簡単に手放したくない」「いつか誰かが使うかも」「ご先祖様の土地だから」
そんな風に思う気持ちは、とてもよく分かります。
でも、その感情が強すぎると、
空き家が抱えるリスク(税金、老朽化、管理費など)という現実から目をそむけてしまう。
客観的な判断ができなくなってしまうことがあるんです。
相続人間で、実家に対する思い入れが違うことも、対立の原因になります。
- どうすれば良いか分からない(知識・情報不足):
相続の手続きって、結構複雑です。
不動産の売買や税金、活用の方法なんて、普通はよく分かりませんよね。
何から手をつけていいか分からなくて、
誰に相談すればいいかも分からなくて、
それで、つい問題を先送りにしてしまう。
そういう方も、たくさんいらっしゃいます。
これらの相続に関する色々な問題が、空き家をちゃんと管理したり、活用したりするのを邪魔して、
問題を長引かせ、さらに複雑にしてしまっているんです。
—
どうでしょうか。
苫小牧市で空き家が増えている背景には、
人口の変化、人々の暮らしの変化、経済や産業の変化、北海道の気候、そして相続の問題…
本当に色々な、そして根深い原因が複雑に絡み合っているんですね。
だからこそ、その解決は簡単ではありません。
一つの決まった方法で、全ての空き家が解決するわけじゃない。
それぞれの空き家が置かれた状況、持ち主の方の考え。
それを丁寧に見て、一番合った方法を見つけていく必要があるんです。
【警告】その放置、本当に大丈夫? 苫小牧市の空き家がもたらす深刻すぎるリスク【詳細解説】
「空き家があるのは知ってるけど、まあ、すぐに困るわけじゃないし…」
もし、あなたが少しでもそう思っているなら…
それは、とても危険な考え方かもしれません。
空き家を放置することは、
まるで時限爆弾を抱えているようなものなんです。
いつ、どんな形で問題が爆発するか分からない。
そして、その影響は、あなた自身だけにとどまりません。
家族、ご近所、地域社会、そして将来の世代にまで及ぶ可能性があるんです。
ここでは、北海道 苫小牧市の状況も考えながら、
空き家を放置することで起こりうる、5つの重大なリスクについて。
その深刻さと具体的な影響を、詳しく解説していきます。
「自分は大丈夫」とは思わずに、
どうか、「自分のこと」として真剣に受け止めてください。

リスク1:【経済的損失・増大】「負」動産化への道…止まらない税負担、管理費、そして突然の増税リスク
空き家を持っていることで、一番直接的に感じるリスク。
それは、やっぱり「お金」の問題ですよね。
放置すればするほど、その負担は重く、大きくなっていきます。
(1) 逃れられない「固定資産税・都市計画税」の支払い義務
苫小牧市内に土地や建物を持っている。
それだけで、毎年必ずかかってくる税金があります。
それが「固定資産税」と「都市計画税」(市街化区域内の場合)です。
これは、その家を使っていようがいまいが、関係ありません。
所有している限り、毎年1月1日時点の持ち主に支払い義務が発生します。

税金の額は、その土地や建物の価値(固定資産税評価額)によって決まります。
苫小牧市内の物件なら、場所や広さにもよりますが、
年間で数万円から、場合によっては数十万円になることも。
考えてみてください。
何の収入も生まない空き家のために、毎年、確実にそのお金が出ていくんです。
これが5年、10年、20年…と続いたら?
総額は、かなりの金額になりますよね。
まさに、持っているだけでお金が減っていく「負」動産。
そんな状態になってしまうんです。
もし、税金を払い忘れて滞納してしまうと…
延滞金がどんどん加算されます。
それでも払わないと、最終的には、あなたの財産。
例えば、給料や預金、あるいはその空き家自体が差し押さえられてしまう可能性だってあるんです。
(2) 恐怖の「特定空家」指定と固定資産税最大6倍のリスク
そして、さらに怖いのが、この「特定空家」という制度です。
これは、「空家等対策の推進に関する特別措置法」という法律に基づいています。
簡単に言うと、
「放置しておくのが、あまりにも危険だったり、汚かったり、景観を損ねたりして、周りに迷惑をかけている空き家」
これを、市町村(この場合は苫小牧市)が「特定空家」として指定できる、というものです。
具体的には、次のような状態が考えられます。
- 建物が傾いている、壁に大きなヒビが入っている(倒壊の危険)。
- 屋根や外壁が剥がれ落ちそうになっている(飛散の危険)。
- ゴミが大量に放置されて、ひどい臭いがする(衛生上有害)。
- 害虫やネズミがたくさん発生している(衛生上有害)。
- 建物がボロボロで、街の景観を著しく悪くしている。
- 庭の木が隣の敷地や道路に大きくはみ出している。
- 誰でも簡単に入れてしまう状態で、犯罪に使われる恐れがある。
苫小牧市も、地域の安全や住みやすさを守るために、
こういう状態の空き家がないか、パトロールしたり、住民からの情報を受けたりしています。
もし、「これは問題だ」と判断されると、まず所有者に連絡が来て、
「ちゃんと管理してくださいね」という助言や指導があります。
それでも改善されない場合、「勧告」という、もう少し強い措置が取られます。
ここが、非常に重要なポイントです。
この「勧告」の対象になった時点で、
固定資産税・都市計画税の「住宅用地の特例」という割引制度が、適用されなくなってしまうんです!
「住宅用地の特例」というのは、家が建っている土地の税金を、
最大で6分の1まで安くしてくれる、とても大きな割引制度です。
これが無くなる、ということは…
土地にかかる税金が、いきなり最大で6倍に跳ね上がる可能性がある、ということなんです!
例えば、今まで年間10万円だった税金が、ある日突然、60万円になる。
そんな、悪夢のようなことが現実に起こり得るんです。
これは、経済的にものすごい打撃ですよね。
さらに、「勧告」にも従わないと、「命令」が出されます。
それでもダメなら、最終手段として、
行政が代わりに家を解体する「行政代執行」が行われることもあります。
その解体費用は、もちろん、全額、所有者に請求されます。
「うちの家は、まだそこまでひどくないから大丈夫」
そう思うのは、危険かもしれません。
法律はどんどん厳しくなっていますし、行政の目も光っています。
長年放置している空き家は、いつ「特定空家」に指定されてもおかしくない。
そういう時代になっているんです。
(3) かさみ続ける維持管理費・修繕費
税金だけではありません。
空き家を持っているだけで、他にも色々なコストがかかります。
- 最低限の管理にかかる費用:
遠くに住んでいる場合、たまに様子を見に行くだけでも交通費がかかります。
庭の草刈りや、冬の雪下ろし、水抜きなどを誰かに頼むなら、その費用も必要です。
シルバー人材センターや便利屋さん、管理業者などに頼むことになりますね。
- 突発的に発生する修繕費用:
建物は、何もしなくても時間とともに傷んでいきます。
台風で屋根が壊れた、大雪で雨樋が歪んだ、給湯器が壊れた、水道管が破裂した…
そんな予期せぬトラブルが起これば、修理代は所有者負担です。
放置期間が長いほど、こういうリスクは高まります。
修理代も、数十万円単位になることが少なくありません。
- 火災保険料など:
空き家でも、火事や自然災害のリスクはあります。
むしろ、放火のリスクなどは高いかもしれません。
万が一に備えて火災保険に入っておくのが望ましいですが、
空き家専用の保険は、普通の家の保険よりも割高になることが多いです。
また、もし自分の家のせいで隣に被害を与えた場合の賠償責任保険も考えられます。
- 将来の解体費用(見えない負債):
もし、最終的に解体するしかなくなったら?
その費用(さっきも言ったように、100万円~300万円以上かかることも)を、
どこかで用意しなければなりません。
これも、見えないけれど確実に存在する、将来の負担(負債)と言えます。
こういうコストも、毎月、毎年と積み重なっていけば、かなりの額になります。
空き家を放置するというのは、経済的に見ても、
ただただ損をし続け、将来のリスクを増やし続けるだけの行為なんです。
リスク2:【建物の劣化・崩壊】思い出の家が廃墟に…資産価値ゼロ、そして危険物へ
「家は、人が住まなくなると、あっという間に傷む」
これ、本当によく聞く言葉ですよね。
迷信なんかじゃなくて、ちゃんとした理由があるんです。
(1) 湿気・カビ・腐朽菌による内部からの侵食
人が住んでいる家は、毎日ドアを開け閉めしたり、換気扇を回したり、
暖房を使ったりすることで、自然と空気が入れ替わります。
湿気も外に逃げていきます。
でも、空き家は窓もドアも閉め切り。
空気の流れが、ほとんどありません。
そうすると、家の中に湿気がどんどん溜まっていくんです。
特に、梅雨の時期や、冬の結露(窓や壁が濡れるやつですね)。
それで、壁や天井、床、畳、押し入れの中とかが、カビだらけに…
見た目が悪いだけじゃなく、カビ臭いし、健康にも良くないですよね。
さらに怖いのが、「木材腐朽菌」という菌。
湿った木材を栄養にして、どんどん増えていきます。
この菌が、家の柱や梁といった大事な構造部分の木材を、
中からボロボロに分解してしまうんです。
床を踏むとブカブカしたり、柱がスカスカになったり。
それは、この腐朽菌の仕業かもしれません。
一度腐ってしまうと、修理も大変です。
(2) 雨漏り・すがもりによる構造体への致命的ダメージ
屋根や外壁も、時間が経つと劣化します。
ペンキが剥げたり、壁のつなぎ目(コーキング)がひび割れたり、
屋根瓦がズレたり割れたり。
そういうわずかな隙間から、雨水が家の中に入り込んでくる。
これが「雨漏り」です。
雨漏りは、建物にとって本当に大敵。
天井や壁にシミができるだけじゃないんです。
見えない壁の中や天井裏に水が回って、
断熱材を濡らしたり、柱や梁を腐らせたり。
建物の強さを、根本から弱らせてしまいます。
北海道特有の「すがもり」も、同じように深刻です。
屋根の雪が溶けて、軒先で凍って、水の逃げ道を塞いでしまう。
それで、屋根の隙間から水が家の中に入ってくる。
これも、じわじわと建物を蝕んでいきます。
雨漏りもすがもりも、一度始まると、どこから漏れているのか見つけるのが大変。
修理にも、結構なお金がかかることが多いです。
しかも、漏電の原因になって、火事につながる危険だってあります。
(3) シロアリ・害虫・害獣の巣窟化
人が住まなくなった家は、残念ながら、
虫や動物たちの格好の住処になってしまうことがあります。
- 忍び寄る脅威「シロアリ」:
特に怖いのがシロアリです。
湿気を含んだ木材が大好き。
床下や壁の中など、普段は見えない場所で、
静かに、でも確実に、家の土台や柱を食べていきます。
気づいた時には、家の構造がボロボロになっていて、
地震が来たらひとたまりもない…なんてことも。
シロアリの駆除や、被害箇所の修理には、
専門的な技術が必要で、費用もかなり高額になることが多いです。
- ネズミや害獣の侵入:
ネズミや、最近ではハクビシン、アライグマといった害獣。
コウモリや鳥などが、家の隙間から入り込んで住み着くことも。
彼らは、柱や壁、断熱材をかじって巣を作ったり、
電気の配線を噛み切って、漏電や火事を引き起こしたりする危険があります。
それに、糞や尿をまき散らすので、ひどい臭いがしたり、
衛生的に問題があったり、病原菌を運んでくる可能性だってあります。
夜中に天井裏を走り回る音も、気味が悪いですよね。
- ゴキブリやハチなどの害虫:
もちろん、ゴキブリなどの害虫も発生しやすくなります。
軒下や壁の隙間に、スズメバチが巣を作ってしまう、なんてことも。
これは非常に危険です。
これらの被害は、建物の価値を大きく下げるだけでなく、
近隣の家にも迷惑をかける原因になります。
(4) 設備の故障・劣化
家の中にある設備。
給湯器、エアコン、換気扇、トイレ、お風呂、キッチン…。
これらも、長期間使わないでいると、故障しやすくなります。
久しぶりに電源を入れても動かない。
水道の蛇口をひねったら、サビ色の水が出てくる。
配管が詰まって水が流れない。
ゴムのパッキンが劣化して水漏れする。
そんなことが、本当によく起こるんです。
もし、その家をまた使おうと思ったら。
これらの設備を点検したり、修理したり、交換したりするのに、
予想外のお金がかかってしまう。
「こんなはずじゃなかった…」と計画が狂ってしまうこともあります。
(5) 最終末路としての「倒壊・崩壊」
そして、一番怖いのが、建物が「壊れる」こと。
湿気や雨漏りで木材が腐り、
シロアリに食われ、
基礎が弱くなっていく…。
そうやって、建物の強度がどんどん失われていくと、
地震や台風、大雪といった自然の力に耐えられなくなります。
あるいは、特別な力が加わらなくても、
ある日突然、家自身の重さに耐えきれずに、
崩れ落ちてしまう可能性だって、ゼロではありません。
特に、古い時代の基準(昭和56年以前の旧耐震基準)で建てられた家は、
今の基準から見ると、地震への備えが十分でないことが多いです。
放置による劣化が加われば、その危険性はさらに高まります。
もし、建物が倒壊したら?
それ自体が危険なのはもちろんですが、
隣の家を壊してしまったり、
道路を塞いでしまったり、
もし、人が近くにいたら、大怪我をさせてしまうかもしれません。
そうなったら、損害賠償など、大変な責任問題になります。
—
どうでしょうか。
空き家を放置するということは、
物理的に、建物をどんどん朽ちさせていく行為なんです。
そして、最終的には、
資産としての価値を失い、
ただの「危険物」へと変えてしまう可能性がある。
たくさんの思い出が詰まった、大切な我が家や実家が。
管理を怠ったばかりに、ボロボロの廃墟になってしまう…
それほど悲しいことは、ないですよね。
放置は、単にお金が損をする、というだけではないんです。
大切な資産と、そこに刻まれた記憶をも失わせてしまう行為なんですよ。
リスク3:【地域社会への悪影響】ご近所トラブル・犯罪誘発・景観破壊… あなたの空き家が地域の問題児に
空き家の問題は、持ち主だけの問題では終わりません。
たった一軒の、管理されていない空き家が、
その周りに住む人たちや、地域全体に、
色々な迷惑や悪影響を及ぼしてしまうことがあるんです。
「自分の家のことだから、放っておいてくれ」
そんな言い分は、もう通用しません。
地域の一員としての責任が、問われる時代になっています。
(1) 街並みの景観破壊と地域イメージの低下
まず、見た目の問題です。
手入れされていない空き家は、やっぱり、みすぼらしいですよね。
- ボロボロの外観:
ペンキが剥げ、壁は汚れ、窓ガラスは割れている。
雨戸やシャッターは壊れたまま。
そんな家が一つあるだけで、その通りの雰囲気、地域のイメージが悪くなってしまいます。
- 荒れ放題の庭:
雑草がぼうぼうに生い茂って、庭の木は伸び放題。
隣の家や道路にまではみ出している。
枯れ葉や、どこからか飛んできたゴミが散らかっている。
こういう状態は、だらしなくて不潔な印象を与えます。
地域のきれいな景観を、台無しにしてしまいます。
- 地域の評判が悪くなる:
苫小牧市には、活気ある港や工場、美しい自然がありますよね。
でも、放置された空き家が目立つようになると、
そういう良いイメージも、損なわれてしまうかもしれません。
「あの辺りは、空き家が多くて、なんだか寂れているね」
そんな悪い評判が立つと、その地域の不動産の価値が下がったり、
新しく住みたいという人が減ってしまったりする原因にもなりかねません。
地域の景観は、そこに住むみんなの財産です。
たった一軒の空き家が、その価値を下げてしまう。
その可能性があることを、知っておく必要があります。
(2) 不法投棄・害虫・悪臭による衛生環境の悪化
ちゃんと管理されていない空き家は、衛生面でも大きな問題を起こします。
- ゴミ捨て場にされる:
人の目につきにくい、誰も管理していないことがバレバレの空き家の敷地。
残念ながら、心ない人たちが、勝手にゴミを捨てていく場所になりやすいんです。
古い家電、家具、タイヤ、生活ゴミ…。
気づいたら、ゴミ屋敷みたいになっていた、なんてことも。
- 虫や動物の発生源になる:
放置されたゴミや、手入れされない庭、湿気が多い家の中。
そういう場所は、ネズミ、ゴキブリ、ハエ、蚊などの害虫や、
カラス、ハト、アライグマ、ハクビシンみたいな害獣にとって、
最高の繁殖場所になってしまいます。
そして、そういう虫や動物は、空き家の中だけにとどまりません。
近所の家にも入り込んできて、食べ物を荒らしたり、
糞や尿で汚したり、夜中に騒音を出したり、
病気を運んできたり…色々な被害をもたらします。
- ひどい臭いの発生源になる:
捨てられたゴミ、動物の糞尿、カビ、腐った建材…。
こういうものから発生するひどい臭いは、風に乗って周りに広がります。
近所の人は、窓を開けられなかったり、洗濯物を外に干せなかったり。
日常生活に、深刻な不快感を与えてしまいます。
こういう衛生問題は、ただ「気持ち悪い」だけじゃないんです。
アレルギーや感染症の原因になるなど、健康への被害も心配されます。
周りに住む人たちの心と体に、大きなストレスを与えてしまうんです。
(3) 倒壊・飛散・火災による安全性の脅威
古くなって、ボロボロになった空き家。
それは、地域にとって、物理的に「危険な物」になりえます。
- 家が壊れるリスク:
さっきも言いましたが、老朽化した家は、
地震や台風、大雪などで、倒壊する危険があります。
もし倒れて、隣の家を壊したり、道路を塞いだり、
通行人に怪我をさせたりしたら…
持ち主は、とてつもない損害賠償責任を負うことになります。
- 物が飛んでくるリスク:
強い風が吹いたとき。
屋根瓦やトタン、壁の一部、割れた窓ガラスなどが、
剥がれて飛んでくる可能性があります。
それが、近所の家や車に当たったり、人に当たったりしたら大変です。
特に、台風のシーズンや、苫小牧のように風が強い日は要注意です。
- 火事のリスク:
空き家は、放火のターゲットにされやすい、と言われています。
枯れ草やゴミが散らかっていたら、火はあっという間に燃え広がります。
それに、古い電気配線が原因で漏電して火事になる、という危険もあります。
もし火事になったら、自分の家が燃えるだけじゃなく、
隣の家に燃え移って、大惨事になる恐れがあります。
(法律上、重大な過失がなければ隣家への賠償責任は免除されることが多いですが、ご近所との関係は最悪になりますよね…)
これらの事故は、人の命に関わる可能性だってあります。
絶対に、軽く考えてはいけないリスクなんです。
(4) 不審者の侵入・犯罪誘発による治安の悪化
人の出入りがなく、管理されていない空き家。
それは、残念ながら、犯罪を呼び込みやすい場所にもなってしまいます。
- 不法侵入・不法占拠:
鍵が壊れていたり、窓ガラスが割れていたり。
そんな家は、誰でも簡単に入れてしまいます。
近所の若者が勝手に入り込んで、たまり場にしてしまったり。
住む家がない人が、寝泊まりする場所にしてしまったり。
もっと悪いことに、犯罪を企む人が隠れ家にしたり、
盗品を隠す場所として使ったりする可能性だってあります。
- 犯罪を誘う「割れ窓理論」:
「割れ窓理論」という考え方があります。
窓ガラスが1枚割れているのを放置しておくと、
「ここは誰も気にしていないんだな」と思われて、
他の窓も割られたり、ゴミが捨てられたり、
どんどん環境が悪くなって、最終的には大きな犯罪も起こりやすくなる、
というものです。
放置された空き家は、まさにその「割れた窓」。
地域の秩序が乱れているサインとなり、
他の軽い犯罪や、子どもの非行などを誘発するきっかけになりかねません。
- 子どもたちの危険な遊び場:
子どもって、探検が好きですよね。
廃墟みたいな空き家は、好奇心をくすぐるのかもしれません。
でも、もし忍び込んで遊んでいるうちに、
腐った床が抜けて落ちたり、
不安定なものが落ちてきて怪我をしたりしたら…
取り返しのつかない事故につながる危険があります。
たった一軒の空き家が、その地域の安全を脅かし、
住民、特に子どもやお年寄りの不安を大きくしてしまう。
そんな存在になってしまう可能性があるんです。
(5) 地域コミュニティへの悪影響と住民間のトラブル
放置された空き家は、目に見える被害だけでなく、
地域の人々の繋がり、コミュニティにも悪い影響を与えます。
- 近隣住民のストレスと不満:
自分の家の隣に、管理されていないボロボロの空き家がある。
それだけで、毎日ストレスを感じますよね。
「いつ崩れるんだろう…」
「もし火事になったら、うちにも燃え移るかも…」
「夜、誰か潜んでいたら怖いな…」
そんな不安が、ずっと心の中に居座り続けることになります。
- 住民同士のトラブルの原因に:
庭の木が自分の敷地にはみ出してきて困る。
空き家から変な臭いがする、虫がたくさん出る。
具体的な被害が出始めると、我慢にも限界があります。
近隣住民が、空き家の所有者に苦情を言いたくても、
所有者が誰か分からなかったり、遠くに住んでいて連絡が取れなかったり。
あるいは、苦情を言っても無視されたり。
そうすると、住民同士の関係が悪くなってしまうことがあります。
- 地域活動の妨げに:
例えば、町内会で地域の清掃活動をしようとしても、
空き家の敷地だけゴミだらけ、草ぼうぼうでは、がっかりしますよね。
防災訓練をしようにも、危険な空き家が近くにあると心配です。
それに、空き家が増えるということは、
地域活動を担ってくれる人が減る、ということでもあります。
コミュニティ全体の活力が、失われていく原因にもなりかねません。
- 税金の無駄遣い?(行政コストの増大):
地域住民からの苦情や相談が、市役所に寄せられます。
市役所の職員は、その対応に追われます。
空き家の状況を調査したり、所有者を探して連絡したり、
改善するように指導したり、勧告したり…
これらには、当然、人手と時間、つまり税金が使われています。
もし最終的に、行政代執行で家を解体することになれば、
さらに多額の税金が投入されることになります。
(もちろん、その費用は後で所有者に請求されますが、回収できないケースもあります)
—
どうでしょうか。
たった一軒の空き家が、
景観、衛生、安全、防犯、そして地域コミュニティそのものにまで。
これだけ多くの、そして深刻な悪影響を及ぼす可能性があるんです。
あなたの空き家が、地域にとって「困った存在」「問題児」になってしまう前に。
持ち主として、そして地域に住む(あるいは、かつて住んでいた)一員として、
ちゃんと責任ある対応を取ることが、求められているのではないでしょうか。
リスク4:【資産価値の暴落】売るに売れない、貸すに貸せない…「負」動産化への最終章
不動産は、本来なら「資産」のはずですよね。
でも、空き家を放置し続けることは、
その大切な資産の価値を、自らどんどん下げていく行為。
そして最終的には、「負」動産。
つまり、持っているだけで損をする「お荷物」にしてしまうことなんです。
(1) 建物の物理的な劣化が価値を奪う
リスク2で詳しくお話ししたように、
放置された建物は、ものすごいスピードで劣化していきます。
柱や土台が腐る、雨漏りでシミだらけになる、シロアリに食われる、設備が壊れる…
こういうダメージは、建物の市場価値を、ほぼゼロにしてしまいます。
だって、そんな家を買いたい、借りたいと思う人は、なかなかいませんよね?
もし買うとしても、直すのにすごくお金がかかる。
だから、不動産屋さんに見てもらっても、
「建物には値段がつきませんね。土地の値段だけです」
と言われることがほとんど。
もっとひどい場合は、
「土地の値段から、家を壊す費用(解体費)を引いた値段ですね」
なんて言われることもあります。
建物があるせいで、かえって土地の値段が下がってしまう。
建物自体が、マイナスの価値(解体費用という負債)を持つことになるんです。
(2) 市場での「欲しい人」がいなくなる
不動産の値段は、結局、「欲しい」と思う人がどれだけいるかで決まります。
建物がそれほど傷んでいなくても、
今の時代のニーズに合わない物件は、なかなか売れたり貸せたりしません。
- 古い間取りや設備:
昔ながらの和室が多い家、リビングが狭い家。
キッチンやお風呂、トイレが古いまま。
断熱性が低くて、冬寒い家。
こういう家は、今の若い世代などからは、あまり好まれません。
- 不便な立地:
駅から遠い、バスも少ない。
道が狭くて車の出し入れが大変。
坂道や階段が多い。
日当たりが悪い。
近くにスーパーや病院がない。
こういう場所にある物件は、どうしても人気が出にくいです。
苫小牧市内でも、便利なエリアとそうでないエリアがありますよね。
- 「空き家だった」というイメージ:
長い間、誰も住んでいなかった家。
それだけで、「何か問題があるんじゃないか?」
「ちゃんと管理されていなかったんじゃないか?」
そんな風に、マイナスのイメージを持たれやすいんです。
買い手や借り手を見つける上で、不利になることがあります。
「欲しい」と思う人が少ない、ということは。
売ろうとしても、なかなか買い手が見つからない。
何年も売れ残ってしまう。
あるいは、値段をすごく下げないと売れない、ということ。
貸そうとしても、借り手が見つからなくて、ずっと空室のまま。
あるいは、すごく安い家賃じゃないと借りてもらえない、ということなんです。
(3) 周りの環境が悪くなると、自分の家も価値が下がる
リスク3でお話ししたように、
放置された空き家は、周りの環境を悪くします。
もし、あなたの空き家がある地域で、
他にも放置された空き家がたくさんあって、
地域全体の景観や治安が悪くなっていたら?
それは、あなたの空き家だけの問題じゃありません。
そのエリア全体の不動産の価値が、下がってしまうんです。
「あの辺りは、空き家が多くて、ちょっと住みたくないね…」
そんな評判が立ってしまったら、
その地域で家を買いたい、借りたいと思う人は、どんどん減っていきます。
不動産の値段も、下がっていくでしょう。
まさに、負のスパイラルです。
(4) 選択肢がなくなる…「詰んでしまう」状況
資産価値が下がり、市場でも欲しい人がいなくなると。
最終的には、「売ることも、貸すこともできない」
そんな状況に追い込まれてしまいます。
そうなった時に、残された道は…
- ものすごくお金をかけて、家を解体する。
- あるいは、そのまま放置し続けるしかない…(でも、税金とリスクは増え続ける)
そんな、非常に厳しい選択しかなくなってしまうんです。
「いつか、高く売れるかもしれない」
「将来、何かの役に立つかもしれない」
そんな淡い期待は、残念ながら、
放置された空き家においては、ほとんどの場合、叶いません。
むしろ、時間が経てば経つほど、打てる手は少なくなり、
解決は、もっともっと難しくなっていくんです。
空き家を放置することは、
大切な資産を、ただのお荷物にしてしまう。
それどころか、将来の世代に、マイナスの遺産を残してしまう行為なんです。
リスク5:【心理的・関係的負担】終わらない悩み、家族・親族間の亀裂…精神的な重圧
これまでお話ししてきた、お金のこと、建物のこと、地域のこと。
これらに加えて、もう一つ、とても大きなリスクがあります。
それは、目には見えにくいけれど、確実に持ち主を苦しめる、
「心」と「人間関係」への負担です。
(1) 所有者自身の終わらない精神的ストレス
「あの空き家、どうしよう…」
この悩み。空き家を持っている限り、
ずっと、あなたの心のどこかに、重くのしかかり続けます。
- 将来への漠然とした不安:
「この先、いつまで税金を払い続けられるだろうか…」
「もし地震や台風で壊れたら、どうしよう…」
「一体、誰に相談したらいいんだろう…」
解決策が見えないことへの不安感。これは本当に辛いものです。
- 管理へのプレッシャーと自己嫌悪:
「そろそろ、草むしりに行かないと…」
「冬になる前に、水抜きしなきゃ…」
「ご近所から、また何か言われてないだろうか…」
ちゃんと管理しなきゃ、というプレッシャー。
でも、実際にはなかなかできない。
そんな自分に対して、嫌気がさしてしまうこともあります。
- 問題を先送りしている罪悪感:
「本当は、ちゃんと向き合わないといけないのに…」
そう思いながらも、行動に移せない。
そのことへの罪悪感。
あるいは、親が大切にしていた家を、
自分が粗末にしてしまっているんじゃないか、という後ろめたさ。
こういうマイナスの感情は、
普段の生活の中で、じわじわと心を蝕んでいきます。
他のことに集中できなかったり、気分が落ち込んだり。
想像以上に、大きなストレスになっているんです。
(2) 家族・親族間の意見対立と関係悪化
特に、空き家を兄弟姉妹など、複数人で相続した場合。
その管理や、どうするかをめぐって、
深刻な家族・親族トラブルに発展してしまうケースが、後を絶ちません。
僕も、そういう場面をたくさん見てきました。
- 考え方の違いがぶつかる:
「思い出の家だから、壊したくない」という人。
「早く売ってお金に換えたい」という人。
「自分が住みたい」という人。
「人に貸して家賃収入を得たい」という人。
それぞれの立場や、家に対する思い入れ、価値観が違う。
それが、対立を生んでしまうんです。
- お金の負担をめぐる争い:
固定資産税、管理費、修理代…。
こういう費用を、誰が、どうやって負担するのか。
これが、一番揉めやすいポイントかもしれません。
「お前が近くに住んでるんだから、管理も費用も負担しろ」
「いや、相続した割合は同じなんだから、費用も平等に割るべきだ」
そんな、押し付け合いが始まってしまう。
- 責任のなすりつけ合い:
具体的な行動を誰も起こさない。
「結局、誰も何もしないじゃないか!」と不満がたまる。
かといって、誰かが中心になって動こうとすると、
「勝手に話を進めるな!」と反発されたり。
誰も責任を取りたがらない状況に陥りがちです。
- 昔からの確執が再燃:
空き家の問題がきっかけになって、
それまで隠れていた、家族や親戚間の昔からの確執、
不満や不信感が、一気に噴き出してしまうこともあります。
そうなると、問題はもっと複雑に、感情的になってしまいます。
お金の問題だけじゃなく、感情的なしこりが絡み合って。
話し合いは平行線のまま、解決の糸口が見えなくなる。
そして、その結果、
一番大切だったはずの、家族や親戚との関係に、
深い、深い亀裂が入ってしまう。
そんな悲しい結末を迎えてしまうことも、少なくないんです。
空き家問題は、ただの不動産の問題じゃない。
人の心、そして人間関係を壊してしまう力を持っているんです。
(3) 次の世代への「負の遺産」の押し付け
そして、考えてみてください。
もし、あなたがこの問題を解決できないまま、放置してしまったら?
自分が亡くなった後、その空き家と、それにまつわる問題は、
そのまま、あなたの子どもや孫の世代へと引き継がれます。
さらに複雑になったかもしれない権利関係。
もっとボロボロになった建物。
増え続ける維持費や税金の負担。
自分が解決できなかった重荷を、
次の世代に、そのまま背負わせてしまうことになるんです。
これは、将来の世代に対して、
あまりにも無責任なことだとは思いませんか?
—
このように、空き家の放置は、
持ち主自身の心を疲れさせ、
大切な人との関係を壊し、
未来にまで、重い問題を残してしまう。
本当に、深刻な問題なんです。
—
ここまで、空き家を放置し続けることの5つの重大なリスクについて、
詳しくお話ししてきました。
経済的な損失、建物の劣化・崩壊、地域への悪影響、
資産価値の暴落、そして心理的・関係的な負担…。
これらのリスクを総合的に考えると、
「空き家を放置し続ける」という選択肢は、
もはや、あり得ない。
そう、ご理解いただけたのではないでしょうか。
「じゃあ、具体的にどうすればいいの?」
その疑問に答える前に、
次の章では、空き家対策で多くの人がやってしまいがちな、
「失敗パターン」について、さらに詳しく見ていきましょう。
良かれと思ってやったことが、なぜ裏目に出てしまうのか。
その理由を知ることが、成功への近道になります。
一人で悩んでいませんか?
空き家の悩みは、経済的な負担だけでなく、心にも重くのしかかります。家族関係に影響が出ることも…。抱え込まず、まずは藤本に話してみませんか?気持ちが楽になるかもしれません。
「良かれ」が裏目に? 苫小牧の空き家対策で避けたい3つの典型的な失敗とその深層
空き家問題の深刻さが分かって、「よし、何とかしよう!」
そう思って行動を起こすこと。
それは、本当に素晴らしいことです。
でも、ちょっと待ってください。
その行動、本当に正しい方向に進んでいますか?
実は、良かれと思ってやったことが、かえって状況を悪くしてしまったり、
たくさんのお金や時間を無駄にしてしまったり…
そんなケースが、残念ながら少なくないんです。
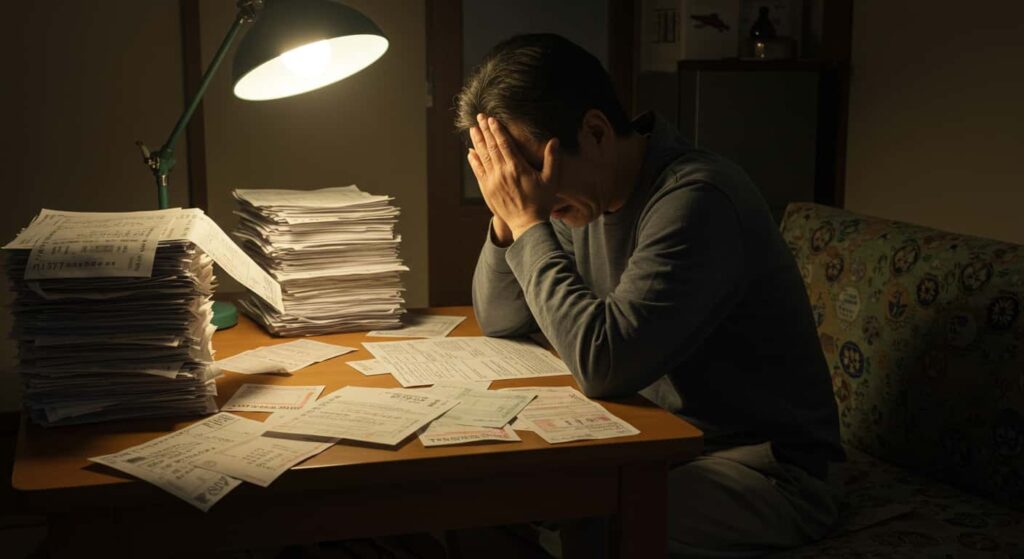
ここでは、僕がこれまでたくさんの空き家のご相談を受ける中で、
「あぁ、これはもったいない…」「こうなる前に相談してほしかった…」
と感じることが多い、典型的な「失敗パターン」を3つご紹介します。
なぜ失敗してしまうのか、その裏にある心理も含めて、少し深く掘り下げてみます。
北海道 苫小牧市で空き家をお持ちのあなたも、
ぜひ、「自分ならどうするだろう?」と考えながら読んでみてください。
同じ失敗を繰り返さないための、大切なヒントになるはずです。
失敗パターン1:「そのうち何とかなる」思考が生む、取り返しのつかない状況悪化

これが、一番多くて、そして一番問題を深刻にしてしまうパターンかもしれません。
「先延ばし」という名の、静かな放置です。
【なぜ先延ばしにしてしまうの? その心理】
- 問題を直視したくない:
空き家のことを考えると、気が重い。
お金もかかりそうだし、手続きも面倒くさそう。
だから、つい目を背けてしまう。
「まだ大丈夫」「きっと何とかなる」と思い込もうとする(正常性バイアス)。
- どうすれば良いか分からない:
具体的な解決策が思いつかない。
誰に相談したらいいのかも分からない。
選択肢がありすぎて選べない、あるいは逆に、打つ手がないように感じてしまう。
それで、結局何もできずに時間が過ぎる。
- 日々の生活で手一杯:
仕事が忙しい、子育てや介護がある、自分の健康が心配…
目の前のことで精一杯で、空き家のことまで考える余裕がない。
どうしても、優先順位が下がってしまう。
- 相続人同士で話がまとまらない:
兄弟姉妹で共有名義になっている場合。
他の人が協力してくれない、意見が合わない。
自分だけではどうしようもない、と感じて諦めてしまう。
- 損をしたくない、タイミングを計りすぎる:
「今売っても、安いだろうな…」
「解体費用、もったいないな…」
もっと良いタイミングがあるはず、と考えているうちに、
どんどん状況が悪化してしまう。
【放置が招く、悲劇のシナリオ】
この「先延ばし」が、最終的にどんな結末を迎えるか。
それは、先ほどお話ししたリスクが、順番に現実になっていくプロセスです。
- 初期段階:
固定資産税の通知が毎年届く。
「またか…」と思いながらも支払う。
たまに様子を見に行くと、庭に雑草が生え、家が少し古びてきたな、と感じる。
でも、「まだ住める状態だ」「問題ない」と自分に言い聞かせる。
- 中期段階:
雨漏りのシミを天井に見つける。
押し入れがカビ臭い。
ネズミがいる気配がする。
近所の人から「庭の草、どうにかなりませんか?」とやんわり言われる。
税金に加えて、ちょっとした修理代や、草刈りを頼む費用がかかり始める。
- 後期段階:
家の傷みが、外から見ても明らかになる。
外壁にヒビが入ったり、剥がれ落ちたり。
窓ガラスが割れたり、雨戸が壊れたり。
庭は雑草だらけで、ゴミが捨てられるようになる。
近隣からの苦情が直接的になり、市役所からも連絡が来る。
「特定空家」になる可能性がありますよ、という指導。
いざ、専門家に見てもらうと、シロアリ被害が深刻で、
修理には数百万円かかると言われる。
- 末期段階:
ついに「特定空家」に指定され、固定資産税が数倍に跳ね上がる。
市役所から「このままでは命令を出しますよ」と通告される。
最終的には行政代執行で強制的に解体され、
その費用(数百万円)を請求される可能性も出てくる。
売ろうとしても、誰も買ってくれない。
もう、解体する以外の道はない。
でも、その費用を用意できない…。完全に手詰まり状態。
「そのうち何とかなる」
その甘い考えが、時間とともに選択肢を奪い、
最終的には、お金の面でも、心の面でも、
取り返しのつかない状況を招いてしまうんです。
問題が小さいうちに、早く手を打つこと。
それが、どれだけ大事か。
この失敗パターンが、痛いほど教えてくれます。
失敗パターン2:「見た目重視」の高額リフォーム投資が招く、回収不能な負債
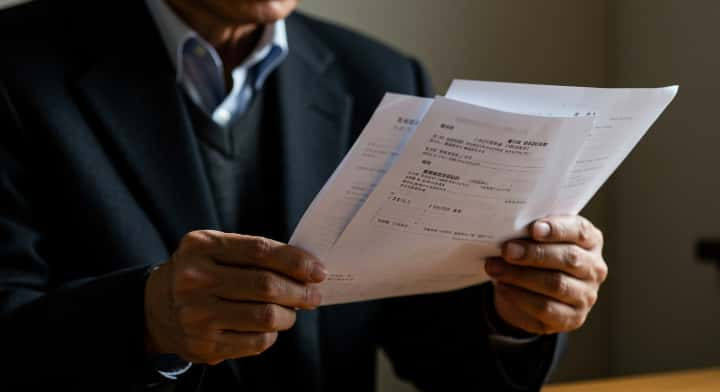
「このままじゃ売れないし、貸せない」
「まずは綺麗にしなくちゃ!」
そう考えて、リフォームやリノベーションにお金をかける。
一見、前向きで、正しい行動のように思えますよね?
でも、これが大きな落とし穴になることがあるんです。
【なぜ高額リフォームに走ってしまうの? その心理】
- 「綺麗=価値が上がる」という期待:
古くて汚い状態より、新しくて綺麗な方が高く売れる、高く貸せるはず。
そう信じて、「価値を高めるため」にリフォームしようと考える。
特に、思い出のある実家だと、「綺麗にしてあげたい」という気持ちが強くなることも。
- 専門家(業者)の言うことを信じすぎる:
リフォーム業者さんに相談すると、
「ここも古いから直した方がいいですよ」
「どうせなら、最新のキッチンに入れ替えませんか?」
色々な提案を受けます。
断りにくかったり、「プロが言うなら間違いないだろう」と思ってしまったり。
でも、業者は商売ですから、より高い工事を勧めたい、という側面もあります。
- 費用対効果を考えない:
リフォームにいくらかけて、それが売却価格や家賃収入にどれだけ上乗せできるのか?
その冷静な計算が、意外とできていないことが多いんです。
その地域で、その家がいくらで売れそうか、いくらで貸せそうか。
その相場を知らないまま、お金をかけてしまう。
- 「投資」と「浪費」を勘違い:
リフォームは「未来への投資」だと思いがち。
でも、市場のニーズに合わない、やりすぎのリフォームは、
ただお金を使っただけ、「浪費」になってしまう危険があるんです。
かけたお金が、全く回収できないかもしれない。
そのリスクを、ちゃんと考えていない。
- ローンが使えるから、と安易に考える:
リフォーム費用が高くても、「ローンを組めば払える」と思ってしまう。
でも、ローンは借金です。
将来、家が売れなかったり、家賃収入がなかったりしたら、
どうやって返していくのか?
その計画がないと、大変なことになります。
【高額リフォーム投資の悲しい結末】
では、意気込んでお金をかけたリフォームが、なぜ失敗に終わることが多いんでしょうか。
- 思ったより費用がかさむ:
見積もりでは予算内だったのに、いざ工事を始めたら、
壁を剥がしたら柱が腐っていた、床をめくったらシロアリ被害が…
そんな風に、隠れていた問題が次々に見つかって、追加工事が必要になる。
結局、最初の予定よりずっと高い金額を請求されてしまう。
これは、古い家のリフォームでは本当によくあることです。
- かけた費用ほど高くは売れない:
例えば、相場が1000万円のエリアで、500万円かけて家をリフォームしたとします。
じゃあ、1500万円で売れるかというと、まず売れません。
買い手は、あくまで周りの家の値段と比べて判断します。
「リフォームにお金がかかったから高く売る」は、通用しないんです。
結局、相場に近い値段まで下げないと売れず、リフォーム費用分は丸々赤字、なんてことも。
- 家賃収入で回収できない:
最新の設備を入れて、すごくオシャレにリフォームしたとします。
でも、その地域の家賃相場や、借り手が求めているもの(広さ、間取り、駐車場の有無など)と合っていなければ?
高い家賃を設定したら、誰も借りてくれません。
苫小牧市内で、高い家賃を出してでも、わざわざ古い一戸建てを借りたい、という人がどれだけいるか?
冷静に考える必要があります。
結果、ずっと空室のまま、ローン返済だけが続く…という最悪の事態も。
- お金だけが出ていく状況に:
結局、「売ろうにも売れない(売れても大赤字)」
「貸そうにも借り手がつかない」
という状況になってしまう。
かけたリフォーム費用は戻ってこず、ローンだけが残る。
そして、固定資産税は払い続けなければならない。
まさに、踏んだり蹴ったりです。
- 大きな後悔と精神的ダメージ:
大金を投じたのに、全く報われない。
この結果は、お金の損失以上に、大きな後悔と精神的なダメージをもたらします。
「あの時、リフォームなんてしなければ良かった…」
そう思っても、もう遅いんです。
もちろん、リフォームがうまくいくケースもあります。
でもそれは、ちゃんと地域の市場を調べて、
どれくらいお金をかけたら、どれくらいのリターンが見込めるか、
しっかり計算した上での、賢いリフォームだけです。
「とりあえず綺麗にすれば何とかなるだろう」
そんな安易な考えで、高額なリフォームに手を出してしまうのは、
非常にリスクが高い。
そう覚えておいてください。
僕、藤本は、「お金をかけない」ことを大切にしています。
だから、こういうケースを見ると、本当にもったいないな、と感じてしまうんです。
失敗パターン3:「補助金頼み」で計画が頓挫、あるいは自己負担増に苦しむ
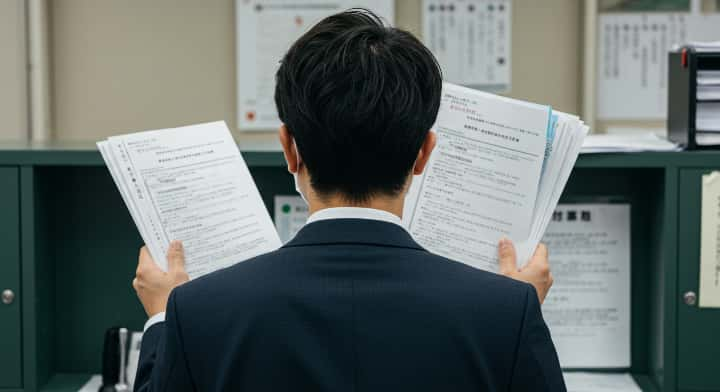
空き家の解体やリフォームには、お金がかかります。
そこで、「市の補助金が使えるらしい!」という情報を聞くと、
「それなら、費用負担が軽くなる!」と期待しますよね。
国や自治体(北海道や苫小牧市)が、空き家対策のために、
補助金制度を用意していることは、確かにあります。
でも、この「補助金頼み」で計画を進めることにも、
注意しないといけない落とし穴があるんです。
【なぜ補助金頼みは危険なの? その心理】
- 「タダ同然」という甘い期待:
「補助金が出る」と聞くと、
まるで工事費用がタダになるかのように誤解してしまう。
補助金は、あくまで「かかった費用の一部を補助する」もの。
ほとんどの場合、自己負担が発生するという認識が薄いんです。
- 制度内容をよく知らない:
補助金の名前や、大まかな内容だけを聞いて、
「自分の家も対象になるはずだ」と思い込んでしまう。
でも、実際には、対象になる家の条件(築年数、場所、状態など)、
持ち主の収入、リフォーム後の使い方など、
すごく細かいルール(要件)が決まっていることが多いんです。
その詳細を確認しないまま、話を進めてしまう。
- 業者さんの話を鵜呑みにする:
解体業者さんやリフォーム業者さんから、
「この工事なら、補助金が使えますよ」と言われる。
申請手続きも「うちでやりますよ」と言われて、任せてしまう。
でも、業者さんが最新の情報を正確に知っているとは限りません。
もし申請が通らなかった場合のリスクについて、
ちゃんと説明してくれない可能性だってあります。
- 予算があることを信じすぎる:
補助金は、税金から出ています。
だから、使える金額(予算)には限りがあります。
申請する人がたくさんいたら、抽選になったり、
年度の途中で「予算がなくなったので、もう受付終了です」
なんてことも普通にあります。
その可能性を、あまり考えていない。
- 手続きの手間を甘く見る:
補助金の申請って、意外と大変なんです。
申請書以外にも、家の図面、工事の見積書、登記簿謄本、
税金の納税証明書など、色々な書類を集めないといけません。
手続きも複雑で、時間がかかることが多い。
その手間を、軽く考えてしまっている。
【補助金頼みが招く、残念な結末】
補助金を当てにして計画を進めた結果、どうなってしまうことが多いのか。
- 申請したけど、ダメだった:
いざ申請書類を出してみたら、
「この家の条件(例:耐震基準を満たしていない、対象エリア外など)では対象外です」
「あなたの収入では、所得制限を超えています」
「リフォームの目的(例:賃貸にする)が、補助金の趣旨と合いません」
そんな理由で、申請が通らない、あるいは審査で落とされてしまう。
補助金がゼロ円になってしまう。
- 間に合わなかった…(期間・予算切れ):
書類を集めるのに手間取っているうちに、申請の締め切りが過ぎてしまった。
あるいは、申請が殺到して、市の予算がなくなってしまい、
受付が打ち切られてしまった。
- 思ったより自己負担が多い!:
補助金は、かかった費用の全部が出るわけではありません。
例えば、「費用の半分、上限50万円」という補助金だとします。
解体費用が200万円かかったら、補助金は上限の50万円。
残りの150万円は、自分で払わないといけません。
この自己負担額をちゃんと用意できていないと、
結局、工事ができない、ということになってしまいます。
- 手続きが面倒で、諦めてしまう:
集めないといけない書類の多さ、手続きの複雑さに、
途中で「もう、やってられない!」と諦めてしまう。
特に、相続登記が終わっていなかったり、
共有名義で他の兄弟の協力が得られなかったりすると、
申請すること自体が、ものすごく難しくなります。
- すぐにはお金がもらえない(立て替え払い):
補助金って、工事が終わって、市役所の検査などを受けた後に、
やっと支払われることが多いんです。
ということは、工事の費用は、一旦、全額自分で支払う(立て替える)必要がある。
その間の資金繰りが大変、ということもあります。
補助金制度は、うまく使えれば確かに助かります。
でも、「必ずもらえるもの」ではないし、「それだけで全て解決するもの」でもない。
それを前提にして計画を立てるのは、かなり危ういんです。
補助金ありきで考えるのではなく、
まずは、補助金がなくてもできる範囲で、どうするのが一番良いか考える。
そして、補助金は「もし使えたらラッキー」くらいの気持ちでいる。
それが、現実的で、安全な考え方だと、僕は思います。
(苫小牧市で使えるかもしれない補助金については、後の章でもう少し触れますね。でも、最新情報は必ずご自身で確認してくださいね!)
—
以上、空き家対策でよくある、3つの失敗パターンについてお話ししました。
「先延ばし」「高額リフォーム」「補助金頼み」。
これらの失敗は、情報が足りなかったり、思い込みがあったり、
あるいは、問題を先送りにしてしまう心から生まれることが多いようです。
では、どうすれば、こういう失敗をしないで、
もっと賢く、そして負担なく、空き家問題を解決できるんでしょうか?
次の章では、まず、世間一般で考えられている空き家の解決策、
「売却」「賃貸」「解体」について。
その良い点、悪い点、そして現実的な側面を、
もう一度、客観的に、そして詳しく整理してみましょう。
それぞれの選択肢の本当のところを知ることが、
あなたにとって一番良い道を見つけるための、大切な基礎になります。
【選択肢の徹底比較】空き家問題、一般的な解決策「売却」「賃貸」「解体」の現実と限界
空き家を「どうにかしたい」と思ったとき。
多くの人が、まず頭に思い浮かべるのは、
たぶん、この3つの方法じゃないでしょうか。
- 家や土地を「売る」(売却)
- 誰かに「貸す」(賃貸)
- 家を「壊す」(解体)
これらは、昔からある、いわば空き家対策の「王道」です。
でも、それぞれの方法には、良い面もあれば、難しい面もあります。
メリットだけじゃなく、デメリット。
実際にやろうとした時の、現実的な難しさ。
そして、注意しないといけない点。
これらをちゃんと理解しておくことが、
後で「こんなはずじゃなかった…」と後悔しないために、すごく大切です。
ここでは、北海道 苫小牧市の不動産市場の状況なんかも考えながら、
これら3つの一般的な解決策について、
その本当のところを、客観的に、そして詳しく比較していきましょう。
解決策1:【売却】手放して現金化、悩みから解放される… は本当か?

空き家とその土地を、他の人に売り渡す方法です。
一番スッキリして、問題から完全に手を引ける。
そんなイメージがありますよね。
【売却で期待できること(メリット)】
- まとまったお金が手に入る:
売れれば、現金収入になります。
ローンの返済や、他の支払いに充てられますね。
相続した家なら、兄弟姉妹で分けるときも、現金なら分けやすいです。
- 管理の手間・費用から解放される:
売ってしまえば、もう自分のものじゃありません。
草むしりや雪下ろしといった面倒な管理。
毎年の固定資産税の支払い。
将来、修理にお金がかかるかも、という心配。
そういう、空き家に関する全ての負担から解放されます。
- 心の重荷がなくなる:
「あの空き家、どうしよう…」
長年抱えてきたその悩みから解放されて、気持ちが楽になります。
特に、遠くに住んでいる方にとっては、大きな安心材料になるでしょう。
【でも、現実は甘くない?(デメリット・課題)】
- そもそも「売れない」かもしれない:
これが一番大きな問題です。
特に、次のような家は、買い手を見つけるのが本当に難しい。
- 築年数が古い家:木造だと築20~25年で価値がほぼゼロと言われます。それ以上古いと…。
- 状態が悪い家:雨漏り、シロアリ、傾き、設備がボロボロ… 修理にお金がかかる家は敬遠されます。
- 場所が良くない家:駅から遠い、道が狭い、日当たりが悪い、周りに嫌な施設がある… 需要が低いです。苫小牧市内でも場所によりますよね。
- 再建築できない家:今の法律では家を建て替えられない土地。利用価値が低いので、売るのは非常に困難です。
- 希望の値段では売れない:
もし売れたとしても、自分が思っていた値段より、ずっと安くなってしまうかも。
不動産屋さんは、周りの似たような家がいくらで売れたか、を参考に値段をつけます。
状態が悪い空き家だと、「土地の値段だけ」とか、
「土地の値段から家を壊す費用を引いた値段」になってしまうことも覚悟が必要です。
- 売るためにお金がかかる(諸費用):
売れても、そのお金が全部手元に残るわけじゃありません。
色々な費用が引かれます。
- 仲介手数料:不動産屋さんに頼んだ場合。売れた値段に応じて結構な額(例:1000万円で売れたら約40万円弱)がかかります。
- 印紙税:契約書に貼る印紙代。
- 登記費用:家のローンが残っていたら消す登記とか、司法書士さんへの報酬とか。
- 税金:売って利益が出たら、所得税・住民税がかかることも。(特例もありますが、要確認)
- その他:土地の境界をはっきりさせる測量費、家の中の物を捨てる費用、家を壊す費用(更地で売る場合)など。
- 売る前の準備が大変:
少しでも印象を良くするために、掃除したり、片付けたり、庭の手入れをしたり。
不動産屋さんとの打ち合わせや、見に来た人への対応も必要です。
- 売った後も安心できない?(契約不適合責任):
これが結構怖いんです。
売った後に、買主が、契約の時には知らなかった重大な欠陥(雨漏り、シロアリ、柱の腐食など)を見つけたとします。
そしたら、買主は売主に対して、「修理代を払え」「値段を下げろ」「契約を解除する」「損害賠償しろ」って言えるんです。
個人同士の売買でも、普通は引き渡しから一定期間(例:3ヶ月とか)はこの責任から逃れられません。
古い空き家は、持ち主も気づいていない欠陥が隠れている可能性が高いので、特に注意が必要です。
「現状のまま売ります」と契約書に書いても、この責任が完全になくなるわけではありません。
【苫小牧市での売却を考えるなら】
苫小牧市は広い街です。
不動産の需要も、場所によって全然違います。
比較的新しい住宅地や、便利な場所なら、適正な値段なら売れるかもしれません。
でも、古い家、駅から遠い家、管理されていない家は、
売るのに時間がかかったり、すごく安くしないと売れなかったり。
最終的に、不動産買取業者に安く買い叩かれるしかない、なんてこともよくあります。
特に、再建築できない家や、大規模な修理が必要な家は、普通の買い手を見つけるのは、ほぼ不可能に近いでしょう。
もし売却を考えるなら、まず複数の不動産屋さんに相談してみること。
「本当に売れるのか?」「いくらくらいで売れそうか?」
「どんな費用やリスクがあるのか?」
その辺りを、ちゃんと確認することが大切です。
「きっと売れるはず」という甘い考えだけで動き出すと、時間とお金を無駄にしてしまうかもしれません。
解決策2:【賃貸】家賃収入で不労所得? その高いハードルと見過ごせないリスク

空き家を誰かに貸して、毎月家賃をもらう方法です。
「家賃収入で固定資産税を払って、お小遣いにもなるかも…」
そんな風に考えると、魅力的に見えますよね。
【賃貸で期待できること(メリット)】
- 毎月の収入になる:
借り手が見つかれば、安定した家賃収入が期待できます。
固定資産税などの維持費を、それで賄えるかもしれません。
- 家を持ち続けられる:
すぐに売ったり壊したりしないで、資産として持っておけます。
将来、インフレになったら価値が上がるかも?(期待しすぎは禁物ですが)
「いつか自分で住むかも」「別の使い道が見つかるかも」という可能性を残せます。
- 家の傷みを防げる:
人が住むと、窓を開けたり閉めたり、換気されます。
設備の不具合にも気づきやすい。
結果的に、家が傷むのを遅らせる効果があります。
- 地域のためになる(かも):
空き家が使われることで、地域の景観が保たれたり、防犯面で安心になったり。
間接的にですが、地域に貢献できる面もあります。
【でも、大家業は大変?(デメリット・課題)】
賃貸経営。「不労所得」なんて言われることもありますが、とんでもない!
実際には、たくさんのハードルとリスクがあります。
- 最初にお金がかかる(リフォーム費用):
これが一番の壁かもしれません。
人に貸すには、最低限、安全で気持ちよく住める状態にしないといけません。
古い空き家だと、だいたい次のようなリフォームが必要になります。
- キッチン、お風呂、トイレなどの水回り交換
- 給湯器の交換
- 壁紙や床の張り替え
- 雨漏りや傷んだ部分の修理
- 家の中の掃除、残った物の処分
- 場合によっては、断熱改修、耐震補強、バリアフリー化など
これらにかかる費用、安くても数十万円。
普通は、数百万円単位になることが多いです。
もしローンを組んだら、それは「借金」です。
- 借り手が見つからない(空室リスク):
お金をかけてリフォームしても、必ず借り手が見つかる保証はありません。
募集しても全然反応がない…
見に来てくれても契約にならない…
そんな可能性は十分にあります。
空室の間は、家賃収入はもちろんゼロ。
でも、ローン返済(もしあれば)、固定資産税、管理費、保険料などは払い続けなければなりません。
空室が長引くと、リフォーム代も回収できず、赤字が膨らむばかりです。
- 家賃を払ってもらえない(滞納リスク):
入居者がいても、家賃をちゃんと払ってくれない。
そういうリスクもあります。
催促しても払ってくれない場合は、法的な手続きが必要になることも。
これも時間とお金、そして精神的な負担がかかります。
(家賃保証会社を使えばリスクは減りますが、費用がかかります)
- 入居者とのトラブル:
大家業には、色々なトラブルがつきものです。
- 騒音(うるさい!)
- ゴミ出しルール違反
- ペット問題(禁止なのに飼っている、うるさい、臭い)
- 近所の人との揉め事
- 部屋を壊された、汚された
こういうことが起きたら、大家さんが対応しないといけません。
話を聞いたり、注意したり、間に入ったり…。結構大変です。
- 管理がとにかく面倒(手間・コスト):
大家さんの仕事って、実はたくさんあります。
- 入居者募集(広告出す、不動産屋に頼む)
- 部屋を見せる(内覧対応)
- 入居審査、契約手続き
- 毎月の家賃チェック、催促
- クレーム対応
- 家の点検、修理の手配
- 退去時の立ち会い、部屋のチェック、敷金精算
これを全部自分でやるのは、かなり大変。
不動産管理会社に頼むこともできますが、管理手数料(家賃の5%くらい)がかかります。
- 修理代がかかる:
貸している間に、給湯器が壊れた、エアコンが動かない、水漏れした…。
こういう、古くなって壊れたものの修理代は、基本的には大家さん負担です。
突然の出費に備えておく必要があります。
- 法律上の責任がある:
大家さんには、法律(借地借家法など)で色々な責任や義務が定められています。
例えば、入居者が安全に暮らせるように配慮する義務があります。
もし家の欠陥が原因で入居者が怪我をしたら、責任を問われる可能性も。
【苫小牧市での賃貸を考えるなら】
苫小牧市で、古い一戸建てを貸す場合、どんな人に需要があるでしょうか?
新しいアパートやマンションもたくさんありますから、競争は激しいです。
単身者向け? ファミリー向け? 企業の社宅?
家賃はいくらくらいが妥当?
駅からの距離は? 周りの環境は?
そういうことを、しっかり調べる必要があります。
高額なリフォームをして高い家賃を設定しても、借り手がつかなければ意味がありません。
もしかしたら、「DIYし放題」「ペットOK」「とにかく家賃が安い」
そんな風に、何か特徴をつけないと、借り手は見つからないかもしれません。
賃貸経営を始める前に、地域の不動産屋さんに相談して、
現実的な見通しを立てることが、絶対に必要です。
「なんとなく儲かりそう」というだけで始めると、痛い目を見ますよ。
賃貸は、うまくいけば収入になります。
でも、それには多額の初期投資と、色々なリスクへの覚悟、
そして、面倒な管理業務をこなす手間と時間が必要です。
「不労所得」どころか、一つの「事業」を始めるくらいの覚悟がいるんです。
解決策3:【解体】更地にしてリセット? しかし費用負担と税金増の重い現実

もう古すぎて、売ることも貸すことも、どう考えても無理。
そんな場合に、最後の手段として考えられるのが、
建物を壊して、更地(さらち=何もない土地)にしてしまう方法です。
【解体で期待できること(メリット)】
- 建物の管理から解放される:
家が無くなれば、もう「壊れるかも」「雨漏りしたらどうしよう」
そんな心配は一切なくなります。
倒壊して誰かに被害を与えるリスクも、もちろんゼロに。
草むしりなどの管理の手間も、ずっと楽になります(土地の管理は残りますが)。
- 「特定空家」のリスク消滅:
建物がなければ、特定空家に指定されることはありません。
固定資産税が6倍になるかも、という心配から解放されます。
- 土地が使いやすくなる(かも):
更地の方が、駐車場にしたり、資材置き場にしたり、家庭菜園にしたり。
色々な使い方が考えやすくなります。
売る場合も、古い家付きより更地の方が買い手がつきやすい、ということもあります。
(ただし、土地の形や場所によります)
- 気持ちの整理がつく:
長年の悩みの種だった空き家が、物理的になくなる。
それで、気持ちに区切りがついて、スッキリするという方もいます。
【でも、解体には大きな代償が…(デメリット・課題)】
家を壊せばスッキリするかもしれませんが、
その代わりに、非常に大きな費用負担と、新たな税金の問題が出てきます。
- ものすごくお金がかかる(解体費用):
これが最大の壁です。
普通の大きさの木造の家(30坪くらい)でも、
解体費用は、100万円~300万円くらいかかるのが普通です。
でも、これはあくまで目安。
- 家の大きさ、構造(鉄骨とかコンクリだと高い)
- 場所(道が狭くて重機が入れない、隣と近いとか)
- アスベスト(石綿)が使われているか(使われていると除去費用が数十万~百万円以上追加!)
- 地中から何か(昔の基礎とか)出てきたら、その撤去費用
- 庭のブロック塀や庭石、木の撤去費用
こういう条件で、費用はもっともっと高くなる可能性があります。
苫小牧市だと、冬は雪で作業しにくいので、冬に頼むと割高になるかも。
業者さんによっても値段が全然違うので、必ず複数の業者さんから見積もりを取ることが大切です。
- 税金が高くなる!(固定資産税・都市計画税の増額):
これも、すごく大事なポイントです。
家が建っている土地は、「住宅用地の特例」で税金が安くなっていますよね(最大6分の1)。
でも、家を壊して更地にしてしまうと、この特例が使えなくなります。
その結果、家を壊した次の年から、土地にかかる固定資産税・都市計画税が、
今までの3倍~6倍くらいに、大幅に上がってしまうことがほとんどなんです!
家の分の税金は無くなりますが、土地の税金がそれ以上に上がることが多い。
だから、トータルで払う税金は、むしろ増えてしまう可能性が高いんです。
これは、本当に大きな落とし穴です。
- 更地にした後、どうするか?:
高いお金を払って更地にしても、その土地をどうするのか?
駐車場にして貸すとか、太陽光パネルを置くとか、売るとか。
そういう活用方法や、売れる見込みがないと、
ただただ高い固定資産税を払い続けるだけの、
もっと困った「負」動産になってしまいます。
家を壊す前に、「その後、この土地をどうするのか?」を具体的に考えておくことが、絶対に必要です。
- 思い出が消えてしまう:
お金の問題だけじゃありません。
生まれ育った家、家族との思い出がたくさん詰まった家。
それを壊してしまうことに、強い抵抗や寂しさを感じる方もいます。
この気持ちの面も、解体を決める上での大きなハードルになります。
- ご近所への配慮:
解体工事は、どうしても騒音や振動、ホコリが出ます。
近所の人たちには、迷惑をかけることになります。
工事を始める前に、ちゃんと挨拶に行って、
工事期間などを説明して、理解してもらうことが大切です。
トラブルにならないように、気を配る必要があります。
【苫小牧市での解体を考えるなら】
苫小牧市内でも、古くて危険な空き家は、地域の安全のために解体した方が良い、というケースはたくさんあります。
市が解体費用の一部を補助してくれる制度があるかもしれません(要確認!)。
でも、補助金が使えたとしても、自己負担額はやっぱり高額になることが多いです。
そして、一番大事なのは、「壊した後の土地をどうするか?」という出口戦略。
苫小牧市内の土地の需要も、場所によって全然違います。
更地にしたからといって、すぐに売れたり、うまく活用できたりするとは限りません。
特に、あまり便利じゃない場所の土地だと、
解体費用と、これから毎年かかる高い固定資産税を考えると、
「本当に壊すのが一番良い選択なのか?」と慎重に考える必要があります。
解体を考えるなら、まず解体費用がいくらかかるか正確に見積もりを取る。
補助金が使えるか確認する。
そして、壊した後の土地が売れそうか、活用できそうか、税金はいくらになるのか。
これらを全部考え合わせた上で、判断することが絶対に必要です。
解体は、物理的に家を無くす最後の手段。
でも、高いお金と、新たな税負担という重い代償が伴う可能性があります。
「壊せば終わり」と安易に考えず、メリットとデメリットをしっかり比べてください。
—
ここまで、空き家問題の一般的な3つの解決策、「売却」「賃貸」「解体」について。
その良い点、悪い点、そして現実的な課題を詳しく見てきました。
お分かりいただけたと思いますが、どの方法にも、良い面と難しい面があります。
そして、共通して言えるのは、
「費用」と「手間」、そして「不確実性(リスク)」が、
大きな壁として立ちはだかることが多い、ということです。
「結局、どの道を選んでも、お金もかかるし、面倒だし、うまくいくか分からないじゃないか…」
そんな風に、がっかりしてしまった方もいるかもしれません。
でも、ここで諦めないでください。
実は、これらの一般的な方法とは、まったく違う考え方で、
「お金と手間をかけずに、空き家を負担から解放し、新しい価値を生み出す」
そんなアプローチがあるんです。
それが、僕、藤本が提案する、空き家解決の具体的な方法です。
次章で、いよいよその核心に迫ります。
【比較表】空き家相談、誰に頼るのが正解? 主要相談先と藤本への相談の違い【詳細版】
空き家の悩みを抱えたとき、色々な専門家や機関が相談相手として考えられますね。でも、それぞれ得意なことや限界、費用も違います。どこに相談するのがベストか、考えるヒントとして主な相談先と、私、藤本に相談した場合の違いを表にまとめました。
| 相談先 | ①主な役割・強み | ②限界・弱み・注意点 | ③【藤本に依頼した場合】 |
|---|---|---|---|
| 不動産仲介業者 (大手・地元の不動産屋さん) | ・売買/賃貸の査定 ・買主/借主探し ・契約サポート | ・成約保証なし ・仲介手数料 高 ・現状渡し基本 ・担当者で差も | 負担ゼロ活用提案 可 仲介(買主探し)せず |
| 賃貸管理会社 (不動産屋さん兼業も) | ・入居者募集/管理 ・家賃回収/督促 ・クレーム対応 ・建物管理/修繕手配 | ・管理手数料 要 ・高額リフォーム推奨も ・空室リスクは自己負担 ・大規模トラブルは別 | 最低限修繕 藤本負担(※) 空室リスク考慮活用(※) 管理の手間なし |
| 不動産買取業者 (再販・リフォーム会社) | ・すぐ現金化 ・仲介手数料なし ・現状買取の場合あり ・責任免除が多い | ・買取価格安い ・業者選定 要注意 ・活用というより処分 | まず活用を最優先 引取りも負担軽減第一 |
| 解体業者 | ・家を壊す専門 ・アスベスト除去 ・整地作業 | ・解体費用 高額 ・解体後の土地ノータッチ ・税金増リスク説明不足も ・業者選定 要注意 | まず活用を検討 解体でも「半額負担引取り」提案可 |
| 建築士・設計事務所・リフォーム会社 | ・家の状態診断 ・リフォーム設計 ・工事監理 | ・費用 高くなりがち ・費用対効果 度外視も ・市場ニーズとズレも ・相談/設計料 要 | 市場・費用対効果重視 最低限リフォーム 藤本負担可 専門家と連携 |
| NPO法人・空き家相談窓口・コンサルタント | ・情報提供/セミナー ・中立アドバイス ・活用プラン提案 ・専門家紹介 | ・実行力に限界 ・相談/コンサル料 要も ・紹介先 限定的かも ・解決は別途依頼 | 相談 完全無料 提案~実行ワンストップ可 しがらみなし提案 |
| 自治体(苫小牧市役所など) | ・相談窓口あり ・空き家バンク運営? ・補助金情報/受付 ・特定空家対応 | ・個別活用提案 限定的 ・民間サービスせず ・補助金 要件/予算あり ・空家対応は最終手段 | 自治体制度も視野 民間の柔軟な解決策 |
※ 藤本が負担する修繕範囲には限度があります(例:給湯器交換、雨漏り応急処置等)。大規模リフォームは行いません。詳細はご相談ください。
※ 藤本の管理代行は家賃保証付きのサブリースではありません。空室時の家賃支払いはありません。
この表を見ると、それぞれの専門家には、できること・できないこと、得意なこと・苦手なことがあるのが分かりますね。
そして、多くの場合、具体的に解決に向けて動こうとすると、「費用」がかかってきます。
それに対して、僕、藤本のやり方の大きな違いは、
- 相談は何度でも、完全に無料です。
- 「お金をかけない、手間をかけない」。持ち主の方の負担をできるだけ無くすことを一番に考えます。
- 一般的な方法とは違う、独自の活用のノウハウを持っています。
- 必要なら、提案から実行まで、できる限りお手伝いします。(僕だけでできないことは、信頼できる仲間と協力します)
そこが、他の選択肢とは違う点だと考えています。
もちろん、僕が全てを解決できるわけではありません。
でも、あなたが一般的な方法でお金をたくさん使ったり、面倒な手続きで悩んだりする前に。
一度、僕の話を聞いてみる価値はあると思いませんか?
次の章では、いよいよ、僕、藤本が具体的にどんな方法で、
あなたの空き家問題を「負担ゼロ」で解決できる可能性があるのか。
その核心の部分を、詳しくお話しします。
【藤本提案】お金をかけずに苫小牧の空き家を「お荷物」から「可能性」へ変える3つの方法
さて、お待たせしました。
ここからは、僕、藤本が自信を持って提案する、
空き家問題の具体的な解決策についてお話しします。
これまでの話で、
空き家を放置するリスクがいかに大きいか。
そして、一般的な解決策(売却・賃貸・解体)には、
費用や手間、そしてリスクが伴うこと。
それが、よくお分かりいただけたかと思います。
「じゃあ、どうすれば…」
「お金もかけられないし、面倒なことも無理…」
そんなあなたのための提案です。
目指すのは、「お金と手間を最小限に抑えて、空き家という負担から解放される」こと。
これは、普通の不動産屋さんやリフォーム屋さんとは、
ちょっと違う考え方かもしれません。
なぜなら、僕の目的は、
単にお金を儲けることじゃないんです。
「空き家問題を解決すること」
「持ち主の方の負担をなくすこと」
「使われなくなった家を、次へと繋いでいくこと」
それ自体が、僕の活動の目的なんです。
もちろん、僕も活動を続けるためには収益が必要です。
でも、その収益は、
「持ち主の方に負担をかけずに、空き家を活用することで生み出す」
これを基本にしています。
「そんなうまい話、あるわけない」
そう思う気持ちも、よく分かります。
でも、これは僕が日々、全国で実践している方法なんです。
そして、僕には強力なパートナーがいます。
全国で100軒以上の空き家を実際に扱い、テレビなどにも出ている
「日本の空き家研究所」代表の竹田さんです。
竹田さんの豊富な経験や知識、全国の成功事例も参考にしながら、
最適な方法を考えています。
一件でも多くの空き家を救いたい。
持ち主の方の悩みを、少しでも軽くしたい。
そんな想いで、僕自身が汗をかき、頭を使って考え出した、
これが僕の提案です。
あなたの北海道 苫小牧市の空き家にも、
きっと、この方法が使える道があるはずです。
僕がご相談を受けるときに、いつも大切にしていることがあります。
- まず、あなたの話をじっくり聞きます:どんな状況で、何に困っていて、どうしたいのか。あなたの気持ちを理解することから始めます。
- 現地現物(可能な範囲で):机の上だけで考えません。写真やオンライン、必要なら実際に苫小牧の物件を見に行きます。(※遠方の場合は交通費等相談させてください)
- 「お金をかけない」が第一:いきなり「壊しましょう」「リフォームしましょう」とは言いません。まず費用ゼロでできることはないか、あらゆる可能性を探ります。
- 良いことも悪いことも正直に:提案するメリットだけでなく、デメリットやリスクも隠さずお伝えします。
- 安易な丸投げはしない:法律の手続きなどで専門家が必要な場合もありますが、その前に僕自身がやれることは全部やります。費用を抑える工夫をします。
- 相談は何度でも無料:あなたが納得できるまで、何度でもご相談ください。お金は一切いただきません。
一緒に、あなたと、あなたの空き家にとって、一番良い方法を見つけましょう!
では、具体的な3つの提案を、一つずつ見ていきましょう。
提案①:「管理代行」による収益化 ~現状のまま貸し出して、手間なく固定資産税以上の収入を目指す~

「人に貸したいけど、リフォームするお金がない…」
「大家さんなんて、面倒なことは絶対できない…」
そんなあなたに、まず考えてみてほしいのが、この「管理代行」です。
これは、普通のアパート経営とかとは違います。
持ち主であるあなたの費用負担と手間を、限りなくゼロに近づける。
それでいて、空き家を活用して、収入も目指せるかもしれない。
そういう、藤本ならではのやり方です。
【仕組み:どんな風に進めるの?】
簡単に言うと、こんな流れです。
ステップ1:現状確認とヒアリング
まず、僕があなたの空き家の状況を見ます。
写真やオンラインでも大丈夫ですし、必要なら苫小牧まで見に行きます。
そして、あなたがどうしたいのか、どんな状況なのか、詳しくお話を聞かせてください。
ステップ2:管理代行契約を結ぶ
「この家なら、活用できるかもしれない」と僕が判断したら。
あなた(持ち主)と僕(藤本)の間で、管理代行に関する契約を結びます。
(※これは、家を貸す「賃貸借契約」とは違います)
ステップ3:最低限の整備(費用は藤本負担!)
ここがポイントです。
僕の費用負担で、人が使えるように最低限の整備をします。
例えば、こんなことです。
- 簡単な掃除
- 残っている家財道具の整理・処分(※あなたと相談しながら、必要なもの以外)
- 雨漏りなどがあれば、応急処置
- 床が抜けそう、など危ない箇所の簡単な補修
- 給湯器がなければ設置、壊れていたら交換(※これは生活に必須なので)
(すごく大事!)
ここでやるのは、あくまで「最低限」です。
壁紙を張り替えたり、キッチンを新しくしたり、
プロの業者さんに頼んでピカピカにしたり、
そういう、普通の「リフォーム」はしません。
できるだけ「今のまま」に近い状態で、貸せるようにすることを目指します。
ステップ4:借りる人(使う人)を探す
僕が、この空き家を借りたい人を探します。
普通の住まいとしてだけでなく、
趣味の部屋、倉庫、会社の短期利用など。
家の状態や場所に合わせて、色々な使い方を考えます。
僕には、独自の探し方やネットワークがあります。
ステップ5:藤本と借りる人の間で契約
借りたい人が見つかったら、
僕(藤本)が貸主となって、借りる人(入居者など)と契約を結びます。
(あなたは、借りる人と直接やり取りする必要はありません)
ステップ6:家賃収入から、あなたにお支払い
借りる人から家賃をもらいます。
そこから、もし経費(広告費など)がかかっていればそれを引いて。
残った中から、あなたの固定資産税・都市計画税などの年間維持費を、
上回る金額をお支払いすることを目指します。
いくらお支払いできるかは、家の状態や家賃によりますので、
契約を結ぶ前に、ちゃんとご相談しますね。
ステップ7:入居中の管理も、基本お任せ
借りている人からの連絡や、ちょっとしたトラブル対応なども、
基本的には僕が窓口になって行います。
【あなたにとってのメリットは?】
この「管理代行」を選ぶと、あなたにはこんな良いことがあります。
- お金が、ほぼかからない!:
リフォーム代はもちろん、最低限の整備費用も僕が出します。
あなたは、基本的にお金を出す必要がありません。
- 手間が、ほぼかからない!:
借りる人探し、契約、家賃集金、管理…
面倒なことは、基本ぜんぶ僕がやります。
あなたは「何もしなくていい」んです。
- 今のままで、OK!:
「古いから」「汚れているから」と諦めないでください。
家の中に物がたくさん残っていても大丈夫です(一緒に片付けましょう)。
最低限の安全が確保できれば、今のまま活用できる道を探します。
- 税金の負担が軽くなる(かも?収入も?):
毎年払っている固定資産税が、重荷になっていませんか?
もし、それ以上の収入が得られれば、負担が軽くなりますよね。
空き家が「お荷物」から「収入源」に変わるかもしれないんです。
- 家が傷みにくくなる:
人が住んだり使ったりすると、家の空気が入れ替わります。
だから、家が傷むスピードを抑えられます。
- 将来の選択肢は、あなたのもの:
家の所有権は、あなたのままです。
だから、将来もし状況が変わったら、
契約を見直したり、自分で使ったり、売ったりすることも可能です。
【注意してほしいこと(デメリット・注意点)】
もちろん、良いことばかりではありません。注意点もあります。
- 家賃保証ではありません:
これは、借りる人が見つかって、家賃を払ってくれて、初めて収入になる仕組みです。
僕が「毎月必ずいくら払います」と保証するものではありません(サブリースとは違います)。
だから、借り手が見つからない間は、あなたへの収入の支払いはありません。
(ただし、その間も、あなたがお金を出す必要はありません)
- 大きな儲けは期待しないで:
「今のまま」に近い状態で貸すので、家賃は相場より安くなることが多いです。
だから、収入は「固定資産税分+少し」くらいになる可能性が高い。
これで大儲けしよう、というものではありません。
- 全部の家でできるわけじゃない:
残念ながら、建物の状態があまりにも悪くて、最低限の安全も確保できない場合。
あるいは、場所的に、どうしても借り手が見つかりそうにない場合。
そういう場合は、この方法が使えないこともあります。
- 僕ができる管理の範囲:
僕がやる管理は、日常的な簡単な対応が中心です。
もし、すごく大きな修理が必要になったり、法律が絡むような難しいトラブルが起きたりしたら、
その時は、あなたに相談させてもらうことがあります。
- 契約期間について:
通常は、ある程度の期間(例えば2年とか5年とか)の契約をお願いすることになります。
【苫小牧市での可能性は?】
この「管理代行」のやり方。
苫小牧市でも、うまくいく可能性は十分にあると思っています。
- 安い家を探している人向け:
「新しくて綺麗じゃなくてもいい。とにかく家賃が安い方がいい」
そういう学生さんや、一人暮らしの方、生活保護を受けている方など。
需要があるかもしれません。
- DIYしたい人向け:
「古い家でも、自分で好きにいじって住みたい!」
そういうDIY好きの人には、今のままの状態がむしろ魅力的に見えることも。
- 外国人労働者の方の住まい:
苫小牧の産業を支えている外国人の方々。
比較的安い一軒家を探しているかもしれません。
- 会社の短期利用:
工事などで、一時的に従業員の住まいが必要な会社。
家具などが残っている古い家が、逆に都合が良い、なんてことも。
- 趣味のスペースとして:
住むためじゃなく、例えば…
バイクをいじるガレージ。
陶芸や木工をするアトリエ。
音楽の練習部屋(防音は必要ですが)。
そういう、広い場所を安く借りたい、という人もいます。
家の状態や場所に合わせて、
どんな使い方があるか、どんな人にニーズがあるか。
それを見つけ出すのが、この提案のポイントです。
(例えば、駅から遠くても、車を持っている人なら問題ないかもしれませんよね?)
「うちの空き家でも、もしかしたら…?」
そう少しでも思ったら、ぜひ一度、僕に相談してみてください。
相談は無料ですから。
提案②:「倉庫・資材置き場」としての活用 ~住めなくても、建物があれば価値がある~

「家が古すぎて、とてもじゃないけど人には貸せないな…」
「雨は漏ってないみたいだけど、お風呂もトイレも使えないし、中はボロボロだし…」
そんな、住む家として使うには、ちょっと厳しい状態の空き家。
それでも、諦めるのはまだ早いかもしれません。
建物自体が、まだちゃんと建っていて、雨風をしのげるなら。
「倉庫」や「資材置き場」として、
誰かの役に立つ可能性があるんです。
【仕組み:どんな風に使うの?】
基本的な流れは、提案①の「管理代行」と似ています。
ステップ1:現状確認とヒアリング
僕が物件の状態を見て、倉庫などとして使えるか判断します。
ステップ2:管理代行契約を結ぶ
あなた(持ち主)と僕(藤本)の間で契約します。
ステップ3:最低限の整備(費用は藤本負担!)
倉庫として使うために、危ないところがないかチェックしたり、
簡単な掃除をしたり、入口の鍵を確認したり。
必要最低限の整備を、僕の費用負担で行います。
(※住むための修理は必要ありません)
ステップ4:利用してくれる事業者を探す
僕が、地域の会社や個人事業主の方で、
倉庫や、仕事で使う資材・道具を置く場所、
簡単な作業スペースなどを探している人に声をかけます。
建設業、運送業、電気屋さん、庭師さん、ネットショップの人…
色々な可能性があります。
ステップ5:藤本と利用者の間で契約
利用したい人が見つかったら、
僕(藤本)が貸主となって、その事業者さんと契約を結びます。
ステップ6:賃料収入から、あなたにお支払い
利用者さんから賃料をもらいます。
そこから経費を引いて、残った中から、
あなたの固定資産税・都市計画税などの年間維持費を、
上回る金額をお支払いすることを目指します。
ステップ7:利用中の管理も、基本お任せ
利用状況の確認や、利用者さんからの簡単な連絡などは、僕が対応します。
(倉庫の場合、人が住むより管理の手間は少ないことが多いです)
【あなたにとってのメリットは?】
- 住むためのリフォームは不要!:
人が住むわけではないので、キッチンやお風呂を直す必要はありません。
費用負担が、ほとんど発生しないのが大きなメリットです。
- 手間がかからない:
利用者探しから契約、賃料回収、簡単な管理まで、僕がやります。
- 「住めない家」でも収入になるかも:
もう壊すしかない、と思っていたボロボロの家でも。
その「空間」自体に価値を見つけて、収入に繋げられるかもしれません。
- 税金の負担が軽くなる:
賃料収入で、固定資産税などの支払いが楽になります。
- 比較的、長く使ってもらえる可能性:
仕事で使う倉庫の場合、一度借りると、比較的長い期間使ってもらえることが多いです。(もちろん、その事業者さんの状況によりますが)
- 家の状態維持にも(少しは):
全く使われないよりは、定期的に人の出入りがあった方が、
家の異常(雨漏りとか)に早く気づけることもあります。
【注意してほしいこと(デメリット・注意点)】
- 使い道が限られる:
倉庫や資材置き場として借りたい、という需要は、
住みたい、という需要ほど多くはありません。
場所や周りの環境によっては、利用者を見つけるのが難しいこともあります。
- 家賃は安め:
人が住む場合と比べると、家賃は安くなるのが普通です。
大きな収入にはなりにくいです。
- 周りの家への配慮が必要:
利用する事業者さんによっては、
資材の運び込みなどで、音や振動が出たり、
トラックなど大きな車が出入りしたりするかもしれません。
事前にどんな使い方をするのかよく聞いて、
近所迷惑にならないように、気をつける必要があります。
場合によっては、使う時間帯などを制限することも考えます。
- あまりにもボロボロだと無理:
いくら倉庫でも、今にも壊れそうな家は使えません。
最低限、建物として安全である必要はあります。
- どんな人が使うか?:
どんな事業者さんが使うかによって、管理の手間やトラブルのリスクも変わります。
信頼できる利用者さんを見つけることが大事です。
【苫小牧市での可能性は?】
工業都市で、港もある苫小牧市。
ここは、倉庫や資材置き場のニーズが、比較的高い地域かもしれません。
- 建設・土木関係の業者さん:工事現場の近くに、資材や道具を置きたい。
- 港や物流関係の業者さん:港の近くなら、需要があるかも。
- 製造業関係の中小企業や個人事業主さん:部品や製品を一時的に置きたい。
- 農業や漁業関係の方(郊外なら):農機具や漁具、肥料などを置きたい。
- ネットショップを運営している人:在庫商品を置く場所が欲しい。
- 個人の趣味の道具置き場:バイク、キャンプ用品、釣り道具など、家には置けない大きな物を置きたい。
特に、敷地が広い家や、トラックなど大きな車が入りやすい場所にある家は、
倉庫・資材置き場としての価値が高そうです。
「家としてはもうダメだけど、建物はまだしっかりしてる…」
そんな空き家をお持ちなら、この使い方も、ぜひ考えてみてください。
住めない家も、諦めないで!
ボロボロだから解体しかない… と思う前に、倉庫や作業場としての活用を考えてみませんか? 費用負担なしで、収益化の道を探ります。まずはLINEでご相談を。
提案③:「解体費用半額負担」での引取り ~どうしても手放したい場合の最終手段~
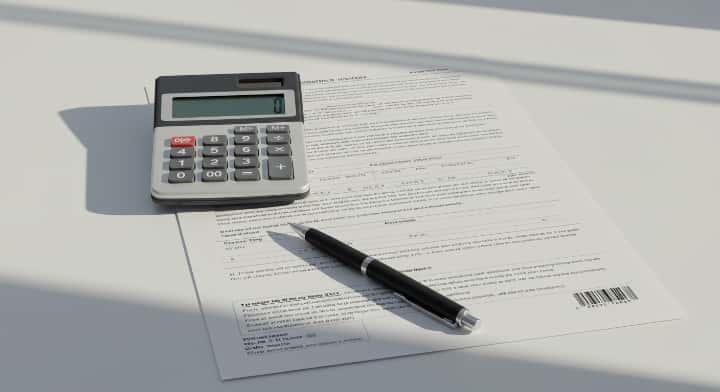
提案①の管理代行も、②の倉庫活用も、難しい…
「とにかく、もうこの空き家を手放して、スッキリしたい!」
「管理の負担や、いつ壊れるか分からないリスクから、一刻も早く解放されたい!」
「でも、家を壊すお金(解体費用)なんて、とても用意できない…」
そんな、もうどうしようもない、八方塞がりだと感じている。
そんなあなたのための、最後の手段が、これです。
「解体費用半額負担での引取り」
【仕組み:どういうこと?】
流れはこうなります。
ステップ1:現状確認とあなたの意思確認
まず、物件の状態を確認します。
そして、あなたが本当にこの家を手放したい、と強く思っているか。
そして、活用するのが非常に難しい状態か、を確認します。
ステップ2:解体費用の見積もり
信頼できる解体業者さんに、解体費用がいくらかかるか、見積もりを取ってもらいます。
(見積もりは無料です)
ステップ3:条件の提案と合意
見積もりが出たら、僕から提案します。
「その解体費用の『半額』を、僕(藤本)が負担します。」
「残りの『半額』を、あなた(持ち主)に負担していただければ、」
「その空き家(土地と建物)の所有権を、僕に移させてもらえませんか?(=僕が引き取ります)」
ステップ4:契約と登記、費用のお支払い
この条件で納得していただけたら、契約を結びます。
これは不動産の売買契約になりますが、売買代金は実質ゼロ円。
解体費用を分け合うことが条件、という形です。
そして、家の名義を僕に変える登記をします。
あなたは、解体費用の半額分を、決められた方法で僕にお支払いいただきます。
ステップ5:引取り完了!あとは藤本にお任せ
家の名義が僕に変わった時点で、あなたの責任は、もう完全に無くなります。
その後の物件の管理、活用、あるいは解体を含めた処分などは、
全て、僕(藤本)の責任において行います。
あなたが、その後のことについて心配する必要は一切ありません。
(すごく大事!)
この提案は、僕があなたの家を「買う」というよりは、
「解体費用の負担を一緒に分け合うことで、あなたが空き家問題から完全に解放されるのを、お手伝いする」
そういう意味合いが強いです。
だから、物件の引取り価格(売買代金)は、基本的にはゼロ円、と考えてください。
【あなたにとってのメリットは?】
- 解体費用の負担が、半分で済む!:
普通なら全額自分で払わないといけない、高額な解体費用。
それを半額で済ませられる。これは、ものすごく大きなメリットですよね。
- 完全に問題から解放される!:
家の名義が僕に移った瞬間から、あなたはもう、その空き家とは無関係です。
固定資産税の支払い義務、管理の責任、将来壊れるかもというリスク…
そういった、全ての心配事から解放されます。心の負担もなくなります。
- 面倒な手続きもお任せ:
もし解体する場合でも、解体業者さん選びや契約、工事の立ち会いなど。
そういう面倒なことは、基本的に僕がやります。
- 早く解決できる:
活用が難しい家の場合、これが一番早く、確実に問題を終わらせる方法になることもあります。
【注意してほしいこと(デメリット・注意点)】
- 家と土地の所有権を失う:
当然ですが、引き渡した後は、もうあなたの家・土地ではありません。
思い出の詰まった場所を手放すことへの、気持ちの整理も必要かもしれません。
- 解体費用の半額は、負担が必要:
負担が半分になるとはいえ、元の解体費用が高ければ、
半額でも数十万円~百万円以上になる可能性はあります。
そのお金を用意できることが、この提案を受け入れる前提になります。
- あくまで「最後の手段」:
これは、提案①や②のような活用が、どうしても難しい場合の、
本当に「最後の手段」だと考えてください。
まずは、活用できる可能性がないか、しっかり検討することが大事です。
安易に「壊して手放そう」と考えるべきではありません。
- 全部の家でできるわけじゃない:
土地の権利関係がすごく複雑だったり、法律的な問題があったりすると、
まれに、引き取りが難しいケースもあります。
【苫小牧市での適応】
この「解体費用半額負担での引取り」は、
苫小牧市内で、次のような状況で困り果てている方にとって、
有効な解決策になるかもしれません。
- 古すぎて、今にも壊れそうな危険な空き家
- 法律的に、家を建て替えられない土地にある空き家
- 相続した兄弟姉妹で揉めてしまい、誰も管理もお金も出せない空き家
- 持ち主が高齢だったり、病気だったり、お金がなかったりで、もうどうしようもない空き家
「もう解体するしかないんだろうけど、お金がなくて…」
そんな風に、絶望しかけている方がいたら。
この方法が、希望の光になるかもしれません。
でも、何度も言いますが、これは最後の手段。
まずは、あなたの空き家に、まだ活用の道がないか。
一緒に考えさせてください。
解体費用の壁、一緒に乗り越えませんか?
高額な解体費用、相続トラブル… もう打つ手がない、と諦めないでください。藤本の「半額負担引取り」なら、負担を減らして問題を完全に解決できるかもしれません。最後の手段として、ご相談ください。
以上、僕、藤本が提案する、
お金と手間をかけずに苫小牧市の空き家問題を解決するための、
3つの具体的な方法について説明しました。
① 管理代行による収益化
② 倉庫・資材置き場としての活用
③ 解体費用半額負担での引取り
あなたの空き家の状態や、あなた自身の考え方によって、
どの方法が一番合っているかは、違ってきます。
もしかしたら、これらの方法を組み合わせたり、
少しやり方を変えたりすることで、
もっと良い解決策が見つかるかもしれません。
一番大切なのは、「諦めないで、まずは相談してみる」ということです。
僕、藤本は、あなたの状況に真剣に耳を傾けます。
そして、費用をかけずに問題を解決できる一番良い道がないか、
全力で、あなたと一緒に考えます。
相談はもちろん無料です。
どうぞ、気軽に、あなたの声を聞かせてください。
【要チェック】苫小牧市で使える? 空き家に関する支援制度・補助金情報(※注意点あり)
空き家の解体やリフォーム。
どうしてもお金がかかることが多いですよね。
「少しでも、市や道から補助が出ないかな…?」
そう考えるのは、自然なことです。
実際に、国や、北海道、そして苫小牧市が、
空き家を減らしたり、活用したりするために、
色々な支援制度や補助金を用意している場合があります。

でも! ここで、すごく大事な注意点があります。
補助金の話を聞くときは、必ず頭に入れておいてください。
【補助金についての【超・重要】な注意点!】
まず、絶対に覚えておいてほしいこと。
- 制度はコロコロ変わる!:
補助金は、毎年度、内容が見直されます。
今年あった制度が来年もあるとは限りません。
金額や条件が変わることもよくあります。
- 予算には限りがある!:
補助金は税金から出ています。
だから、使えるお金(予算)が決まっています。
人気のある制度は、すぐに予算がなくなって、
年度の途中でも受付終了、なんてことも普通にあります。
- 誰でも、どの家でもOKじゃない!:
利用するには、すごく細かい条件があります。
家の古さ、状態、場所、持ち主の収入、どう使うか…
全部クリアしないと、対象になりません。
- 手続きが大変!:
申請するには、たくさんの書類が必要です。
手続きも複雑で、時間がかかることが多いです。
- すぐにお金はもらえない!:
多くの場合、工事が終わって、検査を受けてから。
やっと補助金が振り込まれます。
だから、工事費用は、一旦ぜんぶ自分で払う(立て替える)必要があります。
だから、この記事に書いてある情報は、
「こういう制度があるかもしれない」という、あくまで一般的な例です。
今、この瞬間、苫小牧市で使えることを保証するものでは、絶対にありません!
補助金について詳しく知りたい場合は、
必ず、あなた自身で、
苫小牧市の公式ウェブサイトを見るか、
市役所の担当窓口(都市建設部 建築指導課など、制度によって窓口は違います)に、
直接電話などで問い合わせて、最新の正確な情報を確認してください。
これが、一番大事なことです!
(苫小牧市 公式ウェブサイト: https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/ )
この注意点を、よーく頭に入れた上で。
一般的に、どんな種類の補助金制度がある可能性があるのか、
いくつか例を挙げてみますね。
【苫小牧市で使える「かもしれない」制度・補助金の例】
(※繰り返しですが、あくまで例です。詳細は必ず市役所にご確認を!)
空き家を「壊す」ときの補助金
- どんな目的?:
倒れそうで危ない家とか、周りに迷惑をかけている家を壊すのを応援して、
街を安全に、きれいにするため。
- どんな家が対象かも?:
市が決めた「危険度」の基準を満たす家。
特定のエリアにある家。
長い間空き家だった家、など。
- 誰がもらえるかも?:
家の持ち主(相続人も含む)。
収入に制限がある場合も。
- いくらくらいもらえるかも?:
壊すのにかかった費用の〇分の1(例:半分とか3分の1とか)。
ただし、上限〇〇万円(例:50万円とか100万円とか)まで、という形が多い。
- 気をつけること:
事前に市役所の調査や判定が必要なことが多い。
予算が少ないのですぐ締め切られるかも。
解体業者さんと契約する「前」に申請しないとダメな場合も。
- どんな目的?:
空き家を「直す」ときの補助金
- どんな目的?:
空き家をリフォームして、
移住してくる人や、子育て中の家族が住めるようにしたり、
地域の人が集まる場所として使ったりするのを応援するため。
地震に強くしたり(耐震改修)、冬暖かくしたり(断熱改修)するのを助ける場合も。
- どんな家が対象かも?:
家の古さや場所などに条件があることが多い。
市の「空き家バンク」に登録されている家が対象、ということも。
- 誰がもらえるかも?:
家の持ち主。
あるいは、空き家を買ったり借りたりして直す、移住者や子育て家族など。
- いくらくらいもらえるかも?:
直すのにかかった費用の〇分の1、上限〇〇万円、という形が多い。
どんな工事が対象になるか、細かく決まっている(例:お風呂の工事はOKだけど、壁紙だけはダメ、とか)。
- 気をつけること:
直した後に、「〇年間は人に貸さないといけない」とか、
「移住者が〇年間は住み続けないといけない」とか、条件が付くことがある。
これも、工事を始める「前」に申請が必要。
- どんな目的?:
「空き家バンク」関係の補助金
- どんな目的?:
市町村がやっている「空き家バンク」(空き家情報を集めて紹介する仕組み)に、
家を登録してもらうのを応援するため。
- どんな内容かも?:
バンクに登録するときに、家の中の片付け費用を少し補助するとか。
バンクの家を買ったり借りたりする人が、リフォームする費用を補助するとか。
登録してくれた人に、少しお金を出すとか。
- 気をつけること:
まず、苫小牧市が空き家バンクをやっているか? どんな補助があるか? を確認。
バンクに登録することが大前提。
- どんな目的?:
「移住」してくる人向けの補助金
- どんな目的?:
苫小牧市に、他の街から引っ越してきてもらうのを応援するため。
- どんな内容かも?:
移住してきた人が、苫小牧で家(空き家を含む)を買ったり借りたりする費用を補助。
家をリフォームする費用を補助。
引っ越し代を補助、など。
国や北海道の制度とセットになっていることも。
- 気をつけること:
移住してくる人の年齢、仕事、前の住所、何年住むか、など。
対象になる人の条件が、すごく細かいことが多い。
- どんな目的?:
その他の関係する補助金
- 地震に強くするための補助金:古い家(昭和56年より前)の耐震診断や耐震改修工事の費用補助。
- 危ないブロック塀を壊す補助金:地震で倒れる危険があるブロック塀などを撤去する費用補助。
- 省エネ・バリアフリー改修の補助金:断熱改修、エコキュート設置、手すり設置、段差解消などの費用補助。
【補助金をもらうまでの流れ(一般的な例)】
もし補助金を使おうと思ったら、だいたいこんな順番で進みます。
(制度によって違うので、あくまでイメージです)
- 情報集め・相談:市のウェブサイトや窓口で、使える制度があるか、条件は何か、いつまでか、などを確認。
- 事前相談・調査:市役所の担当者に相談。必要なら家の状況を見てもらう。
- 見積もりを取る:工事してくれる業者さんから、見積もりをもらう。
- 申請書類の準備・提出:申請書や計画書、見積書、家の図面、登記簿、税金の証明書など、必要な書類を全部そろえて、期間内に提出。
- 審査・決定:市役所で審査。「補助金を出しますよ(交付決定)」か「ダメです(不交付決定)」の連絡が来る。
- 契約・工事スタート:「交付決定」の連絡が来てから、業者さんと契約して、工事を始める。(※決定前に始めると補助金もらえなくなることが多い!)
- 工事完了・報告:工事が終わったら、「終わりました」という報告書や、領収書、工事中の写真などを市役所に提出。
- 検査・金額確定:市役所の人が検査に来たりして、補助金の最終的な金額が決まる。
- 請求・受け取り:決まった金額を市役所に請求して、後日、自分の口座にお金が振り込まれる。
ね? 結構、手間と時間がかかりそうでしょう?
【補助金に対する、僕の考え方】
誤解しないでほしいのですが、
補助金を使うこと自体は、僕は全然、反対じゃありません。
使えるものがあるなら、しっかり情報を集めて、
上手に活用するのは、費用を抑えるためにとても良いことです。
でも、これまでお話ししてきたように、
補助金って、不確実なことが多いし、制約も多い。
「もらえると思ってたのに、もらえなかった…」
「手続きが面倒すぎて、途中で諦めた…」
そういう話、本当にたくさん聞くんですよ。
だから、僕としては、
「補助金があるから、これをやろう!」と考えるんじゃなくて、
「まず、補助金がなくてもできる、お金のかからない方法はないかな?」
そう考えることを、お勧めしたいんです。
例えば、僕が提案する「管理代行」や「倉庫活用」。
これは、そもそも持ち主の方のお金がほとんどかからない。
だから、補助金があってもなくても、できる可能性があるんです。
あるいは、「解体費用半額負担での引取り」。
これは、もし補助金が使えなかったり、使っても自己負担が大きすぎたりする場合の、
助け舟になるかもしれません。
もちろん、あなたからご相談を受けた時に、
「このケースなら、市の〇〇補助金が使えるかもしれませんよ」
そんなアドバイスは、できる限りさせていただきます。
でも、それに頼りすぎるんじゃなくて。
もっと確実で、もっと負担の少ない方法がないか。
一緒に、考えていきましょう。
【最後に、もう一度だけ!】
本当にしつこいようですが、大事なことなので繰り返します。
補助金に関する情報は、すぐに古くなります。
この記事の内容は、あくまで参考。
必ず、最新の正確な情報を、苫小牧市の公式ウェブサイトや担当窓口で、
あなた自身で確認してくださいね!
補助金、本当に使えますか?
補助金は魅力的ですが、条件や手続きが複雑なことも。「使えるか分からない」「手続きが面倒…」そんな時も、藤本にご相談ください。補助金に頼らない解決策も一緒に考えます。
【実例でイメージ】もし苫小牧市の空き家を藤本に任せたら? 成功モデルケース紹介
ここまで、空き家のリスクや色々な解決策、
そして僕、藤本の提案について、詳しくお話ししてきました。
「藤本さんのやり方は分かったけど、
実際にどんな風に解決するのか、もっと具体的に知りたいな」
そう思っている方も、きっといらっしゃいますよね。
そこで、ここからは、
もしあなたの北海道 苫小牧市にある空き家を、
僕、藤本に任せていただけたら、
どんな風に問題が解決して、活用される可能性があるのか。
僕がこれまで関わってきた事例などを元にして、
いくつかの「モデルケース」としてご紹介します。
(※これは、実際の事例を元にした架空のケースです。
プライバシーに配慮して、場所や名前などは変えています)

モデルケース1:【管理代行】遠方在住の相続人が、手間なく固定資産税負担から解放されたケース
<こんな状況でした>
- 場所は?:苫小牧市の郊外(例えば、沼ノ端や勇払あたりをイメージ)。駅から少し遠い住宅地の一軒家。
- 持ち主は?:東京に住むAさん(50代)。数年前に苫小牧に住んでいた親御さんから相続。
- 家の状態は?:築40年くらいの木造2階建て。親御さんが亡くなってから約3年間、誰も住んでいない。少し傷んではいるけど、大きな問題はなさそう。でも、家の中には家具や生活用品がそのまま…。
- Aさんの悩み:
東京から苫小牧は遠くて、管理に行けない。
固定資産税(年7万円くらい)を払うのが大変。
家の中の片付けも、どうしたらいいか分からない。
不動産屋さんに聞いたら「片付けてリフォームしないと売れないかも」と言われた。
壊すにもお金がかかる(見積もり180万円!)し、困り果てていた。
<藤本がこうしました!>
- LINEで相談:AさんからLINEで連絡があり、写真を見せてもらったり、詳しく話を聞きました。
- 「管理代行」を提案:「今のままでも、少し手を入れたら貸せるかもしれませんよ」と提案。「残置物はこちらで片付けます」「Aさんのお金は基本かかりません」「固定資産税以上の収入になるかも」と説明。
- 契約と鍵預かり:Aさんは「お金も手間もかからないなら」と納得。管理代行契約を結び、家の鍵を送ってもらいました。
- 最低限の整備(藤本負担):僕(または協力者)が現地へ。Aさんと相談して不要な物を処分。簡単な掃除と、壊れていた給湯器を交換(これは僕の負担)。雨漏りなどないかチェック。
- 借りる人を探す:「現状のまま」「DIYしてもOK」「家賃は格安(例えば月3万円)」という条件で、地域の人や僕のネットワークで募集。
- 入居者が決定!:地元の工場で働くBさんが「安くて広い家を探してた」「古くても平気」と入居希望。僕が貸主となって、Bさんと賃貸契約を結びました。
- 収入をお支払い:月3万円の家賃収入から、Aさんには年間8万円(固定資産税7万円+1万円)をお支払いする約束に。
<Aさんの喜びの声(想像です)>
「もうどうしようもないと思っていた実家が、まさか収入を生むなんて!
遠くにいて何もできなかったのに、お金も手間も一切かからず、
固定資産税の心配までなくなりました。
家の中の片付けまでやってもらえて、本当に藤本さんには感謝しています!」

遠方の空き家管理、お任せください
相続した実家の管理にお困りではありませんか? 遠方にいても大丈夫。藤本があなたの代わりに、費用負担なく管理・活用します。まずはLINEでご相談を。
モデルケース2:【倉庫活用】住居としては厳しい古家が、地域の事業者の役に立つ場所に
<こんな状況でした>
- 場所は?:苫小牧市の昔からの市街地(例えば、錦町や王子町あたりをイメージ)。ちょっと道が狭い場所にある平屋。
- 持ち主は?:苫小牧市に住むCさん(70代)。親戚が住んでいたけど、もう10年以上空き家。
- 家の状態は?:築60年以上。雨漏りはギリギリ大丈夫そうだけど、全体的にボロボロ。お風呂もトイレもキッチンも使えない。人が住むには大がかりな修理が必要。でも、建物自体はまだ壊れてはいない。広い土間がある。
- Cさんの悩み:
固定資産税(年4万円くらい)だけがかかっていく。
本当は壊したいけど、お金がない(見積もり150万円)。
でも、このまま放置して、もし崩れたりしたら大変だ…
と、ずっと心配していた。
<藤本がこうしました!>
- 直接ご相談:Cさんから直接「どうにかならないかねぇ」と相談を受けました。家を見せてもらい、住むのは難しいと判断。
- 「倉庫」としての活用を提案:「人が住むのは無理でも、この『空間』は使えますよ」と提案。「倉庫や資材置き場として、地域の事業者さんに貸しませんか?」と説明。
- 契約と最低限の整備:Cさんは「そんな使い道があるのか!」と納得。管理代行契約を結びました。僕の負担で、入口の鍵を交換し、危ない箇所がないかチェックして簡単な補修をしました。
- 利用してくれる人を探す:地域の商工会や、僕の知り合いの事業者さんたちに「倉庫スペース探してる人いませんか?」と声をかけました。
- 利用者が決定!:近所で内装工事をしている個人事業主のDさんが、「現場で使う材料や道具を置く場所を探してたんだ」「車も近くに停められそうだ」と利用を希望。僕が貸主となって、Dさんと利用契約を結びました(例えば月1.5万円)。
- 収入をお支払い:月1.5万円の賃料収入から、Cさんには年間5万円(固定資産税4万円+1万円)をお支払いすることに。
<Cさんの喜びの声(想像です)>
「もう壊すしかないと思ってた、あのボロボロの家がねぇ。
まさか倉庫として使ってもらえるなんて、考えもしなかったよ。
壊すお金もかからず、税金の心配もなくなって、お小遣いまでもらえるなんて。
本当にありがたい。地域の人の役にも立ててるみたいで、嬉しいねぇ。」

住めない家にも、価値があるかも?
ボロボロで人に貸せない… そんな空き家も、倉庫や作業場として活用できるかもしれません。解体する前に、藤本にご相談ください。新たな可能性を探ります。
モデルケース3:【解体費用半額負担引取り】相続トラブルと費用の壁を乗り越え、問題を完全解決

<こんな状況でした>
- 場所は?:苫小牧市内の、ちょっと不便な場所(例えば、高丘や澄川町あたりをイメージ)。家を建て替えるのが難しいかもしれない土地にある一軒家。
- 持ち主は?:Eさん(60代)と、その兄弟の合計3人の共有名義。相続してから5年以上放置。
- 家の状態は?:築50年。長い間ほったらかしで、ボロボロ。一部壊れていて、かなり危険な状態。市役所からも「特定空家」に指定される寸前だと警告を受けている。どう考えても、もう活用は無理。
- Eさんたちの悩み:
兄弟の間で「どうするか」「誰がお金を出すか」で大揉め。
管理も費用負担も、お互いに押し付け合っている。
固定資産税も滞納しがち。
市役所からは「早く何とかしろ!」と言われている。
壊さないといけないのは分かっているけど、見積もりを取ったら250万円(アスベスト除去も必要)。
誰もそんな大金は出せない。
兄弟仲も最悪…。まさに八方塞がり。
<藤本がこうしました!>
- 代表のEさんからSOS:Eさんから「もう、どうしようもないんです…兄弟とも揉めて…」と、本当に切羽詰まった相談を受けました。状況を聞き、活用は不可能と判断。
- 「半額負担引取り」を提案:「解体費用の半額(125万円)を、ご兄弟でなんとかご負担いただけませんか?」「残りの半額(125万円)は、私が負担します」「その条件で、この家と土地を、私に引き取らせてください」「そうすれば、皆さんの負担も責任も、これで全部なくなりますよ」と提案しました。
- 兄弟間の調整をお手伝い:Eさんを通じて、他の兄弟にもこの提案を伝えました。最初は「なんで俺たちが金を出さないといけないんだ!」と反発もありました。でも、「このまま放置したら、税金が6倍になって、最後は市に壊されて全額請求されるリスク」「共有名義のままだと、将来子どもたちに迷惑がかかること」「半額負担するだけで、完全にこの問題から縁を切れるメリット」などを、丁寧に、粘り強く説明しました。
- なんとか合意へ:時間はかかりましたが、最終的に兄弟全員が「それしかないか…」と納得。僕と共有者全員の間で、売買契約(負担付き贈与に近い形)を結びました。Eさん兄弟は、解体費用の半額(125万円)を分割して僕に支払うことに。
- 所有権移転、そして問題解決!:家の名義が僕に変わりました。これで、Eさんたちの責任は、完全にゼロになりました。その後の物件(土地・建物)をどうするか(活用するか、再販するか、解体するか等)は、全て僕の責任において行います。Eさんたちが、もう悩む必要はありません。
<Eさんの安堵の声(想像です)>
「本当に、長年の悩みの種でした。兄弟ともギクシャクして…。
解体費用が高すぎて、もうどうしようもないと諦めかけていたんです。
でも、藤本さんの提案のおかげで、負担が半分で済んで、
何よりも、あの家と縁を切れたことで、やっと肩の荷が下りました。
これを機に、兄弟との関係も少し良くなった気がします。
本当に、本当にありがとうございました。」
解体費用の壁、一緒に乗り越えませんか?
高額な解体費用、相続トラブル… もう打つ手がない、と諦めないでください。藤本の「半額負担引取り」なら、負担を減らして問題を完全に解決できるかもしれません。最後の手段として、ご相談ください。
—
どうでしたか?
これらは、あくまでモデルケースですが、
あなたの苫小牧市の空き家にも、
きっと、何らかの解決の道筋が見つかるはずです。
大事なのは、一人で悩まないこと。
専門家の力を借りること。
そして、「お金をかけずに解決できるかもしれない」
そういう選択肢があることを、知っておくことです。
次は、多くの方が疑問に思う点について、
Q&A形式でお答えしていきますね。
【疑問を解消!】空き家に関するよくある質問(FAQ)
ここまで、空き家のリスクや解決策、
そして僕、藤本の提案について、詳しくお話ししてきました。
きっと、色々な情報に触れる中で、
「これはどうなの?」「自分の場合は?」
そんな疑問も浮かんできているかもしれませんね。
ここでは、僕が普段よくいただくご質問と、
それに対する答えをQ&A形式でまとめました。
あなたの疑問を解消する、手助けになれば嬉しいです。

- 本当に相談は無料なんですか?
-
はい、ご相談は完全に無料です。公式LINEにて受付をしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
- 藤本さんは大阪在住とのことですが、大阪から遠方の物件でも本当に対応可能なんですか?
-
はい、全く問題ありません! 僕は全国の空き家に対応しています。パートナーである「廃墟不動産投資家の村上氏」「日本の空き家研究所代表の竹田氏」のネットワークもありますので、地域に関わらず、まずはご相談ください。距離は問題になりませんよ。
- 築年数がかなり古い家、ボロボロで雨漏りもするような家でも相談できますか?
-
はい、どんな状態の家でも、まずはご相談ください。 「こんな状態じゃ誰も見向きもしないだろう…」とご自身で判断せずに、まずは現状をお聞かせください。LINEで写真(外観・内観)を送っていただけると、より具体的なお話ができます。諦める前に一度、可能性を探らせてください。
- 一軒家だけですか? アパートの空き部屋でも相談可能ですか?
-
はい、一軒家だけでなく、アパートでもご相談可能です。まずは物件の種類と状況をお知らせください。
- 家の中に荷物(家具や生活用品など)がたくさん残っている状態でも大丈夫ですか?
-
はい、残置物がある状態でも全く問題ありません。 ご自身で片付けるのが大変な場合も、ご相談ください。空き家の中に残置物がそのままの場合でも対応することも可能です。そのまま活用できる家具などは、次の入居者に使ってもらうこともあります。
- 相続した物件で、兄弟(姉妹)と共有名義になっているのですが、相談できますか?
-
はい、共有名義の物件でも、ご相談は可能です。ただし、最終的に管理代行契約や引取り契約を結ぶ際には、原則として共有者全員の同意が必要になります。もし、相続人間で意見がまとまらずお困りの場合も、どうすれば合意形成ができるか、解決に向けてのアドバイスやサポートをさせていただきます。
- 管理代行をお願いした場合、固定資産税はどうなりますか? 他に費用はかかりますか?
-
管理代行の場合でも、固定資産税・都市計画税の支払い義務は、引き続き所有者様にあります。僕の目標は、家賃収入でこれらの税金をカバーし、さらにプラスの収益をお返しすることです。その他の費用については、前述の通り、貸し出すための最低限の簡易修繕(雨漏り補修、給湯器交換など)は原則僕が負担しますが、それ以上の大規模な修繕が必要になった場合などは、別途ご相談となります。契約前に費用負担については明確にご説明しますのでご安心ください。
- 管理代行の家賃収入は保証されるのですか? いわゆるサブリース契約とは違うのですか?
-
僕の管理代行は、不動産会社がよく行う、空室期間も一定の家賃を保証する「サブリース契約(家賃保証付き借り上げ)」とは全く異なります。借り手が見つかってから、オーナー様への家賃収入からお支払いさせていただきます。できるだけ早く、そして安定的に借り手が見つかるよう、僕も最大限の努力をすることはお約束します。
- 相談した内容や、個人情報が外部に漏れることはありませんか?
-
はい、ご相談内容は秘密厳守をお約束します。お預かりした個人情報や物件情報は、空き家問題の解決という目的以外で利用することは一切ありません。また、外部に漏洩することがないよう、厳重に管理いたしますので、どうぞご安心ください。
どうでしたか?
もし、ここに載っていない質問や、
あなたの家の、もっと具体的な状況について。
「これはどうなんだろう?」
「藤本さんに直接聞いてみたい!」
そんなことがあれば、どうぞ遠慮しないでください。
僕のLINEに、直接メッセージを送ってくださいね。
あなたの話をしっかり聞いて、
一つひとつの疑問に、丁寧にお答えします。
もちろん、相談内容が他の人に漏れることは絶対にありません。
秘密は固く守りますので、安心してください。
さいごに:苫小牧市の空き家を、未来へ繋ぐために
いやー、本当に長い時間、お付き合いいただき、
ありがとうございました!
北海道 苫小牧市の空き家について。
なぜ増えているのか、その背景。
放置しておくと、どんな怖いリスクがあるのか。
世間一般では、どうやって解決しようとしているのか。
そして、僕、藤本が提案する、
ちょっと変わっているかもしれないけれど、
負担の少ない解決方法。
できるだけ分かりやすく、詳しくお伝えしてきたつもりです。

空き家の問題って、
ただ「使ってない家がある」ってだけじゃないんですよね。
持ち主の方にとっては、お金の心配、心のストレス。
時には、家族の関係までギクシャクさせてしまう。
本当に、深くて、切実な問題なんです。
そして、地域にとっても、
景観が悪くなったり、安全じゃなくなったり、
空き家は、決して良い影響を与えません。
「もう、どうしようもないのかな…」
「結局、お金をかけるしかないんだろうな…」
もし、あなたが今、そんな風に諦めかけているなら。
ぜひ、今日の話を思い出してください。
お金や手間をかけなくても、
その問題を解決できるかもしれない。
まだ、道は残っているかもしれない。
僕が提案した、
「管理代行」「倉庫活用」「解体費用半額負担引取り」。
これは、普通の不動産屋さんや解体屋さんのやり方とは、
少し違うかもしれません。
でも、だからこそ。
今まで「無理だ」と思っていた状況に、
新しい光を当てることができるかもしれない。
そう、僕は信じています。
僕自身、この活動を通して、
本当にたくさんの「困っている」持ち主の方に会ってきました。
そして、僕の提案で、長年の悩みから解放されて、
ホッとした顔をされた時。
あるいは、使われなくなった家が、新しい人に使ってもらえて、
また少し、明かりが灯った時。
そういう瞬間に立ち会えることが、
僕にとって、何よりの喜びであり、原動力なんです。
僕の根っこにある想いは、すごくシンプル。
「困っている人の、力になりたい」
「使われなくなったモノに、もう一度価値を与えたい」
「地域が、少しでも元気になったら嬉しい」
「日本の空き家研究所」の竹田さんのような、
先を行く人の知恵も借りながら、
僕なりに、本気でこの問題と向き合っています。
あなたの苫小牧市の空き家も、
決して、ただの「お荷物」なんかじゃない。
ちゃんと向き合って、少し手を差し伸べてあげれば、
新しい価値を生み出す「可能性」を、絶対に秘めているはずなんです。
もちろん、僕一人でできることは限られています。
でも、僕には、全国の仲間や専門家のネットワークがあります。
そして何より、あなたの「何とかしたい」という気持ちに寄り添って、
一緒に解決策が見つかるまで、諦めずに考える情熱があります。
もし、あなたが今、苫小牧市の空き家のことで悩んで、
どうしようもなくて、立ち止まっているなら。
どうか、一人で抱え込まないでください。
最初の一歩は、ちょっと勇気がいるかもしれません。
でも、その一歩を踏み出さないと、何も始まりません。
まずは、下のボタンを押して、
僕のLINEに、気軽にメッセージを送ってみてください。
「苫小牧の空き家の件で」
その一言で、大丈夫です。
そこから、あなたの空き家の、そしてあなた自身の未来を、
もっと明るい方向へ動かしていくための、
第一歩を、一緒に踏み出しましょう。
あなたからのご連絡を、心から、本当にお待ちしています。
さあ、今すぐ行動を!
悩んでいるだけでは、何も変わりません。あなたの空き家問題、藤本と一緒に解決しませんか? 相談は無料です。費用も手間もかけずに、問題を解決できるかもしれません。今すぐ下のボタンからLINEでご連絡ください!
※本記事の情報は2025年5月時点のものです。法改正や制度変更、市場動向などにより、内容が現状と異なる場合があります。
※本記事で紹介している支援制度や補助金の情報は2025年5月時点のものです。最新の正確な情報は必ず北海道及び苫小牧市公式ウェブサイト等でご確認ください。
※免責事項:本記事は空き家に関する一般的な情報提供を目的としており、特定の物件に対する法的、税務的、あるいは投資上のアドバイスを提供するものではありません。個別の案件については、必ず専門家にご相談ください。藤本にご相談いただいた場合も、最終的な判断はご自身の責任において行っていただきます。









