
こんにちは、藤本と申します。
僕は大阪を拠点に、全国で増え続ける「空き家」の問題に取り組んでいます。
このページにたどり着いたということは、あなたも今、北海道 留萌市にある空き家や、ご実家のことで頭を悩ませているのかもしれませんね。
留萌市。
日本海に面し、かつてはニシン漁で大いに栄えた港町。
黄金岬に沈む壮大な夕陽、千望台から望むパノラマ、そして「数の子」生産日本一の誇り。
豊かな自然と歴史、そして美味しい海の幸に恵まれた、本当に魅力的な場所だと思います。
僕も仕事で訪れるたび、その独特の風情に心惹かれます。
特に、冬の厳しい寒さや強い風(地元では「だし風」とも呼ばれるそうですね)を知っているからこそ、春の訪れや短い夏の輝きが、より一層尊く感じられるのかもしれません。
しかし、そんな留萌市でも、時代の流れとともに、少しずつ、でも確実に「空き家」が増えているという現実があります。
- 「親から実家を相続したけれど、自分は札幌や、もっと遠い本州に住んでいる…」
- 「留萌に戻る予定もないし、かといって管理のために頻繁に帰省するのは難しい…」
- 「家は古くて傷んでいるし、売ろうにも買い手がつかないのでは…」
- 「毎年、固定資産税だけ払い続けるのは、正直もう限界かもしれない…」
- 「ご近所に迷惑をかけていないか、いつも心配…」
もし、あなたがこうした気持ちを少しでも抱えているなら、どうか一人で抱え込まないでください。
空き家の問題は、複雑で、感情的にもなりやすい、とてもデリケートな問題です。
でも、正しい知識と適切なステップを踏めば、必ず解決の道は見つかります。
****
今日は、なぜ留萌市の空き家を放置してはいけないのか、その具体的なリスクから、一般的な解決策の落とし穴、そして僕が提案する「あなたに負担をかけずに未来へ繋ぐ」ための具体的な方法まで、できるだけ分かりやすく、そして詳しくお話ししていきたいと思います。
この記事が、あなたの悩み解決への第一歩となれば、これほど嬉しいことはありません。
少し長い話になるかもしれませんが、どうぞリラックスして、読み進めてみてください。
「いつか」はもう来ない?留萌市の空き家を放置する、避けられない現実的リスク
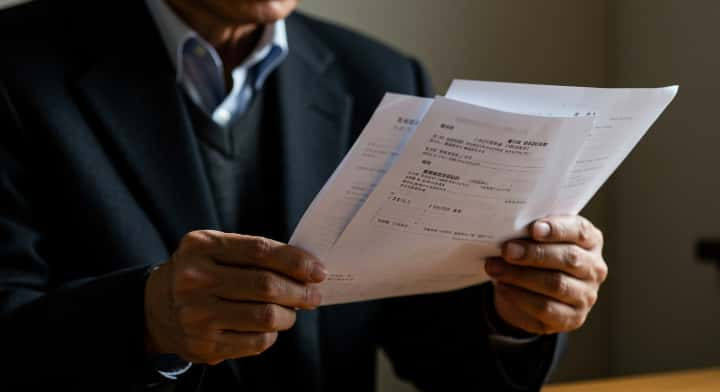
「まぁ、今は誰も住んでいないだけだし、そのうち何とかしよう」
ついつい、そう考えて問題を先送りにしてしまいがちですよね。
特に、留萌市から遠く離れて暮らしている場合、実家の状況を常に把握し、管理し続けるというのは、時間的にも、経済的にも、そして精神的にも大きな負担です。
しかし、残念ながら、空き家を「放置」するという選択は、時間とともに様々なリスクを増大させてしまいます。
それは、まるで静かに進行する病のように、気づいた時には手遅れになりかねない、深刻な問題なのです。
具体的に、どのようなリスクが潜んでいるのでしょうか?
ここでは、大きく分けて5つの観点から、その危険性を詳しく見ていきましょう。
リスク①:逃れられない「経済的負担」の増大 ~固定資産税と特定空家~

まず、最も直接的で避けられないのが、経済的な負担です。
毎年課される固定資産税・都市計画税
空き家であっても、不動産を所有している限り、固定資産税(市町村によっては都市計画税も)は毎年必ず課税されます。
留萌市に物件をお持ちであれば、毎年春ごろに納税通知書が送られてきているはずです。
税額は、その土地と建物の評価額に基づいて計算されますが、たとえ利用していなくても、支払い義務はなくなりません。
「たいした金額じゃないから」と安易に考えてはいけません。
チリも積もれば山となる、ではありませんが、数年、十年と払い続ければ、相当な金額になります。
そのお金、本来ならもっと有効な使い道があったはずですよね?
恐怖!「特定空家」指定による税負担の激増
さらに深刻なのが、「特定空家等」に指定されてしまうリスクです。
これは、「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特措法)」に基づき、そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態、または著しく衛生上有害となるおそれのある状態など、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空き家のことを指します。
具体的には、以下のような状態が判断基準となります。
- 建物が著しく傾いている、または構造材が腐朽・破損している
- 屋根や外壁が剥がれ落ちそう、または剥がれ落ちている
- ゴミが散乱・堆積し、悪臭や害虫が発生している
- 立木等が著しく繁茂し、管理されていない
- その他、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている状態
留萌市は、日本海からの強い風や冬期間の積雪といった厳しい自然環境にさらされるため、建物の劣化が比較的早く進む可能性があります。
適切な管理が行われていない場合、これらの基準に該当しやすくなると言えるでしょう。
もし、あなたの空き家が留萌市によって「特定空家」に指定されると、どうなるか?
まず、固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなります。
通常、住宅が建っている土地(200㎡以下の部分)は、課税標準額が1/6に減額される特例措置が受けられますが、特定空家に指定されると、この優遇が受けられなくなります。
結果として、土地にかかる固定資産税が最大で6倍に跳ね上がる可能性があるのです。
(※都市計画税も同様に、1/3に減額される特例が解除され、税額が最大3倍になる可能性があります)
これは、まさに「寝耳に水」の負担増となり得ます。
行政からの指導、勧告、命令、そして過料…
特定空家に指定されると、税負担が増えるだけではありません。
行政(留萌市)は、所有者に対して、助言・指導、勧告、命令といった段階的な措置を取ることができます。
「適切に管理しなさい」「危険な箇所を修繕しなさい」といった指導に従わず、勧告を受けてもなお改善が見られない場合、市はさらに強い措置として「命令」を出すことができます。
そして、この命令に違反した場合、50万円以下の過料が科される可能性があります。
最終手段「行政代執行」とその費用請求
命令に従わず、放置し続けた場合、最終手段として「行政代執行」が行われる可能性があります。
これは、行政が所有者に代わって、危険な空き家の解体など、必要な措置を行うことです。
「行政がやってくれるなら、それでいいか」と考えてはいけません。
行政代執行にかかった費用(解体費用など、場合によっては数百万円)は、全額、所有者に請求されます。
もし支払えなければ、財産の差し押さえなどに発展する可能性もあります。
このように、空き家を放置することは、経済的なリスクを際限なく高めてしまう行為なのです。
リスク②:思い出の場所が廃墟に…「資産価値の急落」と老朽化の進行

お金の問題だけではありません。
空き家は、あなたが思っている以上のスピードで、物理的に劣化していきます。
人が住まない家は、なぜ傷むのか?
建物は、人が住み、生活することで、ある程度のメンテナンスが自然に行われています。
- 換気:窓の開け閉めによる空気の入れ替えが、湿気を排出し、カビや木材の腐朽を防ぎます。
- 通水:水道を使うことで、給排水管内部のサビや劣化、悪臭の発生を防ぎます。
- 清掃:日常的な掃除が、ホコリや汚れの蓄積、害虫の発生を抑えます。
- 早期発見・早期対応:雨漏りや建具の不具合など、小さな問題に気づき、早めに対処することができます。
空き家になると、これらの「生活によるメンテナンス」が一切行われなくなります。
結果として…
- 湿気とカビ:室内は湿気がこもり、壁や畳、家具などにカビがびっしり生えてしまう。
- 雨漏りと腐食:小さな屋根の隙間や壁のひび割れからの雨漏りが放置され、柱や梁、土台といった構造部分を腐らせてしまう。
- 害虫・害獣の侵入:ネズミやハクビシン、時には蜂などが住み着き、糞尿による汚損や建材の破壊を引き起こす。
- 庭の荒廃:雑草が生い茂り、庭木が伸び放題となり、景観を損ねるだけでなく、害虫の発生源や不法投棄の場所になることも。
- 設備の故障:給湯器やエアコンなどの設備は、長期間使わないと故障しやすくなる。水道管は冬場の凍結で破裂するリスクも(特に留萌市の冬は注意が必要です)。
留萌市特有の環境要因も考慮
留萌市の気候や地理的条件も、建物の劣化に影響を与えます。
- 強風:日本海から吹き付ける強い風(特に冬)は、屋根材や外壁材を傷めたり、飛ばしたりする原因になります。
- 積雪:多量の雪が屋根に積もることで、建物に大きな負荷がかかり、雨漏りや構造の歪みを引き起こす可能性があります。軒先の雪庇(せっぴ)の落下も危険です。
- 塩害:海岸に近いエリアでは、潮風に含まれる塩分が金属部分(トタン屋根や外壁、雨樋など)を錆びさせたり、コンクリートの劣化を早めたりする可能性があります。
- 寒暖差:冬の厳しい寒さと、夏場の(比較的短いですが)暑さによる寒暖差も、建材の収縮・膨張を繰り返し、劣化を促進する一因となります。
資産価値は「ゼロ」どころか「マイナス」へ
このように劣化が進行した空き家は、当然ながら資産価値が大幅に下落します。
「土地の値段があるから大丈夫」と思うかもしれませんが、古家付きの土地は、解体費用がかかる分、更地よりもかえって評価が低くなる(いわゆる「マイナス資産」)ことも少なくありません。
いざ売却しよう、賃貸に出そうと思っても、買い手や借り手を見つけるのは困難になり、見つかったとしても、大幅な値引きや高額なリフォーム費用が必要になるでしょう。
思い出がたくさん詰まった大切な家が、気づけば誰にも見向きもされない「負の遺産」になってしまう。それが放置の現実なのです。
****
僕もね、以前、相続した空き家の管理を少し甘く見ていた時期があったんです。
「まぁ、たまに見に行けばいいか」くらいに考えていたら、ある年の冬、水道管が凍結・破裂してしまって…。
床が水浸しになって、修繕に思った以上の費用と手間がかかりました。
あの時の経験があるからこそ、「放置は本当に怖い」と身をもって感じています。
皆さんは、僕と同じような失敗をしないでほしいな、と切に願います。
リスク③:地域社会への悪影響 ~ご近所トラブルと安全性の問題~
空き家の問題は、所有者だけの問題ではありません。
管理されていない空き家は、その地域全体の環境や安全を脅かす存在にもなり得ます。
景観の悪化とイメージダウン
雑草が生い茂り、建物が朽ちかけた空き家は、単純に見た目が良くありません。
それが一軒でもあると、街並み全体の印象が悪くなり、地域の魅力や価値を下げてしまうことにも繋がります。
「あの辺は空き家が多くて、なんだか寂しい感じだね…」
そんなイメージが定着してしまうのは、誰にとっても悲しいことですよね。
衛生環境の悪化
管理されていない空き家は、残念ながらゴミの不法投棄のターゲットになりやすい傾向があります。
また、ネズミやゴキブリ、ハチなどの害虫・害獣の発生源となり、近隣住民の生活環境を脅かすことも。
庭に生い茂った雑草は、蚊などの発生を助長することもあります。
防災・防犯上のリスク増大
空き家は、様々な危険性をはらんでいます。
- 火災のリスク:放火のターゲットにされやすいだけでなく、漏電などが原因で火災が発生する可能性も。ひとたび火災が起きれば、隣接する家屋に延焼する危険性が非常に高まります。
- 倒壊・飛散のリスク:地震や台風、あるいは留萌市特有の強風によって、老朽化した建物が倒壊したり、屋根瓦や外壁、窓ガラスなどが飛散したりする危険性があります。これが通行人や隣家に被害を与えれば、大惨事になりかねません。
- 犯罪の温床となるリスク:不審者の侵入や、犯罪グループの隠れ家などに利用される可能性も否定できません。地域の治安悪化を招く要因となります。
ご近所トラブルの火種に
空き家の管理不行き届きは、ご近所とのトラブルの原因にもなりやすいです。
- 越境問題:庭木や生垣が隣の敷地に大きくはみ出してしまったり、落ち葉が大量に隣家の雨樋を詰まらせてしまったり。
- 悪臭・害虫問題:放置されたゴミや、建物・庭から発生する悪臭、害虫などが、隣人に不快感を与える。
- 景観問題:「うちの隣だけ、あんなに荒れ放題でみっともない」といった不満。
最初は小さな不満でも、積み重なれば大きなトラブルに発展し、地域での孤立を招くことにもなりかねません。
所有者の法的責任
そして、最も重要なことは、これらの問題によって第三者に損害を与えてしまった場合、空き家の所有者が法的な責任(損害賠償責任)を問われるということです。
民法第717条(土地工作物責任)では、土地の工作物(建物など)の設置または保存に瑕疵(欠陥)があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者(管理している人)、それでも損害が防げなかった場合は所有者が、その損害を賠償する責任を負う、と定められています。
つまり、「知らなかった」「管理できなかった」では済まされないケースがあるのです。
空き家を所有するということは、その建物と土地だけでなく、地域社会に対する責任も負うということなのです。
リスク④:相続トラブルの火種 ~「負動産」が引き起こす亀裂~
空き家問題は、相続の場面で、さらに複雑化することがあります。
誰が管理する?誰がお金を出す?
親から実家を相続したものの、相続人である兄弟姉妹が複数いる場合、
- 「誰が中心となって管理するのか?」
- 「固定資産税や修繕費用は、誰がどう負担するのか?」
といった問題で意見が対立し、揉めてしまうケースが少なくありません。
特に、相続人の一人が留萌市に住んでいて、他の相続人は遠方に住んでいる、といった場合、地元にいる人に管理の負担が偏りがちです。
しかし、費用負担については全員で公平に、となると、なかなか合意形成が難しいことも。
活用か?処分か?意見の不一致
空き家の今後の方針についても、意見が分かれやすいです。
- 「思い出の家だから、残しておきたい」と考える人。
- 「もう誰も住まないし、維持費もかかるから、早く売却したい」と考える人。
- 「賃貸に出して収益化できないか」と考える人。
- 「いっそ解体して更地にすべきだ」と考える人。
それぞれの立場や考え方の違いから、話がまとまらず、結局、誰も意思決定できないまま放置されてしまう…というパターンは、非常によくあります。
共有名義のリスク
相続登記をして、兄弟姉妹などの共有名義になっている場合、売却や大規模なリフォーム、解体などを行う際には、原則として共有者全員の同意が必要になります。
一人でも反対する人がいれば、話を進めることができません。
また、共有者の一人が認知症になったり、連絡が取れなくなったりすると、さらに手続きが困難になります。
空き家という「負動産」が、大切な家族関係に亀裂を入れてしまう…。そんな悲しい事態は、避けたいものですよね。
リスク⑤:機会損失 ~活用できたはずの可能性を逃す~
最後の5つ目のリスクは、少し視点を変えたものです。
それは、「本来なら活用できたはずの可能性を、みすみす逃してしまう」というリスク、つまり機会損失です。
空き家は、確かに厄介な問題を引き起こす可能性があります。
しかし、見方を変えれば、それは「活用されていない資産」であり、「眠っている可能性」でもあるのです。
- もしかしたら、少し手を入れるだけで、快適な住まいとして再生できたかもしれない。
- 留萌市への移住を考えている人に、手頃な価格で貸し出すことができたかもしれない。
- 地域の活性化のために、コミュニティスペースとして役立てることができたかもしれない。
- あなたのアイデア次第で、新しいビジネスや活動の拠点になったかもしれない。
放置している間に建物は劣化し、市場価値は下がり、活用の選択肢はどんどん狭まっていきます。
「あの時、もっと早く行動していれば…」
そう後悔しても、失われた時間と可能性は戻ってきません。
空き家を単なる「お荷物」として捉えるのではなく、「活かせるかもしれない資源」として捉え直す視点も、時には必要なのではないでしょうか。
…さて、ここまで空き家を放置する5つのリスクについて、かなり詳しく見てきました。
「やっぱり、何とかしなきゃいけないな…」
そう感じていただけたのではないでしょうか。
では、具体的に「何とかする」ためには、どうすれば良いのか?
多くの人がまず考えるであろう、一般的な解決策には、実は注意すべき点や「落とし穴」も存在します。
次の章では、そのあたりを掘り下げていきましょう。
放置リスク、他人事ではありません
「うちの空き家、もしかしてリスクが高いかも…」と感じたら、手遅れになる前にご相談ください。具体的な状況を伺い、今すぐやるべきことをお伝えします。
ありがちな失敗談:留萌市の空き家対策で陥りやすい3つの罠
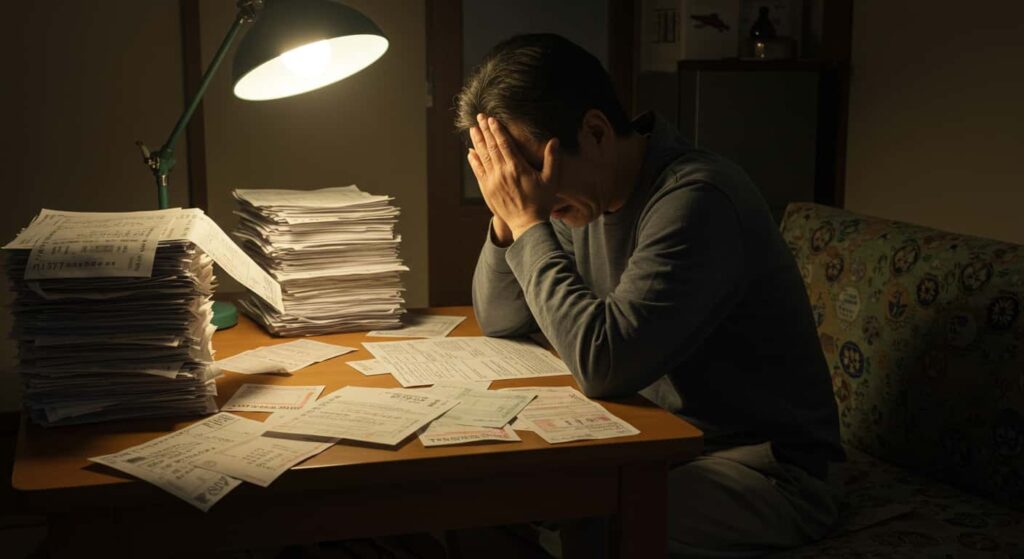
さて、空き家を放置するリスクは十分にご理解いただけたかと思います。
「よし、何とかしよう!」
そう決意するのは素晴らしいことです。
しかし、焦って行動した結果、かえって状況を悪化させてしまったり、思わぬ時間や費用を浪費してしまったりするケースも、残念ながら少なくありません。
ここでは、留萌市の空き家オーナーさんが、つい陥ってしまいがちな「失敗パターン」を3つご紹介します。
他山の石として、ぜひ参考にしてください。
同じ轍を踏まないことが、賢明な解決への近道です。
失敗パターン①:「まだ大丈夫」という先延ばしが生む、取り返しのつかない事態

これが、おそらく最も多くの人が陥ってしまう罠かもしれません。
「そのうち考えよう」
「今は忙しいから、落ち着いたら…」
「まだ誰も困っていないし、急がなくてもいいだろう」
様々な理由をつけて、問題を先延ばしにしてしまう。
その背景には、いくつかの心理的・物理的な要因があります。
なぜ先延ばしにしてしまうのか?
- 心理的な抵抗感:
- 思い出への執着:生まれ育った家、親との思い出が詰まった家を手放すことへの寂しさ、罪悪感。
- 面倒くささ:手続きの煩雑さ、関係者との調整などを考えると、気が重くなってしまう。
- 問題の直視回避:空き家問題を考えると気が滅入るので、無意識のうちに避けてしまう。
- 物理的な障壁:
- 遠方居住:留萌市から遠く離れて暮らしているため、現地に行くこと自体が時間的・経済的に大きな負担。
- 多忙な日常:仕事や子育て、介護など、日々の生活に追われ、空き家のことまで手が回らない。
- 情報不足:どうすれば良いのか、誰に相談すれば良いのか分からず、最初の一歩が踏み出せない。
- 相続人間の意見不一致:前の章でも触れたように、相続人間で方針がまとまらず、膠着状態に陥ってしまう。
先延ばしの「末路」とは?
しかし、この「先延ばし」が、結果的に事態をさらに悪化させ、解決をより困難にしてしまいます。
- リスクの増大:前の章で解説した経済的リスク、老朽化リスク、周辺への影響リスクは、時間とともに確実に増大します。ある日突然、特定空家に指定されたり、建物の一部が崩落したり…といった事態が発生する可能性が高まります。
- 選択肢の減少:放置期間が長引くほど、建物の劣化は進み、資産価値は下がります。そうなると、売却や賃貸といった活用の選択肢がどんどん狭まり、最終的には「解体しか道がない」状況に追い込まれやすくなります。
- 費用の増大:劣化が進めば、修繕費用は高額になります。特定空家に指定されれば、税負担が増えたり、過料が科されたりすることも。行政代執行になれば、莫大な費用を請求される可能性すらあります。早期に対処していれば、もっと少ない費用で済んだはずなのに…。
- 相続問題の複雑化:先延ばしにしている間に、相続人が亡くなったり、認知症になったりして、権利関係がさらに複雑になり、合意形成がより困難になるケースもあります。(いわゆる「数次相続」)
- 精神的負担の増加:問題が解決しないまま時間が過ぎると、「どうしよう…」という不安やストレスが常に付きまとい、精神的な負担も増大していきます。
****
「いつかやろう」の「いつか」は、残念ながら自然にはやってきません。
問題が小さいうちに、選択肢が多いうちに、勇気を出して一歩を踏み出すこと。
それが、結果的に最も負担の少ない解決策に繋がるのです。
「まだ大丈夫」という油断こそが、最大の敵なのかもしれませんね。
失敗パターン②:夢見た活用、しかし現実は…「高額リフォーム投資」の落とし穴
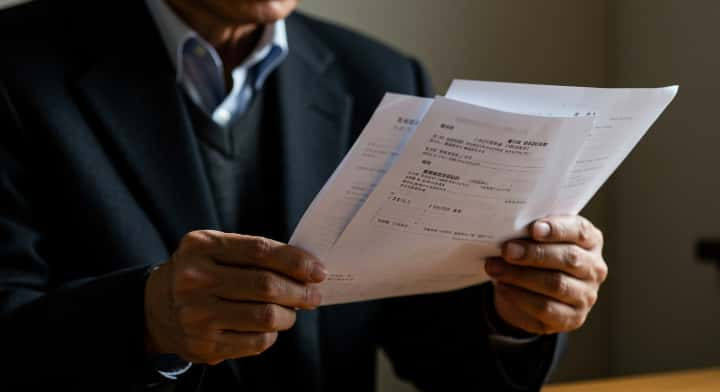
「この古い家も、キレイにリフォームすれば高く売れるはず!」
「おしゃれなカフェやゲストハウスに改装して、人気スポットに!」
空き家を何とか活用しようと考えたとき、大規模なリフォームやリノベーションに夢を託す人は少なくありません。
テレビ番組や雑誌で、古い家が見違えるように再生される様子を見ると、期待感が高まるのも無理はないでしょう。
しかし、ここに大きな落とし穴が潜んでいる場合があります。
特に、留萌市のような地方都市においては、慎重な判断が必要です。
投資した費用、回収できますか?
最大の問題は、リフォームにかけた費用を回収できる保証がどこにもない、ということです。
- 売却の場合:
- 数百万円、場合によっては1000万円以上かけてリフォームしても、その費用を上乗せした価格で売れるとは限りません。留萌市の不動産市場において、高額な中古住宅の需要がどれだけあるでしょうか?
- 買い手は、リフォーム済み物件よりも、価格の安い中古物件を購入し、自分の好みに合わせてリフォームしたい、と考えるケースも多いです。
- 結果的に、リフォーム費用分をほとんど回収できず、大幅な赤字で売却せざるを得なくなる可能性があります。
- 賃貸の場合:
- リフォーム費用を家賃に上乗せして回収しようとすると、周辺の家賃相場よりもかなり高額になってしまう可能性があります。留萌市内で、高い家賃を払ってでも借りたい、という需要が安定して見込めるでしょうか?
- 借り手が見つからなければ、家賃収入はゼロ。リフォーム費用は丸々持ち出しとなり、固定資産税などの維持費だけがかかり続けることになります。
- たとえ借り手が見つかっても、入居期間が短ければ、投資回収には程遠い結果となるでしょう。
留萌市特有の「追加コスト」にも注意
さらに、留萌市の気候や環境を考えると、予想以上のリフォームコストがかかる可能性も考慮すべきです。例えば…
- 断熱性能の向上:冬の厳しい寒さに対応するため、壁、床、天井への断熱材の追加や、高断熱の窓への交換などが必要になる場合、費用がかさみます。
- 雪対策:屋根の強度確保、雪下ろしのしやすい屋根形状への変更、無落雪屋根への改修、融雪設備の設置などは、大きなコスト増に繋がります。
- 風対策:強風に耐えられるような屋根材や外壁材の選定、窓の補強などが必要になる場合があります。
- 塩害対策:海岸に近いエリアでは、サビに強い素材の選定や、定期的なメンテナンス(塗装など)が必要になり、長期的なコストも考慮しなければなりません。
これらの対策を怠ると、せっかくリフォームしてもすぐに不具合が発生し、さらなる修繕費用がかかる…という悪循環に陥る可能性もあります。
業者選びの難しさ
リフォーム業者の中には、残念ながら、オーナーの不安を煽ったり、過剰な工事を勧めたりして、高額な契約を結ぼうとするところも存在します。
「このままだと危険ですよ」「今ならキャンペーンでお得です」といった言葉に惑わされず、複数の業者から相見積もりを取り、工事内容と費用を慎重に比較検討することが不可欠です。
また、地元の評判や実績をよく調べることも重要です。
DIY(自分でリフォーム)の限界
「費用を抑えるために、自分でリフォームしよう!」と考える方もいるかもしれません。
DIYは素晴らしいことですが、専門的な知識や技術が必要な部分(特に構造、電気、水道など)に手を出すのは危険が伴います。
中途半端な仕上がりになったり、かえって状態を悪化させてしまったり、最悪の場合、事故に繋がる可能性もあります。
また、時間と労力も相当かかることを覚悟しなければなりません。
****
もちろん、適切なリフォームによって空き家が再生され、有効活用されるケースもあります。
しかし、それは「市場のニーズ」「物件の状況」「投資額と回収の見込み」などを冷静に分析し、綿密な計画を立てた上での話。
「とりあえずキレイにすれば何とかなるだろう」という安易な考えで高額なリフォームに踏み切るのは、非常にリスクが高い選択だと言えるでしょう。
特に、「売るため」「貸すため」のリフォームは、費用対効果をシビアに見極める必要があります。
失敗パターン③:「補助金があるから大丈夫」という甘い見通しの罠
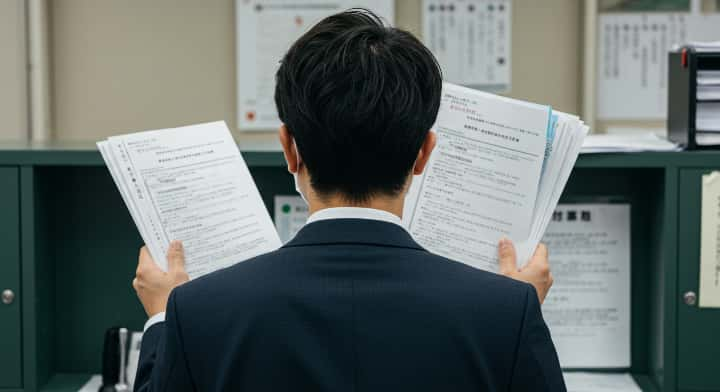
「空き家の解体やリフォームには、国や市から補助金が出るんでしょ?」
そんな話を耳にして、補助金を「あて」にして計画を進めようとする方もいらっしゃいます。
確かに、空き家対策に関する補助金制度は、国や多くの自治体で実施されており、留萌市にも何らかの支援制度が存在する可能性があります。(※詳細は後述しますが、必ず最新情報の確認が必要です)
しかし、この補助金を「計画の前提」として組み込んでしまうことには、大きな危険が伴います。
補助金は「もらえたらラッキー」が大原則
なぜ補助金をあてにしすぎるのが危険なのか?理由はいくつかあります。
- 厳しい「条件」の壁:
- 補助金には、必ず対象となる物件の条件(築年数、状態、立地など)や、所有者の条件(所得制限など)、工事の内容、活用方法など、非常に細かい要件が定められています。
- 「うちの空き家も対象になるだろう」と安易に考えていても、いざ申請しようとしたら条件を満たしていなかった…ということは、本当によくある話です。
- 例えば、「耐震基準を満たしていない危険な空き家の解体」が対象だったり、「移住者向けの改修」が対象だったり、特定の目的に限定されていることが多いです。
- 限られた「予算」と「期間」:
- 補助金は、税金などを原資としているため、当然ながら予算に限りがあります。
- 申請期間が設けられており、その期間内に申請しなければなりません。
- 先着順で受付され、予算がなくなり次第終了、というケースも非常に多いです。のんびりしている間に締め切られてしまう可能性も。
- 年度ごとに制度が見直されるため、今年度あった制度が来年度もあるとは限りません。
- 煩雑な「手続き」のハードル:
- 補助金の申請には、様々な書類(申請書、見積書、図面、住民票、納税証明書など)を揃える必要があり、手続きが非常に煩雑で時間がかかる場合があります。
- 書類に不備があれば、再提出を求められ、さらに時間がかかります。
- 工事前に申請が必要な場合が多く、交付決定を待たずに工事を始めてしまうと、補助金の対象外になってしまうこともあります。
- 「補助率」と「上限額」の罠:
- 補助金は、かかった費用の「全額」が支給されるわけではありません。「補助率(費用の1/2、1/3など)」と「上限額(最大〇〇万円まで)」が定められています。
- 例えば、「解体費用の半額補助、上限50万円」という制度の場合、解体費用が300万円かかったとしても、補助されるのは最大50万円まで、ということです。残りの250万円は自己負担になります。
- この点を勘違いしていると、資金計画が大きく狂ってしまいます。
「補助金頼み」の計画が破綻する時
「補助金が出るはずだから、解体業者と契約しよう」
「補助金を見込んで、リフォームのローンを組もう」
このように、補助金ありきで計画を進めてしまうと、
- いざ申請したら、対象外だった…
- 申請が間に合わず、受付が終了していた…
- 審査に通らず、不採択になった…
- 思ったよりも補助額が少なかった…
といった場合に、計画そのものが頓挫してしまったり、想定外の自己負担が発生して資金繰りに窮したりする可能性があります。
特に、「解体費用〇〇万円、補助金で半分出るから、自己負担は△△万円だな」と考えていたのに、補助金が出なければ、〇〇万円全額が自己負担としてのしかかってきます。
****
補助金制度は、うまく活用できれば非常にありがたいものです。
しかし、それはあくまで「プラスアルファの支援」と捉えるべき。
補助金がなくても計画が実行できるような、堅実な資金計画を立てることが、失敗しないための鉄則です。
補助金に関する情報は、必ず最新の公式情報を確認し、過度な期待は禁物、と心得ておきましょう。
…いかがでしたでしょうか?
「放置」「高額リフォーム」「補助金過信」。
これら3つの罠は、空き家問題で悩む多くの人が、つい足を踏み入れてしまいがちな落とし穴です。
皆さんがこれらの罠にはまらず、より確実で、負担の少ない解決策を見つけられるよう、次の章では、具体的な解決策の選択肢と、それぞれのメリット・デメリットをさらに詳しく比較検討していきたいと思います。
失敗しない空き家対策、一緒に考えませんか?
「うちの計画、大丈夫かな?」「こんな場合はどうすれば?」少しでも不安があれば、専門家の視点からアドバイスします。LINEでのご相談は無料です。
【徹底比較】売却?賃貸?解体?留萌市の空き家、あなたに合う解決策はどれ?
さて、空き家を放置するリスクと、よくある失敗パターンを理解した上で、いよいよ具体的な解決策の選択肢を詳しく見ていきましょう。
一般的に考えられる主な方法は、「売却」「賃貸」「解体」の3つです。
それぞれの方法には、メリットもあればデメリットもあります。
また、あなたの空き家の状況(立地、築年数、状態など)や、あなた自身の意向(早く手放したい、収益を得たい、費用をかけたくないなど)によって、最適な選択肢は変わってきます。
ここでは、それぞれの方法について、
- どんな方法なのか?(概要)
- メリットとデメリット
- 具体的な手順
- かかる費用や税金
- 留萌市で考える上でのポイント
- 注意すべき点
といった観点から、できるだけ詳しく解説していきます。
ご自身の状況と照らし合わせながら、どの方法が最も合っているか、じっくり比較検討してみてください。
選択肢①:空き家を「売却」する ~手放して負担から解放されたいあなたへ~

まず考えられるのが、空き家を第三者に売却してしまう方法です。
売却が完了すれば、あなたは空き家の所有者ではなくなり、管理の手間や固定資産税の支払い義務、将来的なリスクから完全に解放されます。
ある意味、最もシンプルで分かりやすい解決策と言えるかもしれません。
売却のメリット
- 管理・維持の負担がゼロになる:日々の見回り、草むしり、修繕、固定資産税の支払いなど、すべての負担から解放されます。精神的な負担も軽くなるでしょう。
- まとまった現金収入の可能性:売却が成立すれば、売却代金という形で現金を得ることができます。(ただし、価格は物件や市場状況によります)
- 将来的なリスクの完全回避:特定空家指定、倒壊、近隣トラブルといった、空き家を所有し続けることによる将来的なリスクを根本的になくすことができます。
- 相続問題の解決(の場合も):売却して現金化することで、相続人間での遺産分割が容易になる場合があります。
売却のデメリット
- 希望価格で売れるとは限らない:特に地方都市や築古物件の場合、買い手を見つけること自体が難しかったり、見つかっても想定よりかなり低い価格になったりする可能性があります。
- 売却までに時間がかかる:すぐに買い手が見つかるとは限りません。数ヶ月、場合によっては年単位で時間がかかることも覚悟が必要です。その間も管理や税金の負担は続きます。
- 諸費用がかかる:仲介手数料、印紙税、登記費用、場合によっては測量費や残置物処分費、解体費など、売却するために様々な費用が発生します。
- 税金がかかる場合がある:売却によって利益(譲渡所得)が出た場合、所得税・住民税が課税されます。
- 思い出の場所を手放す寂しさ:感情的な側面ですが、大切な家を手放すことへの抵抗感や寂しさを感じる方も少なくありません。
- 契約不適合責任のリスク:売却後、建物や土地に隠れた欠陥(契約内容に適合しない不具合)が見つかった場合、買主から修補や損害賠償、契約解除などを求められる可能性があります。(一定期間、責任を負う特約を付けることが多い)
売却の具体的な種類:「仲介」と「買取」
売却には、大きく分けて2つの方法があります。
- 不動産仲介業者に依頼する(仲介)
- 概要:不動産会社に買主を探してもらう方法です。広く買主を募集するため、市場価格に近い価格で売れる可能性があります。
- メリット:より高い価格で売れる可能性がある。
- デメリット:売れるまでに時間がかかる可能性がある。仲介手数料がかかる(売却価格の3%+6万円+消費税が上限)。
- 不動産買取業者に直接買い取ってもらう(買取)
- 概要:不動産会社(買取業者)が直接、あなたの空き家を買い取る方法です。
- メリット:短期間で現金化できる。仲介手数料がかからない。現状のまま(リフォームや残置物処分不要)で買い取ってくれる場合が多い。契約不適合責任が免除されることが多い。
- デメリット:買取価格は、仲介で売る場合の市場価格より低くなる(一般的に市場価格の5~8割程度と言われる)ことが多い。
どちらが良いかは、あなたの状況や優先順位(価格重視か、スピード重視かなど)によって異なります。
売却(仲介の場合)の一般的な手順
ここでは、より一般的な「仲介」による売却の流れを見てみましょう。
ステップ1:不動産会社選びと査定依頼
まずは、信頼できる不動産会社を探し、空き家の査定を依頼します。
複数の会社に査定を依頼(相見積もり)し、査定価格だけでなく、担当者の対応や販売戦略なども比較検討しましょう。
留萌市内の不動産事情に詳しい地元の会社に相談するのも良いでしょう。
ステップ2:媒介契約の締結
売却を依頼する不動産会社が決まったら、媒介契約を結びます。
契約には「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類があり、それぞれ特徴(自分で買主を見つけられるか、複数の会社に依頼できるか、報告義務など)が異なります。よく説明を聞いて選びましょう。
ステップ3:販売活動の開始
不動産会社が、広告(チラシ、インターネット掲載など)や、他の不動産会社への情報提供(レインズ登録など)を通じて、買主を探します。
ステップ4:内覧対応
購入希望者が見つかったら、実際に空き家を見てもらう「内覧」に対応します。
遠方に住んでいる場合は、不動産会社に鍵を預けて対応してもらうことも可能です。
ステップ5:購入申込みと条件交渉
買主から購入申込書(買付証明書)が提出されたら、売却価格や引き渡し時期などの条件を交渉します。
ステップ6:売買契約の締結
条件がまとまったら、買主と売買契約を締結します。
この際、買主から手付金を受け取ることが一般的です。契約内容(特に契約不適合責任に関する取り決めなど)はしっかり確認しましょう。
ステップ7:決済と引き渡し
契約で定められた日時に、買主から残りの代金を受け取り(決済)、同時に空き家の鍵や関連書類を引き渡します。
所有権移転登記などの手続きも、司法書士の立ち会いのもと、この日に行われるのが一般的です。
以上が、大まかな流れです。通常、査定から引き渡しまで、早くても3ヶ月~半年程度、長ければ1年以上かかることもあります。
売却にかかる費用と税金
売却には、様々な費用がかかります。
- 仲介手数料:不動産会社に支払う成功報酬。売買価格に応じて変動(上限あり)。買取の場合は不要。
- 印紙税:売買契約書に貼る収入印紙代。売買価格によって税額が変わる。
- 登記費用:
- 所有権移転登記費用(通常は買主負担だが、一部負担の場合も)。
- 抵当権抹消登記費用(住宅ローンなどが残っている場合)。司法書士への報酬も必要。
- 相続登記費用(相続登記が未了の場合、売却前に必須)。
- 測量費用:土地の境界が不明確な場合、土地家屋調査士による測量が必要になることも。
- 残置物処分費用:家の中に家具や荷物が残っている場合、その処分費用。
- 解体費用:古家付き土地として売却するのではなく、更地にして売却する場合。
- その他:引っ越し費用(もし住んでいた場合)、ハウスクリーニング費用など。
また、売却によって利益(譲渡所得)が出た場合には、税金がかかります。
- 譲渡所得税・住民税:
- 計算式:譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)
- 税率:所有期間によって異なる(5年以下は短期譲渡所得、5年超は長期譲渡所得)。長期の方が税率は低い。
- 特別控除:マイホームを売却した場合など、一定の要件を満たせば、最高3,000万円の特別控除が受けられる場合がある(空き家にも適用される特例あり)。詳細は税務署や税理士にご確認ください。
売却価格からこれらの費用や税金を差し引いたものが、最終的な手取り額となります。
留萌市で売却を考える上でのポイント
留萌市で空き家を売却する場合、いくつか考慮すべき点があります。
- 市場動向の把握:留萌市の不動産市場は、札幌などの大都市圏とは異なります。人口減少や高齢化の影響もあり、一般的に買い手市場(売主有利ではない)と言えるかもしれません。現実的な売却価格や売却期間を把握することが重要です。地元の不動産会社に相談し、最新の市場動向を確認しましょう。
- 物件の魅力の見極め:どんな物件であれば売れやすいでしょうか?留萌駅から近い、状態が良い、眺望が良い(海の見える物件など)、駐車スペースがある、といった点はプラス要因になる可能性があります。逆に、築年数が古い、再建築不可、アクセスが不便、といった物件は、売却が困難になる可能性が高いです。
- ターゲット層の設定:誰に買ってもらいたいかを考えることも有効です。地元で家を探している人? 札幌圏からの移住希望者? 釣りやアウトドア目的のセカンドハウス需要? ターゲット層に合わせたアピールや価格設定が必要になるかもしれません。
- 価格設定の重要性:周辺の相場からかけ離れた高い価格設定では、いつまで経っても買い手は現れません。かといって、安易に安売りする必要もありません。不動産会社の査定価格を参考にしつつ、現実的な価格を設定することが重要です。場合によっては、価格交渉に応じる柔軟性も必要でしょう。
- 空き家バンクの活用:留萌市が運営している(または連携している)「空き家バンク」に登録するのも一つの方法です。市のウェブサイトなどで情報を確認してみましょう。移住希望者など、特定のニーズを持つ買い手が見つかる可能性があります。
- 古家付き土地としての売却:建物が古い場合、無理にリフォームして売るよりも、「古家付き土地」として、建物の価値はほぼゼロ(あるいはマイナス)と割り切り、土地の価格で売却する方が現実的な場合もあります。解体費用を買主負担とするか、売主負担とするかは交渉次第です。
売却の注意点まとめ
- 査定価格はあくまで目安。鵜呑みにしない。
- 売却期間が長期化する可能性も覚悟する。
- 仲介手数料以外にも諸費用がかかることを理解しておく。
- 契約不適合責任について、契約内容をよく確認する。
- 税金について、事前に確認・相談しておく。
- 買取は早いが価格は安くなる傾向。メリット・デメリットを理解する。
売却は、うまく行けば負担から解放される有効な手段ですが、必ずしも簡単ではない、ということを理解しておく必要があります。
売却について、もっと詳しく聞いてみたい
「うちの家、売れるかな?」「仲介と買取、どっちがいい?」「費用は結局いくらかかる?」など、売却に関する疑問にお答えします。LINEで気軽にご質問ください。
選択肢②:空き家を「賃貸」に出す ~家賃収入で維持・活用したいあなたへ~

次に考えられるのが、空き家を誰かに賃貸に出し、家賃収入を得る方法です。
家を手放すことなく活用でき、維持費を賄える可能性があるのが魅力です。
賃貸のメリット
- 継続的な収入の可能性:借り手が見つかれば、毎月安定した家賃収入を得ることができます。固定資産税などの維持費をカバーし、プラスの収益になる可能性も。
- 家を手放さなくて済む:将来的に自分や家族が住む可能性がある場合や、愛着のある家を手放したくない場合に有効な選択肢です。
- 家の劣化抑制:人が住むことで、換気や通水が行われ、建物の劣化をある程度防ぐ効果が期待できます。定期的な管理も行われやすくなります。
- 地域の活性化貢献:空き家が活用されることで、地域の人口維持や活性化に繋がる可能性があります。
賃貸のデメリット
- 空室リスク:借り手が常に見つかるとは限りません。空室期間中は家賃収入がゼロになり、維持費は持ち出しとなります。
- 初期費用(リフォーム等):多くの場合、人に貸し出せる状態にするために、リフォームや修繕費用がかかります。特に水回り(キッチン、風呂、トイレ)の改修は高額になりがちです。
- 管理の手間:家賃の集金、入居者からのクレーム対応、設備の故障対応、退去時の手続きや原状回復など、大家としての業務が発生します。不動産管理会社に委託することも可能ですが、管理手数料(通常、家賃の5%程度)がかかります。
- 家賃滞納リスク:入居者が家賃を滞納するリスクがあります。督促や法的手続きが必要になる場合も。
- 入居者トラブルのリスク:騒音、ゴミ出しルール違反、無断でのペット飼育や改造など、入居者との間でトラブルが発生する可能性があります。
- 建物の老朽化と修繕費:賃貸に出していても、建物は経年劣化します。給湯器の交換、屋根や外壁の修繕など、将来的にまとまった修繕費用が発生する可能性があります。
- 確定申告の手間:家賃収入は不動産所得として、確定申告を行う必要があります。
賃貸の具体的な種類:「普通賃貸借」と「定期賃貸借」
賃貸借契約には、主に2つの種類があります。
- 普通賃貸借契約
- 概要:契約期間(通常2年)が満了しても、貸主側に正当な事由がない限り、借主が希望すれば契約が更新されるのが原則の契約形態。借主の居住権が強く保護されています。
- メリット:長期的に安定した入居が見込める可能性がある。
- デメリット:貸主側の都合(例えば、将来自分で住みたいなど)で退去してもらうのが難しい場合がある。
- 定期賃貸借契約
- 概要:契約期間の満了によって、更新されることなく契約が確定的に終了する契約形態。再契約は可能ですが、貸主・借主双方の合意が必要です。
- メリット:契約期間を明確に定められるため、「将来的に自分で使う予定がある」「期間限定で貸したい」といった場合に有効。貸主側の計画が立てやすい。
- デメリット:借主にとっては不安定な契約となるため、普通賃貸借に比べて借り手が見つかりにくい、あるいは家賃を低めに設定する必要がある場合がある。
どちらの契約形態を選ぶかは、貸主の意向や物件の特性によって検討します。
賃貸に出すまでの一般的な手順
空き家を賃貸に出すまでの流れを見てみましょう。
ステップ1:リフォーム・修繕・クリーニング
まず、人が安全・快適に住める状態にする必要があります。
必要に応じて、水回り、内装、設備の修繕や交換、ハウスクリーニングを行います。
どこまで手を入れるかは、予算やターゲット層、周辺の競合物件とのバランスを考えて決定します。
ステップ2:賃貸条件の設定
家賃、敷金・礼金、契約期間、管理費、ペット飼育の可否など、賃貸の条件を決定します。
家賃設定は、周辺の相場や物件の状態を考慮して、慎重に行う必要があります。不動産会社に相談するのが一般的です。普通賃貸借か定期賃貸借かもここで決めます。
ステップ3:入居者募集
不動産会社に依頼して、インターネット広告や店頭での紹介などを通じて入居者を募集します。
自分で「ジモティー」などのサイトを利用して募集することも可能ですが、手間やリスクも伴います。
ステップ4:入居審査
入居希望者から申し込みがあったら、家賃支払い能力や人柄などを確認する入居審査を行います。
保証会社への加入を条件とすることも一般的です。
ステップ5:賃貸借契約の締結
審査に通ったら、賃貸借契約を結びます。
契約書の内容(特に禁止事項や退去時の原状回復についてなど)は、後々のトラブルを防ぐために非常に重要です。重要事項説明もしっかり行います。
ステップ6:入居開始と管理
鍵を引き渡し、入居開始となります。
入居中は、家賃の集金、入居者からの問い合わせやクレームへの対応、設備の故障時の修繕手配など、大家としての管理業務が発生します。
これらの業務を不動産管理会社に委託することも可能です。
賃貸経営は、収入が得られる可能性がある一方で、継続的な手間と責任が伴う事業であることを理解しておく必要があります。
賃貸にかかる費用と税金
賃貸経営には、初期費用と運営費用がかかります。
- 初期費用:
- リフォーム・修繕費用
- ハウスクリーニング費用
- 募集広告費(不動産会社に依頼する場合、家賃の1ヶ月分程度が相場)
- 鍵交換費用 など
- 運営費用(ランニングコスト):
- 固定資産税・都市計画税
- 管理委託手数料(管理会社に委託する場合)
- 共有部分の光熱費・清掃費(アパートなどの場合)
- 火災保険料・地震保険料
- 設備の修繕・交換費用(給湯器、エアコンなど、経年劣化によるもの)
- 退去時の原状回復費用(借主負担分を除く)
- 確定申告費用(税理士に依頼する場合) など
税金については、家賃収入からこれらの必要経費を差し引いたものが不動産所得となり、他の所得(給与所得など)と合算して所得税・住民税が課税されます。
不動産所得が赤字になった場合は、他の黒字所得と損益通算することで、節税に繋がる場合もあります。
確定申告は必須ですので、帳簿付けなども必要になります。
留萌市で賃貸を考える上でのポイント
留萌市で空き家を賃貸に出す場合、以下の点を考慮すると良いでしょう。
- 賃貸需要の見極め:留萌市の賃貸市場は、どのような層(単身者、ファミリー、高齢者、学生、季節労働者、移住希望者など)からの需要があるのか、不動産会社などにヒアリングして把握することが重要です。ターゲット層に合わせた物件の整備や家賃設定が必要です。
- 家賃相場の調査:周辺の類似物件の家賃相場を調べ、競争力のある家賃を設定する必要があります。高すぎると借り手が見つからず、安すぎると収益性が低くなります。
- 物件の状態とリフォーム範囲:築年数が古い場合、どこまでリフォームに費用をかけるべきか、慎重な判断が必要です。最低限の設備(風呂、トイレ、キッチン、給湯器など)が使えることは必須ですが、過剰なリフォームは投資回収を困難にします。「現状に近い状態」で安めの家賃で貸し出す、という選択肢も考えられます。
- 管理体制の確保:遠方に住んでいる場合は特に、現地の不動産管理会社に管理を委託することが現実的でしょう。信頼できる管理会社を見つけることが重要です。管理手数料はかかりますが、手間やトラブル対応の負担を軽減できます。
- 短期賃貸の可能性:留萌市は観光資源(黄金岬、海の幸など)や釣りスポットもあるため、通常の長期賃貸だけでなく、観光客や釣り客向けの短期賃貸(民泊に近い形ですが、旅館業法の許可が必要になる場合があります)や、季節的な需要(例えば、冬場の作業員向けなど)に対応する、といった活用も考えられるかもしれません。ただし、安定性は低くなります。
- 地域貢献型賃貸:NPO法人や社会福祉法人などと連携し、高齢者向けの見守り付き住宅や、障がい者のグループホーム、子育て支援の拠点など、地域貢献に繋がる形で活用するという方法もあります。家賃収入は低めになるかもしれませんが、社会的な意義があり、借り手が見つかりやすい可能性もあります。
賃貸の注意点まとめ
- 空室リスク、家賃滞納リスクを常に意識する。
- リフォーム費用は投資。回収計画をしっかり立てる。
- 管理の手間(または委託費用)がかかることを覚悟する。
- 入居者トラブルへの対応が必要になる場合がある。
- 確定申告が必要。経費の領収書などをきちんと保管する。
- 契約形態(普通or定期)をよく検討する。
賃貸は、うまくいけば継続的な収入源となりますが、事業である以上、リスクと手間が伴うことを十分に理解しておく必要があります。
賃貸経営、うちの家でもできる?
「リフォーム費用はどれくらい?」「留萌で借り手はつく?」「管理はどうすれば?」賃貸に関する具体的な疑問や不安にお答えします。お気軽にご相談ください。
選択肢③:空き家を「解体」する ~更地にして次のステップへ~

建物が著しく老朽化している、活用が難しい、あるいは土地として売却・利用したい、といった場合に選択されるのが、建物を解体して更地にすることです。
ある意味、物理的に問題を「なくす」方法と言えます。
解体のメリット
- 建物の管理負担・リスクからの解放:建物の維持管理、修繕、倒壊、特定空家指定といった心配が一切なくなります。
- 土地として活用しやすくなる:更地になることで、売却しやすくなったり、駐車場や資材置き場、自家用の菜園など、土地としての活用(または売却)の選択肢が広がります。(ただし、需要があるかは別問題)
- 景観・衛生面の改善:荒れた建物がなくなることで、景観が改善され、衛生上の問題も解消されます。近隣住民からの印象も良くなるでしょう。
- 精神的な区切り:物理的に建物がなくなることで、気持ちの整理がつき、次のステップに進みやすくなるという側面もあります。
解体のデメリット
- 高額な解体費用:最も大きなデメリットです。木造一軒家でも、立地や構造、アスベストの有無などによりますが、一般的に100万円~数百万円単位の費用がかかります。
- 固定資産税の増額リスク:建物がなくなると、土地に対する固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなり、税額が更地になる前より高くなる(最大で6倍)可能性が高いです。
- 更地の管理は必要:解体して更地にしても、土地の所有権は残ります。そのまま放置すれば雑草が生い茂り、結局、近隣への迷惑や不法投棄の問題が発生するため、定期的な草刈りなどの管理は必要です。
- 思い出の消失:建物が物理的に完全になくなってしまうため、寂しさや喪失感を覚える方もいます。
- 解体後の活用が決まっていないと負担増:更地にしたものの、売却もできず、活用もできなければ、税金と管理の手間だけがかかり続ける「負の資産」になりかねません。
解体の一般的な手順
解体工事は、以下のような流れで進められます。
ステップ1:解体業者選びと見積もり依頼
まずは、信頼できる解体業者を探します。
インターネット検索や、地元の不動産会社からの紹介などで複数社をリストアップし、現地調査の上で見積もりを依頼します。
見積もりは必ず複数社から取り、金額だけでなく、工事内容、工期、廃材の処分方法、保険加入状況などを比較検討します。
ステップ2:契約の締結
依頼する業者が決まったら、工事請負契約を結びます。
契約書の内容(工事範囲、金額、支払い条件、工期、近隣への配慮、アスベスト調査・除去の有無など)をしっかり確認しましょう。
ステップ3:事前準備と届け出
工事開始前に、近隣住民への挨拶回りを行います。
また、建設リサイクル法に基づく届け出や、道路使用許可(必要に応じて)などの手続きが必要です(通常は業者が代行)。
電気、ガス、水道、電話などのライフラインの停止・撤去手続きも行います。
ステップ4:解体工事の実施
足場や養生シートを設置し、騒音、振動、粉塵に配慮しながら、建物の解体工事を進めます。
内装材→屋根→壁→柱・梁→基礎の順に解体していくのが一般的です。
工事中は、業者の指示に従い、安全管理に注意します。
ステップ5:廃材の分別・搬出・処分
解体によって発生した木材、コンクリートガラ、金属などの廃材を、法律に従って適切に分別し、処分場へ搬出します。
不適切な処分(不法投棄など)を行う悪徳業者もいるため、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の発行を確認するなど、注意が必要です。
ステップ6:整地
建物の基礎部分も撤去した後、土地を平らにならす「整地」作業を行います。
どの程度のレベルまで整地するか(粗整地か、砕石を敷くかなど)は、契約内容や今後の土地利用によって異なります。
ステップ7:建物滅失登記の申請
建物が解体されたら、1ヶ月以内に法務局へ建物滅失登記を申請する必要があります。
これを怠ると10万円以下の過料に処される可能性があります。
通常は土地家屋調査士に依頼します(費用が発生)。
解体工事の期間は、建物の規模や構造、天候などによりますが、一般的に木造一軒家で1週間~2週間程度です。
解体にかかる費用と税金
解体費用は、様々な要因で変動しますが、費用の内訳は主に以下のようになります。
- 本体工事費:建物の解体作業そのものにかかる費用。構造(木造、鉄骨造、RC造)や延床面積、立地(重機が入りやすいかなど)によって大きく変わる。木造で坪3万円~5万円程度が目安と言われるが、地域や業者によって差がある。
- 付帯工事費:建物本体以外の解体費用。例:ブロック塀、門、カーポート、庭石、樹木などの撤去費用。
- 廃材処分費:解体で出た廃材を処分するための費用。廃材の種類や量によって変動。アスベストが含まれている場合は、除去・処分に別途高額な費用がかかる。
- 諸経費:足場・養生シート設置費、重機回送費、近隣対策費、官公庁への届け出費用、業者の利益など。
留萌市での解体費用については、地元の複数の解体業者に見積もりを取って相場を確認することが最も確実です。積雪期は作業が難しくなり、費用が割高になる可能性も考慮しましょう。
税金については、前述の通り、建物がなくなることで固定資産税・都市計画税の住宅用地特例が解除され、翌年度から税額が上がる可能性が高いことを念頭に置く必要があります。
留萌市で解体を考える上でのポイント
- 業者選びは慎重に:複数の業者から見積もりを取り、価格だけでなく、実績、評判、保険加入状況、対応などを総合的に判断しましょう。不法投棄などを行う悪徳業者に注意が必要です。
- アスベスト調査:一定規模以上の解体工事や、特定の建材(主に2006年以前のもの)を使用している場合、アスベスト(石綿)の使用有無の事前調査が義務付けられています。アスベストが検出された場合、除去費用が別途高額になる可能性があります。
- 近隣への配慮:工事中は騒音、振動、粉塵などで近隣に迷惑がかかります。事前に十分な説明と挨拶を行い、トラブルを避けるよう努めましょう。業者の対応も重要です。
- 冬季工事の検討:留萌市の冬は積雪が多く、厳しい寒さが続きます。冬季の解体工事は、作業効率の低下や安全確保の難しさから、費用が割高になったり、工期が延びたりする可能性があります。可能であれば、雪のない時期に計画するのが望ましいでしょう。
- 解体後の土地活用計画:解体する前に、更地になった土地をどうするのか、具体的な計画を立てておくことが非常に重要です。「とりあえず更地に」と考えても、売却も活用もできず、税金と管理費だけがかかり続ける…という事態になりかねません。売却の見込み、駐車場の需要、自分で使う予定などを事前に検討しましょう。
- 滅失登記を忘れずに:解体後1ヶ月以内の建物滅失登記は法律上の義務です。忘れずに行いましょう。
解体の注意点まとめ
- 解体費用は高額。必ず複数社から見積もりを取る。
- 固定資産税が上がる可能性が高いことを理解しておく。
- 更地にしても管理(草刈りなど)は必要。
- 解体後の土地活用計画を事前に立てておく。
- アスベスト調査が必要な場合がある。
- 近隣への配慮を十分に行う。
- 建物滅失登記を忘れずに行う。
解体は、物理的に問題をなくす最終手段となり得ますが、費用負担が大きく、税金面でのデメリットもあるため、慎重な判断が必要です。
【比較まとめ】あなたにとって最適な選択肢は?
ここまで、「売却」「賃貸」「解体」という3つの一般的な解決策について、詳しく見てきました。
改めて、それぞれの特徴と、どんな人に向いているかをまとめてみましょう。
| 解決策 | 主なメリット | 主なデメリット | 特にこんな人におすすめ |
|---|---|---|---|
| 売却 | 管理・税負担から解放 現金収入の可能性 将来リスク回避 | 希望価格で売れない可能性 時間がかかる 諸費用・税金がかかる 契約不適合責任リスク | ・早く手放してスッキリしたい人 ・管理や税金の負担をなくしたい人 ・現金化を優先したい人 ・家への執着が少ない人 |
| 賃貸 | 継続的な家賃収入 家を手放さずに済む 家の劣化抑制効果 | 空室・滞納リスク リフォーム費用負担 管理の手間・責任 入居者トラブルリスク | ・家を手放したくない人 ・初期投資がある程度可能な人 ・賃貸経営のリスクを許容できる人 ・安定収入を得たい人 |
| 解体 | 建物管理・リスクから解放 土地活用・売却の可能性 景観・衛生面の改善 | 解体費用が高額 固定資産税増額リスク 更地の管理が必要 土地活用計画が必須 | ・建物が著しく老朽化している人 ・活用が困難な立地の人 ・解体費用を負担できる人 ・土地として活用・売却したい人 |
そして、これらの一般的な選択肢を進める上で、相談先となる専門家と、私(藤本)にご相談いただいた場合の違いを、再度比較表で確認してみましょう。
| 相談先 | ①主な役割・強み | ②限界・弱み | ③【藤本に依頼した場合】 |
|---|---|---|---|
| 不動産仲介業者 | 売買・賃貸の仲介 市場価格の査定 | 売れない/貸せない可能性 仲介手数料が発生 活用提案は限定的 | 負担ゼロ活用提案 可 仲介業務は行わない |
| 賃貸管理会社 | 入居者募集・管理代行 家賃回収・トラブル対応 | 空室リスクはオーナー負担 管理手数料が発生 大規模修繕は別途費用 | 必要最低限の修繕費 藤本負担(※) 空室リスク等考慮した活用提案(※) |
| 不動産買取業者 | 早期現金化が可能 現状のまま買取も | 買取価格は市場価格より低い 活用より処分が目的 | まず活用優先 引取りも負担軽減第一 |
| 解体業者 | 建物の解体工事 更地にする | 解体費用が高額 解体後の土地活用は別問題 活用提案はしない | まず活用検討 解体でも「半額負担引取り」 |
| 建築士・リフォーム会社 | 建物の診断・設計 リフォーム・リノベーション | 費用が高額になりがち 市場ニーズより設計優先も 賃貸経営の知識は別 | 市場ニーズ・費用対効果重視 最低限リフォーム 藤本負担で実施可 |
| 空き家相談窓口(行政など) | 一般的な情報提供 補助金制度の案内 | 個別具体的な解決策は限定的 実行支援は行わない 営利目的の提案は不可 | 相談無料 実行までワンストップ |
| 空き家専門コンサルタント | 多角的な活用提案 専門家ネットワーク | 相談料・コンサル料が高額な場合も 提案だけで実行は別の場合も | 相談無料 実行までワンストップ |
(※)「必要最低限の修繕」とは、残置物処分、簡単な清掃、雨漏り等の応急処置、床の危険箇所補修、給湯器設置/交換などを指します。大規模リフォームは行いません。
(※)「空室リスク等考慮した活用提案」とは、必ずしも賃貸(居住用)に限定せず、倉庫利用など柔軟な活用を探ることを意味します。空室保証(サブリース)ではありません。
どうでしょうか?
一般的な解決策には、それぞれメリットがある一方で、費用負担やリスク、手間といったデメリットも無視できません。
「どの方法も、ちょっと決め手に欠けるな…」
「もっと負担の少ない方法はないのだろうか?」
もしあなたがそう感じているなら、ぜひ、次の章でお話しする私の提案に注目してみてください。
これらの一般的な方法とは異なる、「オーナー様の負担を限りなくゼロに近づける」ことを目指した、新しい解決策をご提案します。
一般的な方法では解決できない…?
売却も賃貸も解体も、どれもハードルが高いと感じていませんか? 大丈夫です、まだ諦めないでください。あなたの状況に合った、もっと良い方法が見つかるかもしれません。まずはLINEでご相談を。
【藤本流】費用・手間・心配事を最小限に!留萌市の空き家、負担ゼロ解決への3つの道筋
さて、ここからが本題です。
一般的な「売却」「賃貸」「解体」では、どうしても費用や手間、リスクといった壁が立ちはだかることが多い…。
「もっと負担なく、この空き家問題を解決する方法はないのだろうか?」
そうお考えのあなたに、私、藤本がご提案したいのが、以下の3つの方法です。
これは、私が全国の空き家オーナーさんと向き合う中で、そしてパートナーである「日本の空き家研究所」代表の竹田さんの豊富な経験や知見(竹田さんは全国で100軒以上の空き家を実際に管理・再生されています!)から学びながら構築してきた、「オーナー様の負担を限りなくゼロに近づける」ことを最優先に考えたアプローチです。
私の活動は、単なるビジネスではありません。
半分は趣味、ライフワークであり、「一件でも多くの空き家を、負担なく未来へ繋ぎたい」「空き家問題で悩む人を一人でも減らしたい」という想いが原動力になっています。
ですから、これからお話しする方法は、もしかしたら一般的な不動産業者の提案とは少し違うかもしれません。
でも、きっとあなたの状況に寄り添える部分があるはずです。
提案①:究極の手間ゼロ・費用ほぼゼロ!「まるっと管理代行」で未来へ繋ぐ

まず最初にご提案したいのが、この「まるっと管理代行」です。
言葉の通り、あなたの空き家の管理と活用を、文字通り「まるっと」私が代行しますよ、といものです。
「それって、普通の賃貸管理と何が違うの?」
そう思われるかもしれませんね。決定的な違いは、オーナー様の「手間」と「費用負担」を、極限までゼロに近づける点にあります。
「藤本の管理代行」は、ここが違います!
一般的な賃貸経営では、貸し出す前にリフォーム費用がかかったり、入居者募集の手間、家賃滞納のリスク、管理会社への手数料支払いなど、様々な負担がオーナー様にのしかかります。
しかし、私の管理代行は、これらの負担をできる限り私が引き受けることを目指しています。
特徴1:現状のまま、が基本!高額リフォームは不要です
「貸すためには、まず数百万円かけてリフォームしないと…」
そんな心配は、基本的に不要です。
私の考え方は、「今ある状態を活かして、最低限の手入れで貸し出す」が原則。
もちろん、安全に関わる重大な問題(例えば、雨漏りがひどくて生活できない、床が抜け落ちそうで危険など)があれば、応急的な修繕は行います。
しかし、壁紙を張り替えたり、キッチンやお風呂を最新式に入れ替えたり、といった見栄えを良くするための高額なリフォームは、原則として行いません。
なぜなら、それがオーナー様の費用負担に繋がってしまうからです。
「こんなボロボロの状態で、借りる人なんているの?」
そう思うかもしれませんが、意外と「安く借りられるなら、多少古くても気にしない」「自分でDIYして好きに使いたい」というニーズもあるんです。
大切なのは、物件の状態に合った利用者さんを見つけることだと考えています。
特徴2:面倒な管理業務は、すべて藤本にお任せ!
空き家の管理には、本当に様々な手間がかかります。
- 定期的な見回り、換気、通水
- 庭の草むしり、樹木の剪定
- 簡単な清掃
- 利用者さん(入居者・テナント)探し
- 内覧の対応
- 賃貸借契約の手続き
- 家賃の集金、送金
- 入居中のクレームや問い合わせへの対応
- 設備の故障時の修繕手配
- 退去時の立ち会い、原状回復の確認
- 近隣住民とのコミュニケーション
これらの煩わしい業務は、すべて私(藤本)が責任をもって行います。
あなたは、基本的に何もしなくて大丈夫。
遠方に住んでいても、忙しくて時間がなくても、安心して任せてもらえます。
定期的に状況報告はさせていただきますので、ご安心ください。
特徴3:最低限の修繕費用は、藤本が負担します(※)
「現状のまま」が基本とはいえ、安全に利用してもらうために、どうしても最低限の修繕が必要になる場合があります。
例えば、
- 残置物の処分:家の中に家具や荷物が大量に残っている場合、利用者さんと相談の上、不要なものを処分します。(費用は基本的に藤本負担。ただし量が多い場合は要相談)
- 簡単な清掃:最低限、人が入れる状態にするための清掃を行います。(プロのハウスクリーニングではありません)
- 雨漏りの応急処置:生活に支障が出るレベルの雨漏りは、応急的に補修します。
- 床などの危険箇所補修:床が抜けそうな箇所など、安全に関わる部分を最低限、補修します。
- 給湯器の設置・交換:お湯が出ないのは致命的なので、給湯器がない場合や故障している場合は、設置または交換します。
これらの「安全・生活に最低限必要な修繕」にかかる費用は、原則として私が負担します。
(※ただし、物件の状態や必要な修繕の規模によっては、一部ご相談させていただく場合もあります。その際は必ず事前にご説明し、ご納得いただいた上で進めます。)
これにより、オーナー様が予期せぬ出費に悩まされることを防ぎます。
【重要:やらないこと】
誤解を避けるために明記しますが、以下のような費用のかかる大規模な改修は行いません。
× プロのハウスクリーニング
× 壁紙・床材の全面張り替え
× キッチン・風呂・トイレなどの水回り設備の総交換
× 間取り変更などのリノベーション
× Wi-Fi設置、家具・家電の設置
特徴4:維持費(固定資産税等)以上の収益を目指します!
空き家を所有しているだけで、毎年かかってくる固定資産税などの維持費。
これが大きな負担になっている方も多いと思います。
私の管理代行では、私が見つけてきた利用者さんからいただく家賃収入の中から、まずはこの年間維持費(固定資産税・都市計画税など)に相当する金額を、オーナー様にお支払いすることをお約束します。
そして、もし家賃収入が維持費を上回った場合は、その超過分(利益)を、オーナー様と私とで協議の上、分配させていただきます。
つまり、あなたは空き家を所有しているだけで、負担がゼロになるどころか、プラスの収入を得られる可能性があるのです。
【注意:空室保証ではありません】
これは非常に重要な点ですが、この仕組みは「空室保証(サブリース)」ではありません。
借り手が見つからない期間や、家賃収入が維持費に満たない期間は、オーナー様への支払いは維持費相当額までとなり、超過分の分配はありません。
家賃収入が全くない場合は、維持費分のお支払いもできません。(ただし、その場合でも管理は継続します)
あくまで、私が見つけてきた利用者さんからの家賃収入が原資となる、という点はご理解ください。
しかし、一日でも早く利用者さんを見つけ、安定した収益を生み出せるよう、私が全力で営業活動を行います。
特徴5:安心の契約形態
契約は、「あなた(オーナー様)と私(藤本)」の間で管理委託に関する契約を結びます。
そして、「私(藤本)と利用者さん(入居者・テナント)」の間で賃貸借契約を結びます。
これは「転貸借(てんたいしゃく)」に近い形式です。
この形式のメリットは、あなたが利用者さんと直接やり取りする必要が一切ないことです。
家賃の請求、クレーム対応、退去時の手続きなど、すべて私が窓口となって行います。
これにより、あなたは煩わしい人間関係やトラブルから解放され、安心して任せることができます。
留萌市での具体的な活用イメージ
「留萌の古い家なんて、誰が借りるの?」
そう思われるかもしれません。
しかし、視点を変えれば、様々な可能性が見えてきます。
- 釣り・アウトドア拠点:留萌は釣りの名所としても知られています。週末やシーズン中に利用できる、安価な滞在拠点としての需要が見込めるかもしれません。荷物置き場や休憩所としても。
- 移住希望者のお試し住宅:本格的な移住の前に、数ヶ月単位で留萌での暮らしを体験したい、という方向けの「お試し移住住宅」として提供する。市の移住支援策と連携できる可能性も。
- 地域活動・交流拠点:NPO法人や地域団体と連携し、高齢者のサロン、子どもたちの居場所、趣味のサークル活動、イベントスペースなど、地域コミュニティの活性化に繋がる使い方。
- サテライトオフィス・コワーキングスペース:近年、地方でのリモートワーク需要も高まっています。静かな環境で仕事に集中したい個人事業主や、企業のサテライトオフィスとしての活用。Wi-Fi環境の整備は必要になるかもしれません。
- アーティスト・クリエイター向けアトリエ:創作活動に没頭できる、安価なアトリエや工房としての提供。「DIY可能」とすれば、借り手が自由に改装できる魅力も。
- 短期・季節労働者の住居:留萌市周辺の漁業や農業、建設業などで、季節的に人手が必要になる場合があります。そうした方々向けの短期的な住居としての活用。
- 留学生・技能実習生向けシェアハウス:もし留萌市内に大学や専門学校、あるいは実習生を受け入れる企業があれば、複数人で共同生活するシェアハウスとしての活用も考えられます。(管理体制は重要になります)
これらはほんの一例です。
物件の立地や間取り、そして地域のニーズに合わせて、最適な活用方法を一緒に探っていきましょう。
固定観念にとらわれず、柔軟な発想で可能性を探ることが大切だと、僕は考えています。
どんな空き家でも相談できますか?
「うちの家は、築50年以上でボロボロなんだけど…」
「荷物が散乱していて、足の踏み場もないくらい…」
心配いりません。どんな状態の家でも、まずは一度ご相談ください。
もちろん、建物の構造的な安全性が著しく低い場合など、物理的にお引き受けできないケースもあります。
しかし、「これはもうダメだろう」とご自身で判断してしまう前に、ぜひ私に現状を見せて(LINEで写真でもOKです!)、お話を聞かせてください。
過去には、「もう解体するしかない」と思っていた家が、意外な形で活用され、オーナー様にも喜んでいただけたケースがたくさんあります。
諦めるのは、まだ早いかもしれませんよ。
****
この「まるっと管理代行」は、あなたの空き家を、負担なく、そして価値あるものとして未来へ繋いでいくための、最も有力な選択肢の一つだと、私は確信しています。
管理代行、もっと詳しく知りたい!
「うちのケースだと、具体的にどうなるの?」「本当に費用はかからない?」どんな疑問にも丁寧にお答えします。まずはLINEで、あなたの空き家の状況を教えてください。
提案②:住めなくても価値はある!「倉庫・資材置き場」という再生術

「藤本さんの管理代行は魅力的だけど、うちの家は正直、もう人が住める状態じゃないんだよ…」
雨漏りがひどい、床が抜けている、設備がすべて使えない…。
リフォームするには莫大な費用がかかるし、かといって解体する費用も捻出できない。
そんな、いわば「居住困難」な状態の空き家。
これも、放置すればリスクが増える一方です。
しかし、ここでも諦めるのはまだ早いかもしれません。
私からの第二の提案は、「倉庫・資材置き場」として活用する、という道です。
「スペース」そのものに価値を見出す
人が住むには厳しい状態でも、「屋根があって、壁があって、ある程度の広さがある空間」、つまり「スペース」そのものには、意外な需要が眠っていることがあります。
考えてみてください。
留萌市内や近郊で活動する事業者さんや、あるいは個人の方の中にも、
- 「資材や道具を、雨風をしのげる場所に保管したい」
- 「季節的にしか使わないものを、手頃な価格で置いておきたい」
- 「作業スペースとして、多少散らかっても気兼ねなく使える場所がほしい」
といったニーズを持っている方がいるのではないでしょうか?
新品のキレイな倉庫やレンタルスペースを借りるほどの費用はかけられないけれど、安価で利用できるなら、古い建物でも構わない、という需要です。
留萌市での具体的な利用者イメージ
留萌市の産業構造やライフスタイルを考えると、以下のような利用者像が考えられます。
- 建設・土木関係の事業者:資材、工具、小型重機などの保管場所として。現場近くの一時的な拠点としても。
- 農業関係者:農機具、肥料、収穫物の一時保管場所として。特に収穫期など。
- 漁業関係者:漁網、ロープ、浮き、小型の船外機などの漁具置き場として。
- 運送・配送業者:一時的な荷物の保管・仕分けスペースとして。
- 個人事業主・職人:木工、金工、陶芸などの作業スペース兼資材置き場として。(騒音などに配慮は必要)
- 個人の趣味利用:キャンプ用品、釣り道具、バイク、タイヤ、除雪用具など、自宅には置ききれない「かさばる物」の保管場所として。
- イベント関連業者:お祭り(るもい呑涛まつりなど)で使う道具や資材の一時保管場所として。
藤本の役割は?
この「倉庫・資材置き場」としての活用も、基本的には提案①の管理代行と同じスキームで、私がサポートします。
- 利用者探し:地元の事業者ネットワークや、インターネットなどを通じて、ニーズのある利用者を探します。
- 契約・管理:賃貸借契約の締結、賃料の回収、利用者との連絡調整など、管理業務を私が行います。
- 収益分配:得られた賃料から、固定資産税などの維持費をお支払いし、超過分があれば分配を目指します。(これも空室保証ではありません)
- 最低限の安全確保:利用に際して危険がないよう、例えば崩れそうな壁の応急処置や、入口周りの整備など、必要最低限の対応を相談の上で行います。(費用は原則藤本負担)
倉庫活用のメリットと注意点
メリット:
- 解体費用をかけずに済む可能性がある。
- 居住用よりも利用者のハードルが低く、借り手が見つかりやすい場合がある。
- 最低限の収入を得て、維持費負担を軽減できる可能性がある。
- 放置によるさらなる劣化やリスクを抑えられる。
注意点:
- 賃料は、居住用として貸す場合よりも安価になる傾向がある。
- 利用目的によっては、建物の損耗が進む可能性がある。(例:重量物の搬入など)
- 利用者のマナーによっては、騒音やゴミの問題が発生する可能性もゼロではない。(契約でルールを明確化)
- 火災保険など、適切な保険への加入を検討する必要がある。
****
「もう使い道がない」と思っていた空き家が、誰かの役に立ち、わずかでも収入を生み出すかもしれない。
そんな視点で、あなたの空き家を見つめ直してみませんか?
特に、留萌市内で広い敷地がある一軒家や、元々商店や作業場だったような建物は、この活用法が適している可能性があります。
「住めない家」の活用、相談してみませんか?
「こんな状態だけど、倉庫として使える可能性はある?」「どんな人が借りてくれそう?」写真を見ながら、具体的な活用方法を一緒に検討しましょう。
提案③:最終手段、でも負担は軽く!「解体費用半額負担」での引取り
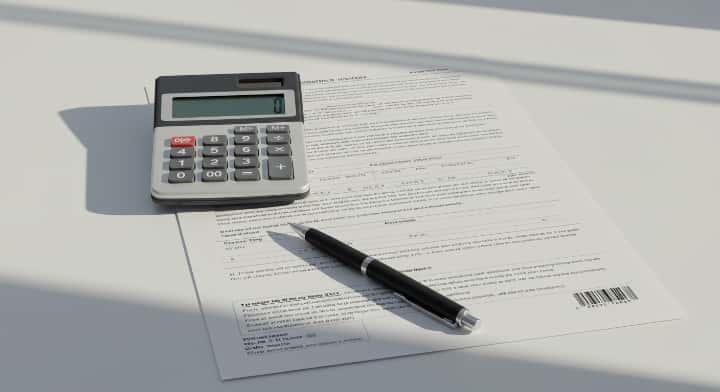
提案①の管理代行も、提案②の倉庫活用も、残念ながら難しい…。
建物が著しく損傷している、立地的にどうしても活用が見込めない、あるいは、もうとにかく一日でも早く、この空き家に関するすべての悩みから解放されたい…
そんな状況の方も、いらっしゃると思います。
様々な手を尽くしても活用が困難で、「もう解体しか道はない」となった場合。
しかし、その解体費用が高額で、捻出できない…。
そんな時のための、いわば「最後のセーフティネット」として、私がご提案できるのが、この「解体費用半額負担での引取り」です。
一般的な「買取」や「寄付」との違い
「それって、不動産買取業者がやっていることと何が違うの?」
「市町村に寄付するのとは違うの?」
そう思われるかもしれません。違いを明確にしておきましょう。
- 不動産買取業者との違い:買取業者は、買い取った物件を転売したり、開発したりして利益を得ることを目的としています。そのため、利益が見込めない物件(状態が悪すぎる、立地が悪いなど)は買い取らないか、非常に安い価格での買取となります。私の引取りは、利益を第一目的としていません。あくまで「オーナー様の負担軽減」が主眼です。
- 自治体への寄付との違い:自治体によっては、不動産の寄付を受け付けている場合があります。しかし、多くの場合、活用見込みのない不動産や、管理に費用がかかる不動産の寄付は断られるケースがほとんどです。寄付を受け付けてもらえず、結局手元に残ってしまう…ということも少なくありません。
「解体費用半額負担での引取り」の仕組み
具体的な仕組みは、以下の通りです。
- 解体費用の見積もり:まず、その空き家を解体するのに、いくらかかるか、信頼できる複数の解体業者から見積もりを取ります。(業者選定も私がサポートします)
- 費用の分担:算出された解体費用の「半額」を、あなた(オーナー様)にご負担いただきます。
- 引取り契約と所有権移転:解体費用の半額をご負担いただくことを条件に、残りの解体費用と、その空き家(建物と土地)の所有権を、私(藤本)が引き取ります。所有権移転登記の手続きも、責任をもって行います。
これにより、あなたは通常の解体費用の半額の負担で、空き家に関するすべての所有者責任(管理義務、税金の支払い、将来のリスク)から完全に解放されることになります。
なぜ、藤本がそんなことを?
「藤本さん、そんなことして損しないの?」
心配してくださる方もいますが、大丈夫です(笑)。
確かに、短期的に見れば、私にも費用負担が発生します。
しかし、冒頭でもお話しした通り、私の活動はライフワークであり、空き家問題の解決に貢献したいという想いが根底にあります。
高額な解体費用がネックとなって、危険な空き家が放置され続ける…。そんな状況を少しでも減らしたいのです。
****
また、私は全国で空き家再生に取り組む「日本の空き家研究所」代表の竹田さんと共に活動しており、そのネットワークやノウハウも活用しています。竹田さんの「どんな空き家も、見方を変えれば価値がある」「負担なく未来へ繋ぐ」という理念に、私も深く共感しています。
引き取らせていただいた土地は、すぐに転売して利益を得ようとは考えていません。
時間をかけて、その土地や地域に合った活用法(例えば、地域の小さな公園や菜園、将来的なコミュニティプロジェクトの用地など)を模索していきたいと考えています。
どんな場合に利用できる?
この「半額負担引取り」は、あくまで他の活用方法が難しい場合の最終手段という位置づけです。
すべての空き家が対象となるわけではありません。
基本的には、
- 提案①、②の活用が、建物の状態や立地などから客観的に見て困難であると判断される場合
- オーナー様ご自身が、活用ではなく、早期の手放しを強く希望されている場合
- 相続人間で意見がまとまらず、共有者全員が引取りに同意される場合
などが対象となり得ます。
まずは、他の活用方法の可能性を十分に検討させていただき、それでも難しい場合に、この選択肢をご提案させていただく流れになります。
****
もしあなたが、「もう解体するしかない、でも費用が…」と八方塞がりの状況にあるのなら、最後の選択肢として、この方法があることを覚えておいてください。
解体費用の負担を軽くしたい…
「うちの家、引取りの対象になる可能性はある?」「具体的な負担額は?」諦める前に、一度ご相談ください。状況を詳しくお伺いし、最善の方法を一緒に考えます。
…以上が、私、藤本からの3つの提案でした。
「まるっと管理代行」
「倉庫・資材置き場活用」
「解体費用半額負担での引取り」
これらの方法は、一般的な不動産の常識からすると、少し変わっているかもしれません。
しかし、空き家問題という、画一的な解決策だけでは対応しきれない複雑な課題に対して、少しでも多くの選択肢を提供したい、という想いから生まれたものです。
あなたの留萌市の空き家が、どの方法に当てはまるか、あるいは、これらの方法を組み合わせることで解決できるかもしれません。
大切なのは、あなたの状況と想いに、最も合った方法を見つけること。
そのために、まずはあなたの声を聞かせていただけませんか?
留萌市で使える?空き家に関する支援制度・補助金について(再掲・詳細情報)

空き家対策を進める上で、少しでも費用負担を軽くしたい、というのは誰もが思うことですよね。
そこで期待されるのが、国や自治体が用意している支援制度や補助金です。
前の章で、補助金をあてにしすぎるリスクについてお話ししましたが、もちろん、うまく活用できれば非常に大きな助けになります。
この章では、留萌市において、空き家に関連して利用できる可能性のある支援制度や補助金について、もう少し詳しく見ていきましょう。
【最重要:はじめにお読みください】
ここでご紹介する情報は、あくまで一般的な可能性や過去の事例に基づくものです。
補助金制度は、毎年度、内容(対象、金額、条件、期間、予算など)が変更されたり、新設・廃止されたりすることが非常に頻繁にあります。
また、予算には限りがあるため、申請期間内であっても、予算がなくなり次第、受付が終了してしまうことも少なくありません。
したがって、本記事の情報を鵜呑みにせず、必ず最新かつ正確な情報を、留萌市の公式ウェブサイトで確認するか、市役所の担当窓口(例えば、都市整備課、建築住宅課、まちづくり推進課など、制度によって担当が異なります)に直接お問い合わせください。
検索する際は、「留萌市 空き家 補助金 2025」のように、年度を含めて検索すると、最新情報が見つかりやすいかもしれません。
(参考:留萌市役所 公式ウェブサイト https://www.city.rumoi.hokkaido.jp/ )
この点を十分にご理解いただいた上で、読み進めてください。
どんな種類の補助金が考えられる?(一般的な例)
全国の自治体で実施されている空き家関連の補助金には、主に以下のような種類があります。留萌市でも、これらのいずれか、または類似の制度が実施されている(あるいは過去に実施されていた)可能性があります。
1.空き家等の解体費用に対する補助
- 目的:管理不全で危険な状態にある空き家や、倒壊の恐れがあるブロック塀などの除却(解体・撤去)を促進し、安全確保や景観改善を図る。
- 対象となる空き家(例):
- 市が実施する老朽度判定などで「危険」と判断された空き家
- 「特定空家等」に指定(または指定される可能性が高い)空き家
- 一定期間以上(例:1年以上)居住その他の使用実績がない空き家
- 耐震基準を満たしていない空き家 など
- 補助対象者(例):
- 空き家の所有者(個人、法人)またはその相続人
- 市税等を滞納していないこと
- 暴力団員等でないこと など
- 補助対象経費(例):
- 解体工事費(建物本体、基礎、付帯物など)
- 廃材の運搬・処分費 など
※家財道具(残置物)の処分費用は対象外となることが多いです。
- 補助率・上限額(例):
- 補助対象経費の〇分の1(例:1/2、1/3、1/5など)
- 上限額 〇〇万円(例:30万円、50万円、80万円など)
※補助率は、市の基準額と比較して低い方が適用される、といった計算方法の場合もあります。
- 注意点:
- 交付決定前に工事契約・着工した場合は対象外となるのが一般的です。必ず申請し、交付決定通知を受けてから工事を開始する必要があります。
- 解体業者は、市内の業者に限る、といった条件が付く場合があります。
- 補助金を受けた場合、一定期間、土地の適正管理が義務付けられることがあります。
- 留萌市での状況:過去に実施されていた可能性、または現在も実施されている可能性があります。特に、危険な状態の空き家に対する解体支援は、多くの自治体で重視されています。必ず市の最新情報をご確認ください。
2.空き家の改修(リフォーム)費用に対する補助
- 目的:空き家を居住可能な状態に改修し、再利用(移住者の受け入れ、子育て世帯向け住宅、地域交流拠点など)を促進する。
- 対象となる空き家(例):
- 空き家バンクに登録されている物件
- 一定期間以上、居住その他の使用実績がない物件 など
- 対象となる改修工事(例):
- 居住に必要な基本的な改修(屋根、外壁、内装、水回りなど)
- 耐震改修工事
- バリアフリー改修工事
- 省エネルギー改修工事(断熱、高効率給湯器など)
- 地域交流スペースや、お試し移住施設等への用途変更に伴う改修 など
- 補助対象者(例):
- 空き家の所有者
- 空き家を購入または賃借して改修する移住者、子育て世帯 など
- NPO法人や地域団体 など
※所得制限などの要件が付く場合があります。
- 補助率・上限額(例):
- 補助対象経費の〇分の1(例:1/2、1/3など)
- 上限額 〇〇万円(例:50万円、100万円、200万円など)
※工事内容や対象者によって補助率や上限額が異なる場合があります。
- 注意点:
- 解体補助と同様、交付決定前の契約・着工は原則対象外です。
- 補助対象となる工事内容が細かく定められていることが多いです。(DIYは対象外、特定の設備機器は対象外など)
- 改修後の用途(例:〇年間は居住する、地域に開放するなど)に条件が付く場合があります。
- 施工業者は、市内の業者に限る、といった条件が付く場合があります。
- 留萌市での状況:移住・定住促進や、子育て支援、地域活性化の観点から、改修費補助制度が設けられている可能性があります。特に、市の「空き家バンク」制度と連携している場合が多いです。
3.空き家バンク関連の支援
- 目的:空き家バンク制度への登録や利用を促進し、空き家の流通・活用を図る。
- 支援内容(例):
- 登録奨励金:空き家をバンクに登録した所有者に対して、奨励金(例:数万円)を支給。
- 家財道具処分費補助:バンク登録物件の所有者が、家の中の不要な家財道具を処分する費用の一部を補助。
- 成約奨励金:バンクを通じて売買・賃貸契約が成立した場合に、所有者や利用者に奨励金を支給。
- バンク利用者の改修費補助:バンクを通じて空き家を購入・賃借した人が、その物件を改修する費用の一部を補助(上記2と重なる部分)。
- 留萌市での状況:まず、留萌市に「空き家バンク」制度があるかを確認する必要があります。もし制度があれば、関連する支援策が用意されている可能性があります。市のウェブサイトや担当窓口でご確認ください。
4.移住・定住促進に関連する支援
- 目的:市外からの移住者を呼び込み、定住を促進することで、人口減少対策や地域活性化を図る。
- 支援内容(例):
- 移住支援金:東京圏などから移住し、特定の条件(就業、起業など)を満たした世帯・個人に対して支援金を支給(国・道・市の連携事業)。
- 住宅取得・新築・改修補助:移住者が市内で住宅を取得、新築、または改修する際の費用の一部を補助。空き家の購入・改修も対象となる場合が多い。
- 家賃補助:移住者が市内の民間賃貸住宅に入居する際の家賃の一部を、一定期間補助。
- 子育て世帯向け支援:住宅取得補助の上乗せや、その他の子育て支援策。
- 留萌市での状況:多くの地方自治体が移住・定住促進に力を入れています。留萌市でも、移住者向けの様々な支援策が用意されている可能性が高いです。市のウェブサイトの「移住・定住」関連ページなどを確認してみましょう。空き家の購入や改修を伴う移住の場合、これらの支援策と空き家関連補助金を併用できる可能性もあります(ただし、併用不可の場合もあるので要確認)。
以上はあくまで一般的な例であり、留萌市でどのような制度が実施されているかは、必ず個別に確認が必要です。
補助金申請の一般的な流れと注意点
もし、利用できそうな補助金制度が見つかった場合、申請はどのような流れで進むのでしょうか? 一般的なステップと、注意点をまとめました。
申請の一般的な流れ
- 情報収集と事前相談:
- 市のウェブサイトや広報誌などで、補助金制度の概要、要件、申請期間などを確認します。
- 不明な点があれば、必ず市役所の担当窓口に事前相談に行きましょう。自分のケースが対象になるか、必要な書類は何か、注意点は何か、などを詳しく確認します。
- 申請書類の準備:
- 申請書、事業計画書、見積書(複数社が望ましい場合も)、図面、現況写真、住民票、納税証明書、登記事項証明書など、制度ごとに定められた書類を準備します。
- 書類作成に時間がかかる場合もあるため、早めに準備を始めましょう。
- 申請書の提出:
- 定められた申請期間内に、必要書類を添えて担当窓口に提出します。郵送可能な場合もありますが、窓口で内容を確認してもらう方が確実です。
- 審査:
- 提出された書類に基づいて、市が審査を行います。書類の不備や、内容について問い合わせがある場合もあります。
- 審査には通常、数週間~1ヶ月程度の時間がかかります。
- 交付(または不交付)決定通知:
- 審査の結果、補助金の交付が決定されると、「交付決定通知書」が送られてきます。残念ながら不採択となった場合は、「不交付決定通知書」が届きます。
- 事業の実施(契約・着工):
- 【重要】必ず、交付決定通知書を受け取ってから、工事請負契約を結び、工事に着手してください。交付決定前に契約・着工してしまうと、補助金の対象外となります。
- 事業完了・実績報告:
- 工事が完了したら、定められた期間内に、実績報告書、工事写真、領収書の写しなどを提出します。
- 市による完了検査が行われる場合もあります。
- 補助金額の確定・請求:
- 実績報告書等が審査され、補助金額が確定すると、「補助金確定通知書」が送られてきます。
- その後、請求書を提出します。
- 補助金の交付(支払い):
- 請求書に基づいて、指定した口座に補助金が振り込まれます。
このように、補助金の申請から受給までには、多くのステップと時間が必要です。
補助金利用における注意点
- スケジュールに余裕を持つ:申請準備から交付決定、工事完了、実績報告、受給まで、かなりの時間がかかります。スケジュールには十分に余裕を持って計画しましょう。
- 予算と期間を常に意識する:「いつの間にか申請期間が過ぎていた」「予算がなくなって締め切られた」ということのないよう、常に最新情報をチェックしましょう。
- 交付決定前の着工は厳禁:繰り返しになりますが、フライングは絶対にNGです。
- 書類は正確・丁寧に:書類の不備は、審査の遅れや不採択の原因になります。丁寧に作成し、提出前によく確認しましょう。
- 対象経費を正しく理解する:何が補助対象となり、何が対象外なのかを正確に理解しておきましょう。消費税の扱いなども確認が必要です。
- 他の補助金との併用:国や道の他の補助金と併用できる場合と、できない場合があります。必ず確認しましょう。
- 変更・中止の手続き:計画に変更が生じた場合や、事業を中止する場合は、速やかに市に届け出る必要があります。
- 実績報告を忘れずに:工事が終わったら、忘れずに実績報告を行いましょう。これを怠ると、補助金が受け取れません。
- 記録の保管:申請書類の控え、契約書、領収書、工事写真などは、後で確認できるよう、きちんと整理・保管しておきましょう。
補助金は、手続きが煩雑で時間もかかりますが、条件に合えば大きなメリットがあります。
利用を検討する場合は、まずは留萌市の担当窓口に相談してみることから始めましょう。
****
僕自身も、お客様の空き家活用をサポートする中で、補助金申請のお手伝いをさせていただくことがあります。
ただ、あくまで主体はオーナー様ご自身であり、僕はそのサポート役に徹するというスタンスです。
なぜなら、補助金は「もらう」ものではなく、「要件を満たして申請し、審査を経て交付される」ものだからです。
もし補助金活用についてもお困りでしたら、一般的な流れや注意点について、私の知っている範囲でアドバイスさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
補助金、うちの空き家は使える?
「どんな補助金があるか知りたい」「申請手続きが難しそう…」補助金に関する疑問や不安にもお答えします。ただし、最新・正確な情報は必ずご自身で留萌市にご確認くださいね。
【留萌市版】空き家活用・処分の成功モデルケース(詳細版)
ここまで、空き家問題のリスク、一般的な解決策、そして私、藤本からのご提案についてお話ししてきました。
「理屈は分かったけど、実際に藤本さんの提案で、どんな風に解決できるの?」
そう思われる方もいらっしゃるでしょう。
そこで、ここでは留萌市を舞台にした、架空の成功モデルケースを3つ、もう少し詳しくご紹介したいと思います。
もちろん、これらはフィクションですが、私がこれまで全国で関わってきた多くの事例や、留萌市の地域特性を踏まえて作成したものです。
あなたの状況に近いケースや、解決へのヒントが見つかるかもしれません。

モデルケース1:「まるっと管理代行」で遠方の悩み解消!地域にも貢献できたAさんの場合

オーナー様の状況と悩み
Aさんは、札幌市にお住まいの40代女性。ご夫婦共働きで、小学生のお子さんが二人いらっしゃいます。
数年前に、留萌市錦町にあったご実家を、一人っ子のAさんが相続されました。
ご実家は、築45年の木造一軒家。お父様が大切に住まわれていましたが、Aさんご一家が住む予定はなく、空き家になっていました。
Aさんの悩みは、典型的な「遠方からの管理」の問題でした。
- 距離の壁:札幌から留萌までは車で2時間半~3時間。仕事や子育てに忙しい中、頻繁に帰省して家の管理(換気、掃除、庭の手入れなど)をするのは、時間的にも体力的にも大きな負担でした。特に冬場の帰省は雪道の運転も心配でした。
- 費用の負担:誰も住んでいなくても、毎年かかる固定資産税。それに加えて、火災保険料や、たまに依頼する庭の手入れ費用など、じわじわと出費がかさみます。
- 家の状態への不安:たまに帰省すると、家の中にカビ臭さを感じたり、庭が荒れていたり。「このまま放置したら、もっとひどくなるのでは…」という不安が常にありました。特に、留萌の冬の厳しさを考えると、水道管の凍結なども心配でした。
- 手放すことへの抵抗感:売却も考えましたが、生まれ育った家への愛着があり、簡単には決断できませんでした。かといって、賃貸に出すにはリフォームが必要そうで、その費用も捻出できませんでした。
- 将来への漠然とした不安:「この家、最終的にどうなるんだろう…」という漠然とした不安を抱え、ご主人とも時々話し合ってはみるものの、具体的な解決策が見いだせずにいました。
藤本からの提案と実施プロセス
そんな時、インターネットで私の活動を知り、LINEでご相談をいただきました。
まず、Aさんから家の状況や悩みを詳しくヒアリング。その後、私が実際に留萌の現地を訪問し、建物の状態を確認させていただきました。
幸い、建物は古いものの、大きな構造的な問題はなく、雨漏りなども見られませんでした。ただ、長年空き家だったため、多少の清掃や、古くなっていた給湯器の交換は必要と判断しました。
そこで、私から提案させていただいたのが「まるっと管理代行」です。
- 現状のまま活用:大規模なリフォームは行わず、現状を活かして活用すること。
- 最低限の整備:家全体の簡単な清掃と、故障していた給湯器の交換は、私の負担で行うこと。残置物(家具など)は、活用方法が決まってから、必要に応じて整理・処分すること(これも原則、藤本負担)。
- 利用者探し:私が責任をもって、この家を活用してくれる利用者を探すこと。
- 管理の代行:家賃回収、利用者対応、定期的な見回りなど、すべての管理業務を私が代行すること。
- 収益の分配:得られた家賃収入から、まず固定資産税などの維持費をAさんにお支払いし、残った利益があれば、Aさんと私とで分配すること(空室保証ではない点も説明)。
Aさんは、「本当に費用がかからないの?」「こんな古い家を借りる人がいるの?」と半信半疑でしたが、現状の負担がなくなること、家を手放さなくて済むことに魅力を感じ、私に任せていただくことになりました。
留萌市の地域ニーズとのマッチング
私は、留萌市内で地域活動を行っているNPO法人などにコンタクトを取り始めました。
留萌市でも、共働き家庭の増加に伴う「放課後の子どもの居場所」や、高齢化が進む中での「地域の交流拠点」の必要性が高まっているのではないか、と考えたからです。
そして、運良く、市内で子育て支援と高齢者支援の両方に取り組むNPO法人Bさんと繋がることができました。
NPO法人Bさんは、ちょうど活動拠点のスペースを探しており、Aさんのご実家の立地(錦町で比較的人家が集まるエリア)や間取り(和室が多く、子どもたちが宿題をしたり、高齢者が集まってお茶を飲んだりするのに適している)が、彼らのニーズに合致しました。
家賃は相場より安めに設定しましたが、NPO法人Bさんにとっては非常に魅力的であり、双方合意の上で賃貸借契約(藤本とNPO法人Bさん間)を結ぶことができました。
契約形態は、将来的にAさんが家を使う可能性も考慮し、まずは3年間の定期賃貸借契約としました。
結果とオーナー様の声
現在、Aさんのご実家は、「地域のほっとスペース」として、放課後は子どもたちの元気な声が響き、日中は高齢者の方々が集う、温かい交流の場として活用されています。
Aさんは、
- 毎年の固定資産税の負担がなくなり、さらにわずかながら収入も得られるようになった。
- 遠方から管理する手間と精神的なストレスから完全に解放された。
- 大切な実家が、取り壊されることなく、地域の中で活かされていることに、大きな喜びと満足感を感じている。
「最初は不安でいっぱいでしたが、藤本さんにお願いして、本当に良かったと思っています。まさか実家がこんな形で地域のお役に立てるなんて、夢にも思いませんでした。固定資産税の支払いがなくなっただけでも助かるのに、少しですが収入までいただけるなんて…。それに、定期的に藤本さんから家の様子や活動の報告をいただけるので、遠くにいても安心です。実家に帰る楽しみも増えました。」(Aさん談)
NPO法人Bさんからも、「安価で良い活動拠点が見つかり、地域活動の幅が広がった」と感謝されています。
このケースのように、空き家は所有者だけの問題ではなく、地域の資源として捉え直すことで、新たな価値を生み出す可能性があるのです。
モデルケース2:「倉庫活用」で解体を回避!悩める高齢オーナーCさんの場合

オーナー様の状況と悩み
Cさんは、留萌市在住の70代後半の男性。お一人暮らしです。
数年前に奥様を亡くされ、お子さんたちはそれぞれ独立して市外で暮らしています。
Cさんご自身が住んでいる家の他に、港に近いエリア(例えば、開運町や船場町あたりを想定)に、数十年前に亡くなったご両親が営んでいた小さな商店(店舗兼住宅)を相続していました。
その建物は築60年以上と古く、ここ10年以上は誰も住んでおらず、空き家状態でした。
Cさんの悩みは深刻でした。
- 建物の著しい老朽化:雨漏りは常態化し、壁の一部は剥がれ落ち、建具も歪んでいました。人が住むのは到底無理な状態でした。
- 解体費用の壁:危険な状態であることは認識しており、解体も考えましたが、見積もりを取ったところ200万円以上かかると言われ、年金暮らしのCさんには到底捻出できる金額ではありませんでした。
- 固定資産税の負担:わずかな年金の中から、使わない家の固定資産税を払い続けるのは、大きな経済的負担でした。
- 近隣への迷惑:いつ建物の一部が崩れて隣に迷惑をかけるか、強風でトタン屋根などが飛ばないか、常に心配していました。ご近所からの視線も気になっていました。
- 将来への不安:「自分が元気なうちに、この家を何とかしなければ、子どもたちに迷惑がかかる…」という強い思いがありました。
藤本からの提案と実施プロセス
お子さんから私のことを聞き、藁にもすがる思いでご相談をいただきました。
現地を拝見し、確かに居住用としての再利用は困難だと判断しました。
しかし、建物が倒壊するほどの危険性は(すぐには)ないと見受けられ、また、港に近い立地と、元店舗だったため比較的広い土間スペースがある点に着目しました。
そこで、私から提案させていただいたのが「倉庫・資材置き場」としての活用です。
- 居住目的ではなく「スペース」として貸し出す:人が住む前提ではないため、大規模なリフォームは不要。
- 最低限の安全確保:雨漏りが特にひどい箇所の応急的な補修(ブルーシート等での養生を含む)と、入口周りの片付け、危険な箇所の簡単な補強などを、私の負担で行うこと。
- 利用者探し:港に近い立地を活かし、漁業関係者や、あるいは建設・土木関係の事業者などに、「資材・道具置き場」として利用してもらえないか、私が探すこと。
- 管理代行と収益分配:契約や管理は私が行い、得られた賃料から固定資産税相当額をCさんにお支払いし、超過分があれば分配を目指すこと。
Cさんは、「こんなボロボロの建物を、本当に倉庫として借りる人がいるんだろうか…」と不安そうでしたが、「解体費用がかからず、少しでも収入になる可能性があるなら…」と、この提案を受け入れてくださいました。
地域ニーズとのマッチング
私は、留萌市内の漁業協同組合や、建設業協会などにコンタクトを取り、安価で利用できる倉庫スペースを探している人がいないか、情報収集を行いました。
すると、ちょうど市内の中堅建設会社のD社が、現場で使う資材や、冬場に使う小型の除雪機などを保管する場所を探している、という情報を得ました。
D社にとっては、新品の倉庫を借りるほどのコストはかけたくないが、雨風がしのげて、ある程度の広さがあれば十分、というニーズがありました。
Cさんの物件は、古くはあるものの、そのニーズには合致しました。
賃料は月額1万円と低めに設定しましたが、D社にとっては魅力的であり、双方合意の上で、まずは1年間の賃貸借契約(藤本とD社間)を結ぶことができました。
結果とオーナー様の声
現在、Cさんの元商店は、D社の資材や機材置き場として活用されています。
Cさんは、
- 毎月1万円の収入を得られるようになり、固定資産税の負担が実質的になくなった。
- 解体費用を心配する必要がなくなり、精神的に非常に楽になった。
- 放置状態が解消され、近隣への迷惑の心配も減った。
- 「自分が死んだ後、子どもたちに迷惑をかける」という不安が大きく軽減された。
「本当に助かりました。もう壊すしかないと諦めかけていた家が、まさかこんな形で役に立つなんて、思ってもみませんでした。毎月わずかでも収入があるというのは、年金暮らしにはありがたいです。何より、肩の荷が下りて、夜ぐっすり眠れるようになりました。藤本さんには感謝しかありません。」(Cさん談)
D社も、安価で便利な場所に保管スペースを確保でき、満足されています。
このケースのように、「住めない家」にも、視点を変えれば「スペースとしての価値」が眠っていることがあるのです。
モデルケース3:「半額負担引取り」で相続問題を円満解決!Eさん兄弟の場合

オーナー様の状況と悩み
Eさん(50代男性・東京都在住)は、2年前に亡くなったお父様が遺した、留萌市郊外(例えば、幌糠地区や大和田地区など、山間部に近いエリアを想定)にある一軒家を、弟さん(北海道旭川市在住)と妹さん(大阪府在住)の3人で相続しました。
その家は、築70年近い古い農家住宅で、長年空き家になっており、老朽化が非常に激しく、屋根は一部抜け落ち、壁も崩れかけているような状態でした。
立地も最寄りのバス停から遠く、アクセスが悪いため、活用は極めて困難でした。
Eさん兄弟が抱えていた悩みは、まさに「負動産」の典型でした。
- 活用不能な状態と立地:建物は危険な状態で、リフォームは現実的ではなく、賃貸や倉庫としての活用も考えられない。立地が悪いため、土地としての価値もほとんど期待できない。
- 高額な解体費用:解体業者に見積もりを取ったところ、建物の大きさやアスベスト含有の可能性もあり、400万円以上かかると言われた。
- 相続人間の意見不一致と負担の押し付け合い:
- 長男のEさん(東京)は「早く解体して問題をなくしたいが、費用負担が大きい」と考えている。
- 次男(旭川)は「兄さんが長男なんだから、なんとかしてくれ」と、やや他人任せ。
- 妹(大阪)は「解体費用なんて払えない。そもそも相続放棄したかった」と主張。
固定資産税は、とりあえずEさんが立て替えて支払っていましたが、弟さん、妹さんからの協力は得られず、不満が溜まっていました。
- 放置によるリスク増大:話し合いが進まないまま時間が過ぎ、いつ倒壊してもおかしくない状態に。「もし事故が起きたら、相続人全員の責任問題になる」という焦りがありました。
藤本からの提案と実施プロセス
Eさんがインターネットで私の「解体費用半額負担引取り」を行なっている事を知り、ご相談くださいました。
状況を詳しく伺い、現地も確認した結果、この物件は残念ながら活用は極めて困難であり、解体する以外に現実的な選択肢はないと判断しました。
そこで、Eさん、弟さん、妹さんの3人とのオンラインでの面談を設定させていただき、以下の提案を行いました。
- 現状の確認とリスク共有:まず、建物の危険な状態と、放置し続けることのリスク(損害賠償責任など)を、相続人全員に改めて認識していただきました。
- 解体費用の再見積もり:私が信頼できる複数の解体業者(地元業者も含む)に相見積もりを取り、最も妥当な金額(結果的に約380万円)を提示しました。
- 「解体費用半額負担引取り」の提案:解体費用380万円の半額である190万円を、相続人3人で(あるいは主にEさんが)負担していただければ、残りの190万円と、この空き家(土地・建物)の所有権を、私が責任をもって引き取る、という提案です。
- 相続人間の合意形成サポート:弟さん、妹さんに対して、この提案が現状の問題を解決するための最も現実的で負担の少ない方法であることを、丁寧に説明しました。「何もしない」という選択肢のリスク、共有名義のまま放置するデメリットなどもお伝えし、合意形成を促しました。
最初は難色を示していた弟さん、妹さんも、具体的な費用負担額(一人あたり約63万円)と、これで長年の問題から完全に解放されるというメリットを理解し、最終的に3人全員の同意を得ることができました。
その後、相続人全員と私との間で引取りに関する契約を結び、所有権移転登記を行い、私が新たな所有者となりました。
費用負担分はEさんからお支払いいただき、私は引き継いだ物件の再活用法を引き続き検討しています。
結果とオーナー様の声
Eさん兄弟は、
- 高額な解体費用の全額負担(一人あたり約127万円)を免れ、負担を半減(一人あたり約63万円)させることができた。
- 長年、兄弟間の懸案事項だった空き家問題が、円満に解決した。
- 管理責任、税金支払い、将来のリスクといった全ての悩みから解放された。
「本当に、肩の荷が下りました。兄弟で何度も話し合っては平行線で、もうどうしようもないと諦めかけていました。解体費用も高くて、正直途方に暮れていたんです。藤本さんの提案は、まさに救いの手でした。費用負担はありましたが、これで全ての問題が解決するなら、と決断しました。丁寧に進めていただき、兄弟間の関係も壊れずに済み、本当に感謝しています。」(Eさん談)
このケースのように、活用が困難で、相続問題も絡んで複雑化しているような「どうしようもない」空き家に対しても、解決の道筋をつけることができる場合があります。
—
以上、3つのモデルケースをご紹介しました。
あなたの状況とは異なる部分もあるかと思いますが、空き家問題の解決には、画一的な方法だけでなく、柔軟な発想と、状況に応じたオーダーメイドの対応が必要であることを、感じていただけたのではないでしょうか。
あなたの空き家は、どのケースに近いですか?
「うちも似たような状況かも…」「こんな場合はどうなるの?」あなたの具体的なお悩みや状況をお聞かせください。最適な解決策を一緒に見つけ出します。
よくあるご質問(FAQ)

空き家のこと、私の活動について、これまでに多くのご質問をいただいてきました。
ここでは、特に多く寄せられるご質問とその回答をまとめました。
ご不明な点があれば、まずはこちらをご確認いただけますでしょうか。
もちろん、ここにないご質問も、LINEでお気軽にお問い合わせくださいね。
- 本当に相談は無料なんですか?
-
はい、ご相談は完全に無料です。公式LINEにて受付をしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
- 藤本さんは大阪在住とのことですが、大阪から遠方の物件でも本当に対応可能なんですか?
-
はい、全く問題ありません! 僕は全国の空き家に対応しています。パートナーである「廃墟不動産投資家の村上氏」「日本の空き家研究所代表の竹田氏」のネットワークもありますので、地域に関わらず、まずはご相談ください。距離は問題になりませんよ。
- 築年数がかなり古い家、ボロボロで雨漏りもするような家でも相談できますか?
-
はい、どんな状態の家でも、まずはご相談ください。 「こんな状態じゃ誰も見向きもしないだろう…」とご自身で判断せずに、まずは現状をお聞かせください。LINEで写真(外観・内観)を送っていただけると、より具体的なお話ができます。諦める前に一度、可能性を探らせてください。
- 一軒家だけですか? アパートの空き部屋でも相談可能ですか?
-
はい、一軒家だけでなく、アパートでもご相談可能です。まずは物件の種類と状況をお知らせください。
- 家の中に荷物(家具や生活用品など)がたくさん残っている状態でも大丈夫ですか?
-
はい、残置物がある状態でも全く問題ありません。 ご自身で片付けるのが大変な場合も、ご相談ください。空き家の中に残置物がそのままの場合でも対応することも可能です。そのまま活用できる家具などは、次の入居者に使ってもらうこともあります。
- 相続した物件で、兄弟(姉妹)と共有名義になっているのですが、相談できますか?
-
はい、共有名義の物件でも、ご相談は可能です。ただし、最終的に管理代行契約や引取り契約を結ぶ際には、原則として共有者全員の同意が必要になります。もし、相続人間で意見がまとまらずお困りの場合も、どうすれば合意形成ができるか、解決に向けてのアドバイスやサポートをさせていただきます。
- 管理代行をお願いした場合、固定資産税はどうなりますか? 他に費用はかかりますか?
-
管理代行の場合でも、固定資産税・都市計画税の支払い義務は、引き続き所有者様にあります。僕の目標は、家賃収入でこれらの税金をカバーし、さらにプラスの収益をお返しすることです。その他の費用については、前述の通り、貸し出すための最低限の簡易修繕(雨漏り補修、給湯器交換など)は原則僕が負担しますが、それ以上の大規模な修繕が必要になった場合などは、別途ご相談となります。契約前に費用負担については明確にご説明しますのでご安心ください。
- 管理代行の家賃収入は保証されるのですか? いわゆるサブリース契約とは違うのですか?
-
僕の管理代行は、不動産会社がよく行う、空室期間も一定の家賃を保証する「サブリース契約(家賃保証付き借り上げ)」とは全く異なります。借り手が見つかってから、オーナー様への家賃収入からお支払いさせていただきます。できるだけ早く、そして安定的に借り手が見つかるよう、僕も最大限の努力をすることはお約束します。
- 相談した内容や、個人情報が外部に漏れることはありませんか?
-
はい、ご相談内容は秘密厳守をお約束します。お預かりした個人情報や物件情報は、空き家問題の解決という目的以外で利用することは一切ありません。また、外部に漏洩することがないよう、厳重に管理いたしますので、どうぞご安心ください。
いかがでしたでしょうか?
少しでもあなたの疑問や不安解消の助けになれば幸いです。
もし、さらに聞きたいこと、確認したいことがあれば、本当に遠慮なく、下のLINEからメッセージを送ってくださいね。
ご相談内容は秘密厳守いたしますので、ご安心ください。
FAQで解決しない疑問はLINEで!
あなたの状況は、他の誰とも違います。個別の疑問や、もっと詳しい話が聞きたい場合は、LINEで直接お尋ねください。丁寧にお答えします。
さいごに:留萌市の空き家、未来への一歩を

長い時間、この記事にお付き合いいただき、本当にありがとうございました。
北海道 留萌市にある、あなたの大切な空き家・ご実家。
その処分や活用について、放置するリスクの大きさ、一般的な解決策の難しさ、そして、私たちが提案する「負担の少ない」解決への道筋について、できる限り詳しくお伝えしてきました。
空き家の問題は、本当に複雑で、一筋縄ではいかないことが多いです。
経済的な負担、管理の手間、老朽化への不安、相続の問題、そして何より、思い出の詰まった場所への愛着…。
様々な要素が絡み合い、どうすれば良いのか分からなくなってしまう気持ち、痛いほどよく分かります。
****
でも、どうか忘れないでください。
あなたは、一人ではありません。
そして、どんなに困難に見える状況でも、必ず解決策はあります。
大切なのは、問題を先送りせず、勇気を出して「最初の一歩」を踏み出すこと。
その一歩が、あなたを長年の悩みから解放し、そして、あなたの空き家を、もしかしたら留萌市の未来にとって価値あるものへと変えるきっかけになるかもしれないのです。
私が提案させていただいた「まるっと管理代行」「倉庫活用」「半額負担引取り」は、
「オーナー様の費用と手間を、限りなくゼロに近づけたい」
「画一的な方法ではなく、一つ一つの空き家、一人一人のオーナー様に寄り添った解決策を見つけたい」
という、私の強い想いから生まれたものです。
もちろん、これが唯一の正解ではありません。
でも、もしあなたが、これまでの方法では解決が難しいと感じているなら、あるいは、何から手をつけて良いか分からないと途方に暮れているなら、ぜひ一度、私にあなたの声を聞かせてください。
相談は、完全に無料です。
そして、相談したからといって、無理に契約を迫るようなことは絶対にありません。
私の活動は、利益優先のビジネスではなく、ライフワークですから。
まずは、下のボタンからLINEでメッセージを送ってください。
「留萌市の空き家の件で相談したい」
「記事を読んだけど、うちの場合はどうなる?」
そんな簡単な一言で構いません。
空き家の住所や状況、お分かりになる範囲で構いませんので、教えていただけると、より具体的なお話ができます。
もちろん、LINEで空き家の写真を送っていただくだけでもOKです。
(ご相談内容は秘密厳守いたしますので、ご安心ください)
問題を放置して、リスクが大きくなってしまう前に。
手遅れになって、後悔してしまう前に。
今、この瞬間が、あなたの未来を変えるチャンスかもしれません。
日本海の風が吹き抜ける美しい街、留萌市。
その街の未来のためにも、一つでも多くの空き家が、負担なく、そして適切に管理・活用されることを、心から願っています。
あなたからのご連絡を、お待ちしています。
一緒に、最善の解決策を見つけましょう。
【無料】今すぐLINEで相談する
もう一人で悩まないでください。あなたの空き家問題、必ず解決策があります。まずは下のボタンから、お気軽にご連絡ください。相談だけでも大歓迎です!
※本記事の情報は2025年05月時点のものです。
※本記事で紹介している支援制度や補助金の情報は2025年05月時点のものです。最新の正確な情報は必ず北海道 留萌市公式ウェブサイトでご確認ください。
※本記事は空き家に関する一般的な情報提供を目的としており、特定の物件に対する法的、税務的、あるいは投資上のアドバイスを提供するものではありません。









